防災月間の教育・訓練は脱マンネリを意識
第13回:防災月間を考える

本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
2025/09/20
これだけは社員に伝えておきたいリスク対策

本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
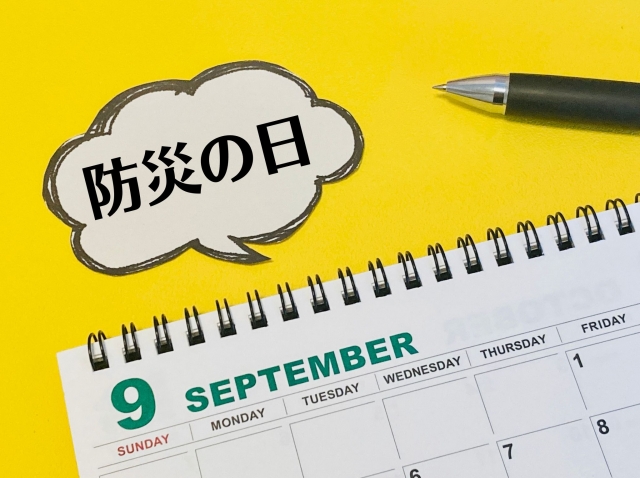
毎年9月が近づくと全国的に防災に関する情報が発信されますが、これは9月1日の「防災の日」のタイミングを踏まえたものと言えるでしょう。防災の日(1960年に閣議決定)は、1923年9月1日に発生した関東大震災がその由来となっており、また9月は「防災月間」とされています。
企業は、「防災月間」のタイミングで、BCPの見直しを行う、また避難訓練を行うとともに、あわせて従業員への防災意識の啓発なども進めています。今回は、防災月間について考えます。
防災月間に、BCPの見直しを実施する企業も増えています。ただ、BCPの見直し自体は、必ず9月に実施しなくてはならないものではありません。

BCPの見直しは定期的に、つまり1年に1回以上見直すことが重要です。一度BCPを策定しても、見直さないまま経過すると、その内容は実態にそぐわないものとなってしまいます。例えば、複数の新規事業をスタートさせたにもかかわらず、中核事業の見直しをしていなければ、緊急時のおける事業の復旧、そして継続について的確な対応ができません。
また、BCPに人事異動や入退職者が反映されていなければ、BCPの運用にも支障が生じます。定期的に見直しをするということであれば、人事異動や組織変更のタイミングに合わせて、4月に行うということでもよいでしょう。
あわせて、実際に被害に見舞われた場合は、その際の初動対応や事業復旧対応後の検証などを踏まえて、BCPを見直すことも必要です。
防災月間のタイミングをとらえて、従業員を対象とした教育や訓練を実施する企業も多くあります。教育や訓練は、あくまで平常時に行うものですが、定期的に実施することで、発災時に速やかに行動できることを目指します。
新たに入社した従業員については、自社の防災体制やBCPの概要を説明しますが、その際、内容をまとめた小冊子やハンドブックを配布するとよいでしょう。また、既存の従業員には、防災体制の見直しやBCPの改訂にあわせて、その内容を周知するためにも定期的に教育の機会を設けることが望ましいでしょう。
あわせて、従業員の自宅における防災教育も大切です。建物の耐震性やハザードマップの確認、そして防災備蓄の消費期限の確認などを推奨します。
安否確認訓練、避難訓練、そして応急処置訓練などは、実際、毎年実施していたとしても、マンネリになっていないでしょうか。

これらの訓練は、特定の行動、例えば、いざという時に避難行動を的確に行えるように、何度も繰り返すことでその習熟度のレベルを向上させることになります。逆に言えば、「避難訓練」を毎年やっていても、安否確認や応急処置の水準は上がりません。
定期的に実施する場合でも、「春は安否確認訓練、そして秋は避難訓練」のように、さまざまな訓練を繰り返すことで習熟度を向上させていきましょう。
これだけは社員に伝えておきたいリスク対策の他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26



報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23


※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方