2016/06/14
直言居士-ちょくげんこじ
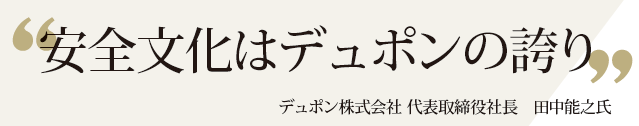

「実は昔、ヘッドハンティングで転職を誘われたことがあるのですが、その会社の安全文化に対する取り組みに納得がいかなかったためにお断りしました」と快活に話してくれたのはデュポン株式会社代表取締役社長の田中能之氏。「コアバリュー(企業理念)にもある通り、安全文化はデュポンの経営の根幹であり、私たちの誇りです」と胸を張る。
デュポン社は1802年、米国で黒色火薬の製造会社として設立した。危険物質を扱うため、設立当初から「川沿いに工場を建てる」「金属を使わない靴を支給する」「作業着のポケットをなくす」「新しい設備はトップマネジメントがスイッチを入れて安全を確かめる」など、安全に対して積極的な経営を行ってきた。1811年には最初の安全ルールを確立。現在では「農業・栄養&健康分野」「バイオプロセス・ソリューション分野」「高機能製品・素材分野」を中心に世界中で事業を展開する、210年以上の歴史を誇るサイエンスカンパニーだ。
日本では1961年に現在のデュポン株式会社の前身となるデュポンファーイースト日本社が設立。田中氏は1982年に東京大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程を卒業後、同社に入社した。入社当時からデュポンの安全に対する取り組みに対して「面白いな」と共感していたという。
例えばデュポンでは、全世界において社長以下、従業員全員が、階段では手すりにつかまることがルールになっている。就業中、あるいは就業後に関わらず、会社であろうと駅であろうと、階段ではかならず手すりにつかまらなければならない。さらにユニークなのは、社長であっても手すりにつかまっていないところを社員に見つかれば注意され、注意をした社員には「ありがとう」と感謝をするという。
また、田中氏が入社した当時から、デュポンでは車に乗る場合に後部座席に座る人もシートベルトを着用することを義務付けていた。まだ日本ではドライバーのシートベルト着用のみが義務付けられていた時代だ。田中社長は「日本でシートベルトの法律ができたころには、私は車のどこの座席に座ってもシートベルトをする習慣がついていました。デュポンは社内のルールがその国の法律より上まわっていれば、社内のルールを優先し、その国の法律が上まわっていれば、その国の法律を優先する。常に厳しい方に合わせているんです」と話す。
グローバルで事業を展開しているデュポンは、ルールも世界共通だ。タクシーの話1つとってみても、例えば中国ではシートベルトがないタクシーも多いため、必ずシートベルトを完備しているタクシーを予約しなければならないという。
ほかにもリスクコミュニケーションとして、社内で行うほぼ全ての会議の冒頭で「セーフティコンタクト」と題し、安全に関して気づいたことを話し合う場を設けている。アジア太平洋地域では、年に一度は「リフレッシャーズトレーニング」として、全社員が安全に関する講習を受ける。日本国内はもとより、世界を見渡してもこれだけ「安全文化」が根付いている企業は珍しいだろう。
デュポンには、フェルト・リーダーシップ(Felt Leadership)という独特の言葉がある。これは「リーダーは率先垂範する」という考え方で、安全衛生環境活動においては、役職だけでなく「社員全員がリーダーのつもりでリーダーシップを発揮する」ことが期待される。
田中氏は「社員全員がフェルト・リーダーシップを持ち、安全に関して常に当たり前のものとして取り組んでいる。これがデュポンの安全に関する強み」と話している。
編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年9月25日号(Vol.51)掲載の記事を、Web記事として再掲したものです。(2016年6月15日)
(了)
- keyword
- 直言居士-ちょくげんこじ
直言居士-ちょくげんこじの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方