2016/12/20
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
11 、やっぱり無理だ。いちかばちか流しちゃえ!とした場合の責任問題
東日本大震災の無料法律相談事例集(日本弁護士連合会)には、下水道か上水道か明らかではありませんが、水漏れ事例が記録されています。
ケース188 震災で上階から漏水。マンション自室が水浸しになり、修繕に200万かかる予定。上階の所有者に修繕費を出してもらいたいが回答がない。近々マンション管理組合の集会に諮(はか)る予定
「東日本大震災無料法律相談事例集(日本弁護士連合会)」より引用
熊本地震でご自身も被災された 弁護士法人リーガル・プロ代表で弁護士の鹿瀬島正剛氏(http://www.legal-pro.jp)にお話を伺ったところ、熊本地震でも通常の水漏れの相談はあったとのこと。そして通常の水漏れが、地震だけを原因として漏れていたのに対し、震災後、配水管などの確認前にトイレで水を流すのは、自らの行為が介在するので不法行為による過失が認定される可能性もあるとのことです。
隣や上の階といった隣人ともめるとその後の生活が苦しくなるので、東日本大震災や熊本地震では訴訟ではなく、震災ADR(※)による調停が多く選択されていました。住民が多く、引越も多い地域であれば、訴訟の可能性も高くなるかもしれません。
また、地震保険に加入していたとしても、階下への水漏れなど、第3者への損害は、保証対象ではありません。損害賠償責任を負うとなると保険でカバーされないのです。以下、とある損害保険会社のホームページのQ&Aには以下のように掲載されていました。
Q,地震で水道管が破裂し階下へ被害を与えてしまいました。自分の地震保険か火災保険で階下の損害を補償してもらえますか?
A,いいえ、地震により他人に与えてしまった損害については、ご自身の火災保険・地震保険いずれでも補償されません。
(注:ただし、一般社団法人日本損害保険協会によれば、この場合でも「階下の人」が地震保険に加入して入れば、「階下の人」の地震保険が有効になる可能性があるとのこと。最後まであきらめずに確認してくださいね。また、上記をもって地震保険に入らなくてもよいとは思わないでください。加入によって生活再建のスピードは格段に速くなる可能性がありますし、意外なメリットもあります。詳しくはまた後日のリスク対策.comにて!!)
さらに、企業であれば、災害復興や企業BCPに詳しい丸の内総合法律事務所の弁護士の中野明安氏が「企業には従業員に対して安全配慮義務があり、災害時にトイレ施設の維持・管理を怠った場合には安全配慮義務違反が問われる可能性がある」ことを指摘されています。
■まずはトイレを備蓄せよ!
災害時にトイレの備えがなければ安全配慮義務違反?
http://www.risktaisaku.com/articles/-/525?page=3
たった一回、「いちかばちか流しちゃえ!」としたことで、負うかもしれない責任はもう想定外ではありません。
ADRとは、判決等の裁判によらない紛争解決方法をいいます。
弁護士会のADRは、弁護士が、中立の立場で「和解のあっせん人」となって、当事者の言い分をよく聞いて、ときには、双方に、有益と思われる「あっせん案」を提示するなどして、当事者間での自主的な解決、すなわち、和解による解決を援助、促進する手続です。
このように、弁護士会ADRは、話し合いによる円満な解決を目指す手続です。
法的紛争に関して、当事者間で話し合いの余地があって、双方が、弁護士という法律の専門家から事情に応じた法的助言を得ることで、互いに歩み寄る可能性があるような事案に有効であるといえます。
熊本弁護士会HPより
http://www.kumaben.or.jp/soudan/jishin/adr/
12、使用済みペーパー、ためるとNG

ところで、引用した東京防災にはもうひとつ気になることが書いています。「トイレットペーパーは流さずゴミとしてすてます」(P200)とあり、P60の上のイラストでは、トイレ横に使用済みペーパーをためる箱が設置されています。
しかし、ためておくと汚物が乾燥し、空気中に浮遊するので衛生上の問題や感染症の問題がでてきます。
水は流さず1度目から災害用トイレを設置。その中に使用済みペーパーを入れ早めにゴミとして処理。ペーパーは別途ためない。どうか、間違えないようにお願いします。
さて、年内最後の来週は災害時のトイレ問題最終編!
避難所におけるトイレの感染症などの衛生問題や、男女のトイレの在り方などについて考えてみます。次回もお楽しみに♪
(了)
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事
おすすめ記事
-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

-











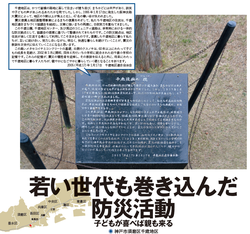














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方