2017/01/17
誌面情報 vol47
Oral History07 神戸の人々の士気を高めるのが我々の務めやないか
生田神社 宮司(当時)加藤隆久氏
聴取日:1998年10月6日
神戸は「生田の神を守る民か家」
もう何がなにやらぐちゃぐちゃになっているところを拝殿へ向かって飛び出したところ、昨日、夕拝をし、夕べのお祈りをして帰ってきたあの拝殿が倒壊してるんです。余震の度に楼門がだんだん傾いてくる。これは早く処理しないといかん、と思いました。この楼門を設計した竹中工務店の鎌谷憲彦という設計部長が17日の夜、暗闇の中を西宮から自転車でやってきた。被害を受けたオーナーに会ったところみんなしょぼんとしている。しかし、生田神社にきたときに「鎌谷さん、この桜門すぐに工事にとりかかってください」と言うと「ええっ、宮司だけですわ。そんなに元気なの」と言われた。 私はあの震災の時に、この神戸という地名は「生田の神を守る民や家」という意味の「カンベ」じゃないかと感じました。この神戸の大氏神さんまで潰れたまま放置されているのは、これはもう一番人々の士気に拘わる。だからとにかく早く復興することによって、神戸の人々の士気を高めるのが我々の務めやないかと。
避難者は入れない
(他の神社は)避難者のテントや仮設住宅を入れさせた。うちの職員も「ここもテントを入れさせてよいか」と言った。反対した宮司はわしだけです。「アカン」と。「まず被災した神社を復興させる。俺はもう鬼になって神社を護っていくから、これの復興にみんな当たってくれ」と言った。
確かに困っている人々を境内に入れて、テントや仮設住宅などを何とかしてと。しかしそれは僕の体験からすると大変困る事態になる。僕は心を鬼にして「まず神社の復興、神社が復興し美しくなったら地域に活気が出てきて、みんなに喜ばれるんやから」ということで私の言う通りになりました。
一人としてリストラしない
復興にはお金がかかります。おそらく周辺氏子がすべて駄目で支援は望むべくもありません。建物は重要文化財でもありませんから、国や県の支援もないでしょう。ただ、平素からあらゆるものを節約して営繕資金をここ10年以上蓄えておりました。会計部長に積立金がどれくらいあるのか尋ね、そして、建築計画を立て、なんとかいけるめどが立ったのです。私は職員に、復興できるまでテント生活をしながらがんばろうと言い、「一人として職員をリストラしない」と明言しました。若い職員や巫女さんがこうしたときに必要になると思ったからです。
復興していく姿をPR
生田神社の被害状況やあの倒壊した姿は世界中にPRされている。これを逆手にとって復興していく姿をさらにPRすることにより、氏子の人々に理解してもらい、支援の輪を広げようと決心しました。拝殿にくる人々に職員が震災の状況を写真からパネルにして掲げ、説明しました。他の神社で、氏子が崩壊しているのに神社の復興が早すぎるとクレームのついたところもあったようですが、私は、神社の復興こそが氏子の人々の精神的復興を推進する第一であるとの信念でやってきました。
先を見越した投資
神社境内に付属の立体駐車場があるのですが、あの地震で甚大な被害を受けました。すぐ解体にとりかかりましたが、新しく再建すると5億の工事費がかかるから3基の立体駐車場は止めにしたらどうかという意見が大半でした。しかし、この周辺のこれからを考えたときにどうしても3基の立体駐車状は必要だと予測したのです。というのは、三宮周辺で復興工事がはじまると工事の車や乗用車や緒々の車が集中してくるだろうと。するとたちまち駐車難に陥り、車が溢れる。したがって、いの一番に建設すべきは立体駐車場であると思ったのです。おかげで、連日満車で1年半後には借入金を返済することができました。
常に備えよ
本人にとっても身の縮むような思いをしたわけですが、これから一寸先は闇でどんなことになるかわからなんから、職員にいつも「常に備えよ」と言っており、いろいろ考えておかないといかんというふうに思うんです。
(了)
誌面情報 vol47の他の記事
- 「阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質」(巻頭インタビュー 京都大学防災研究所教授(現・防災科学技術研究所理事長)林春男氏)
- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (前編)
- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (後編)
- 特集1 爆速経営を妨げない ヤフーのリスクマネジメント
- ERM本質と手法 企業の成長を妨げるリスクを取り除く
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-











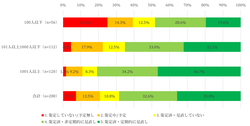















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方