2017/01/17
誌面情報 vol47
Oral History05 どんな責任も負かうら放送を最優先
兵庫エフエムラジオ放送株式会社代表取締役社長(当時)小榑雅章氏
聴取日:2002年7月24日
「助けてくれ」と言われた
私はマンションの7階にいました。「ガーン」ときたわけです。会社は24時間放送ですから泊まりがいるので電話をかけて「どうだ?」と言ったら、「放送はしているが、怖い」と言うんです。「すぐ行くから」と言って、私は歩いて外に出ましたが、まだ真っ暗でした。
すると3軒目の家がつぶれていました。ちょっと行ったところで「助けてくれ」と言われました。ただ、「自分の力と計って、絶対にこの梁は持ち上がらない」ということと「放送という使命のために、自分は絶対行かなければならない」ということを思いながら、知らぬ顔をして通り過ぎて行ったわけです。今でも嫌な思い出です。
情報を盗もう
放送局の使命としては情報を何とかして流さなければならないことでしたが、情報がどこからも何もこないという段階で、「盗もう」私はと言ったのです。自家発電がありますから大阪のテレビ放送が入ります。テレビをニュース源にすると「何とかによれば」と断って流さなくてはならないわけですが、「何でもいいから流していけ」と指示をしました。
どうやって人間を確保するかというときに、緊急用の電話が鳴って、「こられません」とある社員が言った。後になって、総務の人間がきていない社員に「大丈夫か」と電話で聞いていたんです。普通なら美談ですね。でも、私は怒りました。緊急用の電話の割り当てはうちの会社に1台しかないんですよ。そこへいろいろな情報がくるわけで、社員の安否を尋ねているのではプライオリティが違うじゃないかと。そのとき、私は「鬼」だと言われました。かなり喧嘩になりました。
放送会社が情報を流すべき義務があって、それがいかに重要か分かっているわけですが、自分の家がつぶれていると技術部長がやってこない。何をおいてもこないといけないのに翌日になって会社に来たのです。私は放送の使命を共有するという基盤がない限り組織というのは保たない、と思いました。
非常電源がなくなる
「非常電源は、社長、8時間しか持ちません」と、朝10時くらいに言われました。(午前)6時に切り替わってるので、午後2時か3時には非常電源がなくなる。油を買いに行こうにも何もないわけです。一番近いダイエーに歩いて行ったんです。震災のときにいったい何が必要だったかというと、私にとって一番重要なのはハイテクの機器とかでなく(非常電源の燃料を運搬する)ポリタンクだったんですよ。ポリタンク3つしかなかったので(私が)何回も往復したわけです。
そうやって燃料を確保しましたが、3日目になったときに「連続燃焼をこれだけしても大丈夫という設計はされてません。ボイラーが爆発するので、なんとか配電をお願いできないか頼んでください」と言われました。関電の神戸支店長が友人でしたので、そこに行き、わけを話すと1時間後にはきてくれました。
社員に「出てこい!」と言えたか
もっと大事なことは引っ越さないで大丈夫なのかということでした。夜中になると余震もあるし、なくても「ギーッ」と音が出て実際に揺れる。3日目になると少しは余裕が出てきましたが、神戸市から退去命令が出て、怖さもあった時ですので本気で引っ越すことを考えましたね。しかし、できないのですよ。
社長にしかできない判断は、この建物をどうするとか引っ越しはしないとか、燃料をどうするか、関電に掛け合うとかいう根本的な存立の問題とか、あるいは初めに情報をどうやって確保するかというようなことはありますが、後からのものは社員に任せました。基本的には陣頭指揮でやりました。
いくつかの決断をしましたが、社員に「出てこい!」と言えたか。やはり言えなかった経営者が多いと思いますよ。しかし、情報として(市民からの)FAXがどんどん入ってきたりすると、この神戸でたった1つの放送局だと思いましたから、そういう中で、どんな責任も負うからこれ(放送)を最優先にしようと思いました。
誌面情報 vol47の他の記事
- 「阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質」(巻頭インタビュー 京都大学防災研究所教授(現・防災科学技術研究所理事長)林春男氏)
- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (前編)
- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (後編)
- 特集1 爆速経営を妨げない ヤフーのリスクマネジメント
- ERM本質と手法 企業の成長を妨げるリスクを取り除く
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-












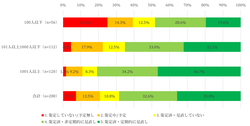















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方