2017/01/17
誌面情報 vol47
Oral History04 2日間納入しなかったら終わりです
オリバーソース株式会社 代表取締役社長(当時)道満雅彦氏
聴取日:1999年9月2日
損失額は10億3000万円
会社の売上金額が史上最高を記録したのが1994年の12月です。つまり、史上最高額を集金する予定だった3日前に、震災が起きたわけです。震災によって我々が被った損失額は銀行の計算でだいたい10億3000万円と言われています。その前年のソース売上げが21億にちょっと足りないぐらいでしたから、年商の半分以上が損失ということになります。おそらく神戸に現存している食品会社の中で、損害額は年商比でいうとトップだったと思います。
本社のあった兵庫区まで向かうと、うちの会社が燃えとったんです。ものすごい煙。コンピュータとサーバーが全焼しました。本社棟のバックアップのコンピュータは助かるかと思ったが、結局、火の粉が入って全焼しました。書類とか営業活動するためのデータベースがこの2棟にありました。
廃業まで考えた
借り入れはゼロですし自己資金で全部やっていました。借金の経験がなかったんです。借金ができるという頭がなかったので、(会社を)やめようとなりました。兵庫区内に1440坪の土地と建物の資産を持っていましたので、この土地を生かして、ここの場所にマンションを建てよう、これでは(会社は)無理やと。ソース業界でも調味料全般ですが、スーパーさんとお取引するのに発注があってから2日間納入しなかったら終わりです。1週間も滞るともう絶対出入り禁止です。だから「もうやめた言うとこ」という気分になっていたんです。
実は震災から1週間か10日ぐらいして大手食品業界の新聞が震災を取りあげて、私が結局、行方不明。それで『オリバーソース再起不能。施設は全焼』という記事が載りました。後日、大々的にそれは訂正記事を出してもらいましたけれど、それを読まれた食品業界の方は非常に多いと思います。オリバーソースを注文しても返事もこない。納入を待ってもこないということで(他社の)代替商品がかなり流れました。
我々がしっかりとしていたら大阪支店とか東京支店があるわけですから、1軒1軒スーパーにどんどん電話したらよかったんですが、それどころじゃない。みんな神戸の応援にきた。基本的にそれで正しかったと思います。一致団結してもう一度会社を再建しようという意欲、あるいは会社がどうなっているか情報を仕入れるには良かったと思いますが、ここに入ったら(神戸の外に)出られない。
今オリバーソースは再建中です
商品開発をする開発棟が無傷だった以外、工場はほとんど全焼でした。でも、「何とかなるのちゃう」「借金したらええやないか」と再建しようとなったのが2週間後くらいです。一番怖いのは得意先に荷物が着かないことですね。いろんな倉庫にあるものを大事な得意先から少しずつ出すことになりました。とりあえず、復興部隊を神戸において「今オリバーソースは再建中です」「何とかもう少しご猶予をください」とお願いしました。
混乱していて指揮系統の確立が本当に難しかった。結局、指揮官がたくさんいれば余計に交錯してダメになるということで、僕から命令1本で号令を出していた。ただ、営業に関しては私も全然情報がつかめないので営業本部長に任せて、何とか問屋さんにオリバーソースを売るところを確保してもらえるように指示しました。
再建をプラスに
後から考えて言えることですが、震災前にやりたかったことがいっぱいあったんですね。工場をきれいにしたいとか。
HACCPという衛生管理の問題や、(製造)ラインをああしたいとかこうしたいとか。工場を移転することで一気に済んだところがあります。以前の工場で本社としての機能があればこういう改革はできなかったと思います。人員は減って、商品自体はかなり良くなっていると思います。今までやりたいと思っていたことを全部やりました。
誰からも非難されずに堂々と借金もできたし、新しいシステムを作りあげるにしても真剣にそこだけに集中できるというのが良かったなと思います。
誌面情報 vol47の他の記事
- 「阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質」(巻頭インタビュー 京都大学防災研究所教授(現・防災科学技術研究所理事長)林春男氏)
- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (前編)
- Oral History 阪神・淡路大震災 経営者の証言から読み取るBCMの本質 (後編)
- 特集1 爆速経営を妨げない ヤフーのリスクマネジメント
- ERM本質と手法 企業の成長を妨げるリスクを取り除く
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-












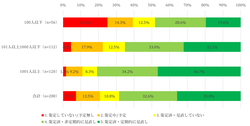















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方