2013/11/25
誌面情報 vol40
アメリカの専門家が語る日本での普及の障壁
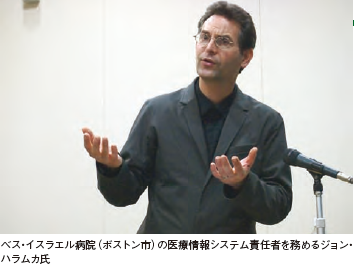
患者のカルテなど医療情報をクラウド上で管理する取り組みがアメリカで普及している。一方、日本は一般的にはクラウドは主流になりつつあるものの、医療分野については個人情報保護などを懸念する医療機関が多く、ほとんど取り入れられていない。しかし、福島第一原発事故後、福島県のある地域ではクラウドを使った試みが医療活動を支えた。日米におけるクラウド型医療情報システムの現状を取材した。
遠隔地で医療情報を共有
福島第一原発事故で放射線被害が広がった福島県。震災後の医療を支えた影にはクラウドの存在があった。
東日本大震災後、東北地方には、全国からDMAT(災害派遣医療チーム)や日本医師会に登録する医師が医療活動の支援に訪れた。しかし、福島に限っては放射線被爆を恐れ、全国からなかなか医師が集まらず、せっかく来ても滞在時間は短く、患者の診察や診断の履歴がうまく引き継がれない状況に陥った。
こうした中、九州大学大学院の永田高志助教(先端医療医学部門災害・救急医学)らが中心となり、クラウド型医療情報システムを活用した日本医師会災害医療チームJMATによる医療活動を開始。福島県新地町にある仮設診療所では、先に活動を行っていた医師と医療スタッフが手で書いていた患者600人分の紙のカルテを電子化してクラウド上で管理し、遠隔からでも患者の状況が確認できるようにした。これにより、遠方の複数の医療機関から派遣されるJMATが医療支援に入る際にはあらかじめ患者一人ひとりの診断状況を把握し、必要な医薬品を持ち込むなどの効率的な医療活動が実現した。クラウド型災害医療情報システムを用いた福島県新地町に対するJMATの医療支援活動は2011年4月15日から5月31日まで行われ、地元の医療機関の回復に併せて撤収した。

日本では、電子カルテは既に普及しつつあるものの、クラウド型の医療情報システムはほとんど普及していない。一方、アメリカでは数年前からクラウド型の医療情報システムが主流になりつつある。
2008年から独自のクラウドシステムを構築し病院の運営を行ってきたベス・イスラエル病院(米国、ボストン市)の医療情報システム責任者を務めるジョン・ハラムカ氏は、その理由として、①コストパフォーマンス、②信頼性の向上、③安全性の向上、④運用の容易性、⑤他の医療機関などとの連携の容易性など5点を挙げる。
コストパフォーマンスについては、クラウドの場合、複数の医療機関が1つのシステムを使えることから独自に電子カルテシステムなどを構築するより大幅に運用経費が下げられるとする。その効果は、最終的には患者に還元され、医療費が安くなることにつながる。
誌面情報 vol40の他の記事
おすすめ記事
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方