2018/01/09
安心、それが最大の敵だ
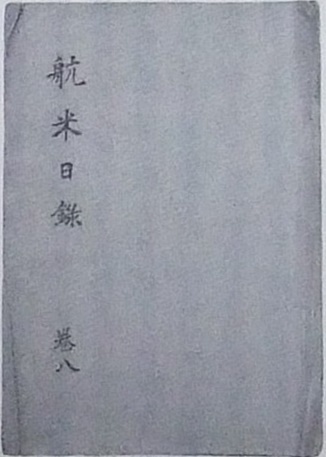
ワシントンでの観察と見解
首都ワシントンでの観察を見てみたい。玉虫左太夫は、副使村垣と異なり、女性の存在に驚いたり、複雑な礼儀に欠けていることに苛立ちを覚えたりすることはなかった。また、議事堂の訪問に際しても、村垣とは全く違った感想を述べている。
「又行くこと2町計にして議事堂あり、カビテンハウス(注:キャピトルハウス)と云う。花盛頓府(ワシントン府)第一の巨屋高さ3、4層なり。出入口四方にあり、周囲10町計にして・・・事を議するときは中央卑き所に官吏及び書記官等列出、而(しか)して其事に管する者都(ルビすべ)て毎階に列し、高きより卑き臨む。故に官吏の公私分明に見え衆をして怨を抱かしめざるなり。」(原文カタカナ、ちなみに副使村垣は議会を「我が日本橋の魚市のさまによく似ている」と愚かにも記して、同行の監察(ナンバー3)小栗忠順の失笑を買っている)。
左太夫にも他の同行者らと同様に儒教思想の背景があり、彼はまた、その後半生を徳川幕府の封建体制支持に傾倒して生きたサムライであった。彼の記録には権力の側の価値観に対する明らかな批判や挑戦を指摘することが出来る。近代西洋文明に触れた目には、忠義という縦のつながりが弛緩しているとさえ感じられる。玉虫の体制批判は控えめである。が、それでも彼は、極度に異なったアメリカ文化の中で自国に欠けていると痛切に感じた制度を発見した数少ない使節一行の一人であった。
◇
万延元年(1860)遣米使節及び咸臨丸の随員が残した旅行記、回想録のうち現存するものは約40を数えるとされる。(新見、村垣のような徳川幕府の高級官僚(幕臣)や、福沢諭吉、勝海舟のような蘭学の教養を身に着けた才気あふれる人物、さらには玉虫のような外様藩士たち、もっと身分の低い武士ではない奉公人にいたるまで、すべての階層の人びとによって書かれたこれらの記録は、未知の西洋と遭遇した際の、近代日本の夜明けの時代の徳川精神を最も適切に表している。だが「航米日録」に勝る観察記録はない。
帰国後の玉虫左太夫は、世界一周の体験や見聞に基づいて技術の重要性を感じ、食塩の製造法を研究した。文久3年(1863)、40歳の時に「食塩製造論」を著し、3年後には自ら属する東北の雄藩・仙台藩気仙沼の浜辺に製塩場を建設した。だが左太夫は不運であった。仙台藩重臣に取り立てられ小姓組並、江戸勤務学問出精を命じられ、また仙台藩学問所養賢堂指南頭取(学長)となった。
慶応4年(1868)仙台藩主の命を受けて、会津に赴き、藩主松平容保に会い佐幕連盟の約を果たした。が、仙台藩内が勤王、佐幕に分裂し、明治新政府に組しない立場を貫いた左太夫は劣勢となった。左太夫は、幕府の軍艦奉行榎本釜次郎(後に武揚)が軍艦を率いて蝦夷地(北海道)へ向かうことを聞き知って、これに乗って蝦夷地に一緒に逃げようとし、自ら造った気仙沼の製塩場に行って塩を集めて、これを榎本の軍艦に積み込み持っていこうとした。榎本武揚も、軍艦を気仙沼に寄港させ左太夫と同志門弟16人を救出しようと試みた。だが、わずか1日の差で左太夫らは捕吏に捕えられた。反対派の桜田良佐らの策謀によって反逆者の烙印を押されて、翌明治2年(1869)4月切腹自刃に追い込まれた。
享年46歳。左太夫の無念の思いはいかばかりであったろうか。明治維新後、玉虫家は家名を奪われ相続も許されず、明治22年(1889)憲法発布まで家名復興を許されなかった。明治新政府に反抗した者を容赦なく追及し罰してやまなかった非情な暴挙を、まざまざとここに見る。
参考文献:「走馬灯」(遠藤周作)、「我ら見しままに 万延元年遣米使節の旅路」(マサオ・ミヨシ)、「西洋見聞集 日本思想大系」(岩波書店)
(つづく)
- keyword
- 安心、それが最大の敵だ
- 幕末
- 玉虫佐太夫
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-










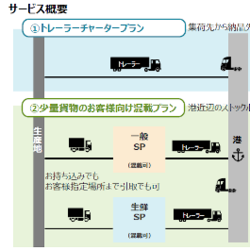















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方