2015/01/20
C+Bousai vol2
環境活動から始まったコミュニティ
真野地区のコミュニティ活動は1965年、公害に対する環境運動から始まった。真野地区には当時、長田区特有のケミカル産業、ゴム産業、メッキ産業などの有害物質を出す工場が集中しており、振動、悪臭、ばい煙とあらゆる公害が発生。環境汚染に起因する体調不良は「苅藻(かるも)ぜんそく」と呼ばれ、四日市ぜんそくの被害者から見ても「うちよりひどい」と言われるほどのものだった。

当時の自治会連合会長だった毛利芳蔵氏を中心に、当初は自分たちで清掃活動や花を植えるなどの環境美化活動を展開していたが、公害はなくならなかった。悲惨な状況を打破するため、報道機関に取材させ、その記事や大学教授の分析記事を神戸市役所から三ノ宮駅に続く地下通路に貼りだすなど、無規則な都市開発への抗議運動を展開。ついには行政・企業と住民による対話集会を開くにいたった。集会は、被害を受けた人なら誰でも参加可能とし、行政・企業と話し合った。集会を重ねるうち、企業も公害防止装置の設置などさまざまな改善を約束するようになった。
真野地区まちづくり推進会の清水光久氏は当時を振り返り「今では訴訟に持ち込むのが一般的だが、毛利氏は企業と不毛な関係を作りたくなかった。公害を出していても地元の人が働く地元の企業。対話で連携と共生を図ろうとした」と話す。
高齢化と見守り活動
1970年代には工業団地が新たにほかの地区で完成したこともあり、企業や工場は真野地区を離れていき、町は活気を失っていった。毛利氏は活気を取り戻すため、街の整備に乗り出す。出て行った工場の跡地を行政に購入してもらい、8つの公園をつくってもらった。この公園は阪神・淡路大震災の時にも住民の避難所として活用されたという。1980年には、通常は行政が行うことが多い街づくりのハード部分のプランを住民主体で作成し「20年後の将来像」として粘り強く神戸市の協力を得て国に働きかけた結果、多額の補助金を国からもらい、注目された。さらに地区を住宅街区と住工協調街区に分け、土地の売買や新規の工場の建設などは行政の建築確認申請を通っても、まちづくり推進会の承認を経ないと着工できない仕組みをつくった。この仕組みは現在でも続いている。
「真野はもともと行政や工場によって環境を破壊された町だが、それだけでは補助金は出なかった。地区にはまちづくり推進会や自治会をはじめ、老人会、婦人会などさまざまな組織があるが、それらが一致団結して住民の総意として(新たな街の整備に)合意したのが強みになっている。ここまで住民一致団結している地域は日本中探しても見当たらない」(清水氏)。
それでも、若者は流出し、全国的に見ても早いペースで高齢化は進んだ。世間では「孤独死」なども取りざたされた時期で、民生委員だけでは全ての対応ができない状況を見た毛利氏は、1980年代に1人暮らし老人の見守りをする「ゆうあい訪問ボランティアグループ」を立ち上げた。各町ごとに高齢者や要介護者の名簿を作り、担当者を決め、民生委員が状況を把握できるシステムを作った。月2回の給食サービスや入浴サービスなども、全国に先駆けてこの時に始まっている。これらのコミュニティ活動がすべて、震災時の人命救助活動や地区の迅速な復興につながっていった。
清水氏は、「それまで30年間続いてきたコミュニティ活動がなければ、阪神・淡路大震災時の迅速な救助活動や復興はありえなかった」と話す。


C+Bousai vol2の他の記事
- 特別対談|意欲的に取り組める防災教育「正解のない」問題を考える 災害経験を風化させないため
- 「60分ルール」で津波から守る 訓練のリアリティを追求する (神戸市長田区真陽地区)
- 若い世代も巻き込んだ防災活動 子どもが喜べば親も来る (神戸市須磨区千歳地区)
- コミュニティが町を救う 震災前に30年間のコミュニティ活動 (神戸市長田区真野地区)
- 毎月定例会毎年訓練と見直し (神戸市中央区旧居留地連絡協議会)
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-










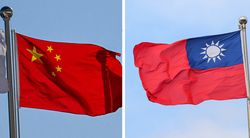















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方