BCP-DX/AIの入り口としての視覚化
第19回:BCPのビジュアライゼーションを考える

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
2022/11/22
企業を変えるBCP

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
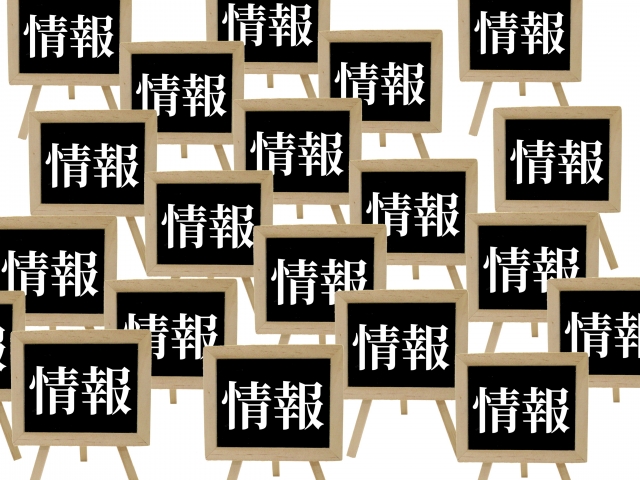
今回はBCP のビジュアライゼーション、すなわち視覚化がテーマです。
ここ数年、BCP訓練をサポートする機会が多くなるなか、訓練で報告される情報の量や質、体裁に目が行くようになりました。その結果、BCPとして目指すべきあるレベルの到達点に向けて「被災状況の視覚化」が重要ではないかと考えるようになりました。このことは、初動フェーズ訓練よりも、BCPフェーズ訓練においてより一層際立ってくるようです。
初動時、つまり発災直後の数時間内に起きた出来事を対策本部や事務局に報告・共有する初動フェーズ訓練では、ポータルサイトに掲出される報告内容の字面と担当者の声を、リモートを通じて見聞きすることになります。実際の報告内容はヒト、モノ、ジョウホウの損傷ですが、初動時のBCP活動は人命優先ですから、報告を受ける側はヒトを中心とした報告がすんなり入り、指示を出しやすいことはいうまでもありません。
一方、BCPフェーズ訓練になると事は複雑です。製造業や流通業など、工場や配送センター、倉庫、支店、営業所が多いと、各拠点からの報告内容は事業(復旧)要素の高い項目が多くなり、聞く側(経営層)は非常に混乱します。

BCPフェーズではヒトの問題がある程度クリアになっているので、モノとジョウホウに関する莫大な報告を受けることになります。経営層は事業継続のために、何が重要で、何をあきらめ、何を優先し、組織やモノをどう動かすか、大量の情報から素早く判断しなければなりません。いわば一国の大統領的思考が求められるわけです。
取締役・役員がBCPフェーズ訓練に参加すると、おそらくこの状況を思い浮かべ、ある種の恐ろしさを感じるのではないでしょうか。自分は経営者として大量の情報に接し、取捨選択しながら会社とステークホルダーにとって最適な判断ができるのだろうか、と。
実際、報告する側は自らの事業所の被災内容をBCP的に分かり易く、ヒト(従業員)、モノ(施設および設備)、ジョウホウ(IT)に細分化して報告します。しかし報告はそれだけでなく、事業(復旧)にからむさまざまな要素が新たに加わります。
取引先からの資材・原材料の供給、営業を通じた顧客からの要望、工場・配送センターにある在庫量と被災による出荷品質のレベル、物流の状況やクレーム対応などがそれ。内外のあらゆる情報が時系列に変化しながら加わり、事業体が多ければ多いほど、情報量として莫大になります。
この点で、大企業はBCP情報の DX化とAIによる対策本部の判断支援が求められます。その取り組みに注力すべきというのが、この連載でも何度か述べている私の主張ですが、一方で取り組みのハードルが余りに高く、着手すらできないというご意見も多くいただきます。
DXやAIで予測モデルをつくるにはある程度の教師データが必要ですが、その教師データがまったくない、つまり過去の災害の経験を自社の被災データとして残せていない状況では、DX/AI化がままならないというわけです。

しかし、BCP-DX/AIに踏み出す一歩として、いったん人の視覚的な把握能力に頼るという方法があります。物事の本質を見極めたい時、マインドマップやホワイトボードに全体像を描いてみることで、整理し易くなり、見えてくるものがあるように、自社の状況を俯瞰するための図が役に立つという考え方です。
DX/AIの機能の一つに、次元減少による簡易化というものがありますが、DX/AIに至らずとも、大量のデータ項目を目的にそって減らし、方向性や特異点にフォーカスすることで見えてくるものがあります。よく「木を見て森を見ず」という言葉がありますが「森を見る」ために、視覚化が役立ちます。
企業を変えるBCPの他の記事
おすすめ記事


今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12


中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方