2024年4月から労働条件明示ルールが改正
就業場所・業務の変更の範囲の明示など

毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2023/07/12
ニューノーマル時代の労務管理のポイント

毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
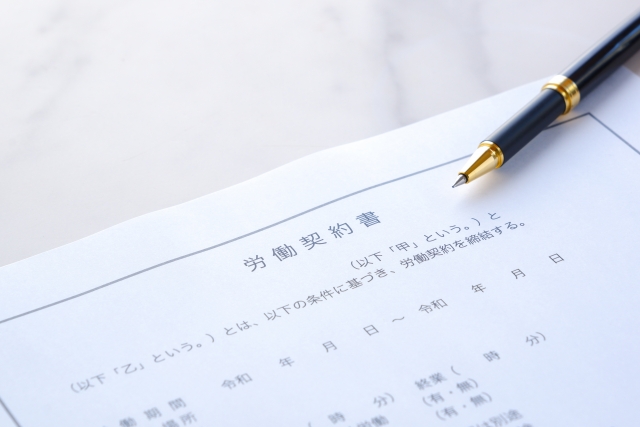
2024年4月から労働契約を締結する際の労働条件の明示ルールが変更されます。
労働契約を締結する際は、労働基準法第15条で定められた労働条件を労働者に明示する必要があります。この労働条件の明示ルールが労働基準法施行規則の改正により変更され、2024年4月からは、明示事項として次の事項が追加されます。
|
明示のタイミング |
新しく追加される明示事項 |
|
全ての労働契約の締結時と |
・就業場所・業務の変更の範囲 |
|
有期労働契約の締結時と |
・更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容 |
|
無期転換ルールに基づく |
・無期転換申込機会 |
出典:厚生労働省リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
現行法においては、全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、雇入れ直後の就業場所と業務の内容を労働契約書や労働条件通知書に記載するなどにより明示することが使用者に義務付けられていますが、2024年4月からは、就業場所と業務内容の「変更の範囲」についても明示することが必要となります。
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わりうる就業場所及び業務の範囲を指します。たとえば、本社で採用した労働者について、本社勤務以外に支店勤務や在宅勤務やサテライトオフィス勤務を行わせる可能性がある場合は、就業場所としてそれらを変更の範囲として明示する必要があります。業務内容については、業務を限定して採用された労働者については、その業務を明示します。業務の内容が限定されていない労働者については、「●●業務、●●業務、その他付帯業務」など、現在及び将来において配属の可能性がある部や課の業務について明示します。
なお、長期雇用を前提とした正社員については、労働契約締結時に変更の範囲が不明確な場合が少なくありません。このような場合は、労働契約書にできるだけ広く業務内容を示したうえで、就業規則に配置転換に関する条文を設けて、業務上の理由から就業場所や従事する業務内容の変更を命じる場合があることを定めておくことが考えられます。
①更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容を明示することが必要になります。
労働契約締結後に更新上限を新たに設けたり、短縮したりする場合は、あらかじめその理由を労働者に説明する必要があります。たとえば、従来は有期労働契約の通算期間の上限を定めていなかったものを新たに5年までと上限を定める場合や、更新回数を4回までとしていたものを3回に短縮する場合が該当します。更新上限は、有期労働契約の無期転換を回避する目的で設けられることが多いですが、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中に解雇することは、労働契約法第18条の趣旨に照らして望ましくないとされています。
ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事
おすすめ記事


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方