2014/02/20
防災・危機管理ニュース
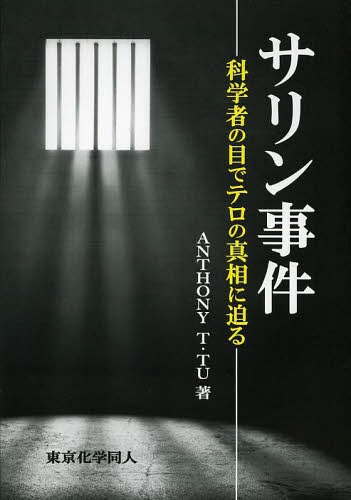
地下鉄サリン事件を例に、化学兵器の脅威や実情を描いた新刊が東京化学同人から出版された。元陸上自衛隊化学学校副校長で株式会社重松製作所主任研究員の濵田昌彦氏に本書の書評をいただいた。
(編集部)
科学者の目でテロの真相に迫る
株式会社重松製作所 主任研究員 濵田昌彦
(元陸上自衛隊化学学校副校長)
実は、この書評を書くに当たり、細心の注意を持って書かなければという思いがある。というのは、この本の中に、オウムのVX合成に関する次のようなエピソードがあるからである。そして、このエピソードは、Tu先生の中川死刑囚に対する面会で明らかになったことである。中川は語る。
「VXは「現代化学」1994年9月号の先生の論文を見て、土屋君がVXを造れると言って造ったのです。雑誌は8月15日に出たので、オウムは9月からVXを造り始めました」。
これを聞いて、Tu先生は仰天したという。地下鉄サリン事件が、1995年3月20日、その一年前の1994年6月27日に松本サリン事件が起こっている。オウムは、この二つの事件の間に、このVXを使って3件の殺人(あるいは殺人未遂)事件を起こしている。ちなみに、この論文は警察の捜査にも大いに役に立った。そういう訳で、情報は常に二面性を持っており、テロ組織を利するようなことがあってはならない。
しかし、化学に関する記述が、あるときには有用となり、あるときには悪用の危険をもつことは、ある意味で仕方のないことかもしれない。Tu先生も、本文中でそのように書いておられる。それにしても、悪用されないよう(意図的に)簡略化された合成経路を一目見た瞬間、これならできると直感した土屋の能力というのは感嘆すべきものである。惜しむらくは、その能力をテロではなく創造に使って欲しかったと思う。
本書の中で注目すべきは、これまで知られていなかったオウムの生物化学兵器に関する新事実が、次々と明らかになることである。例えば、シクロサリン合成である。サリンは、化学兵器としては理想的なものであるが、揮発度が高い。水と同様の速度で蒸発するため、ある地域を使えないようにする、あるいは効果を長く持続させたい時には、やや物足りない感がある。
これを補うのがシクロサリンであり、毒性もサリンより高い。かつてのイラクも、これを保有していたことが知られている。オウムはその他にも、タブンやソマンまで合成していたことが明らかにされている。もし、これらの神経剤が、あの日、東京の地下鉄で使われていれば、様相はもっと悲惨なものになったかもしれない。
実は、サリンもソマンもそしてシクロサリンも、兄弟のようなものである。通称ジフロライドと呼ばれる中間体に、どんな種類のアルコールを反応させるかで生成物も変わってくる。サリンの場合には、イソプロピルアルコールというかなり一般的な薬品であるが、ソマンやシクロサリンではそうはいかない。
現在では、これらの薬品へのアクセスには厳重なチェックがなされているが、当時は国内法も未整備であった。それにしても、これらの原材料を入手できたとしても、オウムはサリン等の合成ノウハウをどこから得ていたのか。この点はこれまで不明な部分が多く、ロシアとの関係が以前から噂されていた。ジエチルアニリンという耳慣れない溶媒を使っていたことも、ロシアとの関係を疑わせる要因となった。
しかし、本書ではこれが明確に否定されている。中川死刑囚がTu先生に語ったところによれば、国会図書館や大学の資料だけで、十分にやれたというのである。当時のオウムの力量がよくわかる。
もう一つ、明らかになった事実がある。生物兵器である炭疽菌の開発失敗の理由である。オウムの炭疽菌は、まったく効果がなく悪臭がしただけであった。それは、間違えてワクチン用の無毒株であるスターン株を使ったためと理解していた。しかし、オウムの生物兵器開発の責任者であった遠藤は、敢えてスターン株を選び、それを遺伝子工学的に改変し、強毒性にできる自信があったというのである。だとすれば、時間と資源があれば、オウムによる炭疽菌事件が、2001年の米国炭疽菌事件のはるか前に、世界を震撼させていたかもしれない。
最後に、中川死刑囚が東京拘置所でTu先生に語った印象的な言葉をここに記す。「先生、サリンをつくるのはそんなに難しいことではありませんよ。大学の化学の知識のある人ならすぐにつくれるものですよ」。
確かに、自分の経験からしてもその通りだと思う。だからこそ、本書にある教訓と事実をかみしめて、二度とこのようなテロ事件を起こさないよう努力と精進を重ねていこうと思う。
(了)
- keyword
- テロ・大規模事故
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方