連載
-

【第5章】 災害救護 1(後編)
ショックとは血液の循環が悪く、体中の細胞へ十分な酸素と栄養が行き渡らない状態を指し、この状態が長引くと死に至ることがある。しかし、このショック症状は見逃しやすいので注意深く要救助者を観察する必要がある。
2017/04/25
-

自然災害によるPTSD~救援者側が抱える心の傷
東日本大震災、鬼怒川決壊、岩手県岩泉町の大水害などの自然災害の現場を歩き、地元自治体や被災者を訪ねて被災体験や生活再建に耳を傾ける時、被災者が時間の経過にかかわらず心的外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Disorder、PTSD)で苦悩されている事実を知った。PTSDを発症した人がうつ病、不安障害などを合併させるケースも多いという。人生はやり直しがきかない。それだけに心からぬぐえないトラウマは深刻である。
2017/04/24
-

杉戸町の人々の第二の故郷だった富岡町
こうして2013年度の国土交通省補助事業「広域的地域間共助推進事業」がスタートしました。そして同事業の中では、あの日から現在まで何が起こっていたか整理する作業も行われました。普段のプレゼンテーション中では時間が無く、説明できなかったものなので、今回は背景からその後までじっくりと説明させて頂きます。
2017/04/20
-

【第5章】 災害救護 1(前編)
読者の方もご存知だと思うが、あの震災では自助・共助により命が助かった割合はなんと95%にも上る。(下グラフ参照) 一体この数字から何が読み取れるのだろうか? 筆者はこの数字を“人間が本能的に持つ善の心がもたらした勇気ある行動の結果”だと思っている。つまり、一旦災害が発生し自分の命が助かった者は、好む・好まざるに関わらず、自発的に救助活動を始めるということである。しかしその側面では大変な悲劇を招きかねない危険が潜んでいる。
2017/04/18
-

幕末・土壇場の危機回避~江戸無血開城と勝海舟~
幕末・危機一髪のクライマックス、江戸無血開城と幕臣・勝海舟の危機回避への深謀遠慮を考える。「海舟は幕府体制の中にいながら、体制をぶち壊し体制の枠を超えてずっと先を見通している」(「それからの海舟」半藤一利)。最後の将軍徳川慶喜から危険視されていた勝海舟が陸軍総裁に任命されるのが慶応4年(1868年)1月23日(旧暦)である。
2017/04/17
-

【第4章】 火災防護 (後編)
読者の皆様にも「サイズアップ」という言葉を聞いたことがある方は多いと思うが、今一度説明しよう。サイズアップとは現場の状況を評価し判断することである。プロのレスポンダー(災害対応にあたる人)が現場で行っているこのサイズアップのプロセスは当然一般市民レベルでも活用すべきもので、火災現場におけるサイズアップの9つのステップを紹介する。
2017/04/11
-

「減災への取り組み~荒川下流域のタイムライン~」
タイムラインは自然災害に対処する「人類の知恵」である。災害が想定される数日前から、発生やその後の対応まで、関係機関が災害時に何を優先して取り組むかを時系列的に定めた行動計画表のことである。被災住民、自治体、国、自治会、消防団、鉄道会社、電力会社、教育機関などのとるべき行動が一覧票にまとめてあり、各組織の動きや連携関係が一覧できる。
2017/04/10
-

「誰にとっても心地よい社会」を目指して
「こんな町で、大規模な訓練が行われているとは思わなかったですよ」私たちの活動を取材してくれた直木賞作家の天童荒太さんから出た素直な感想でした。SANKEI EXPRESSに連載されていた天童荒太さんの「だから人間は滅びない」その最終回(2014.11.29号)で、私たちの杉戸式協働型災害訓練を取り上げてくださいました。その取材の中で天童さんが発した言葉でした。まあ、確かに言われてみれば…です。
2017/04/06
-

【第4章】 火災防護 (前編)
米国ではCDC(米国疾病予防管理センター)の下部組織でNIOSH(通称ナイオッシュ/National Institute for Occupational Safety and Health:米国立労働安全衛生研究所)という労働災害の予防を目的とした研究・勧告を行う政府機関があり、そこでは火災現場で殉職した消防士の事故調査を教訓に「火の動態と特性」を理解することがいかに重要であるかを力説している。これは常備消防だけに限らず、消防団をはじめ、市民レベルでの消火隊にも広く教育・啓蒙されなければならない。
2017/04/05
-

第12回(最終回):手のかからない維持管理
いざという時に備えてERPを日ごろから見直そう。写真は昨年の糸魚川大火で焼け残った建物。■緊急対応プランを日頃から生かすための3つの工夫日々の会社の業務は、右から左への流れ作業そのものです。ERP(緊急対応プラン)の策定のようなイレギュラーな活動の場合はなおさらのこと。
2017/03/30
-

【第3章】 チームの安全を守るICS (後編)
CFRまたはCERTメンバーとして災害が発生した場合、どのようにその機動力を発揮するかが重要だ。事前計画が文書上で決められているだけで形骸化していては何もならない。第1章の災害準備編でも述べたように、まず自分自身の身を守り、家族を守り、家を守り、近隣住民を守ることを省略することはできない。
2017/03/27
-

アナフィラキシーは死ぬかもしれない病気です
ある日のランチタイム、賑わう社員食堂で男性が卒倒した。「どうしたんだ?!」そこに午前の会議を終えた中澤(仮名46才男性管理職)がやってきた。同僚の話によると、さっきまで普通に談笑しながら食事をとっていたのだが、急に「息が苦しい、気分が悪い…」と言い出して倒れてしまったとのことだ。
2017/03/23
-

カスリーン台風から70年、大惨事を検証する
今から70年前の1947年。南太平洋に発生し弧を描いて北上して日本列島を襲う台風は、英語圏の女性名がアルファベット順に冠せられていた。猛威を振るう台風が英語圏の女性名。打ちひしがれた敗戦国の国民に、この厳粛な事実を知らしめたのがカスリーン(Kathleen)台風であった。
2017/03/23
-

【第3章】 チームの安全を守るICS (前編)
さて、いよいよこの章から最終章まで、一気に一般市民または組織の従業員がファーストレスポンダー※1として公設のプロのレスポンダーが現場へ到着するまでの数時間から数日間を繋ぎ、災害現場において真の自助・共助を実践するための具体的なノウハウの部分に入っていく。
2017/03/21
-

<大事件の前に必ず小事件あり>~技師青山士の名言
「大事件の前には必ず小事件がある。小事件をいち早くキャッチすることが技術者の最大の任務である」「技術は人なり」「手抜き工事は国民への背信行為である」。
2017/03/16
-

第11回:右も左も熱い人でいっぱいじゃござんせんか!
2009 年に世界各地で発生した新型インフルエンザ(H1N1型)は、毒性はさほど強くなく、生活やビジネスへの影響も比較的限定的なものにとどまりました。今や新型インフルエンザと聞いても、不安を抱く人はほとんどいないのではないでしょうか。しかし今後、より感染力や毒性の強いウイルスが突然現れて、あちこち拡散しないとも限りません。
2017/03/16
-

【第2章】 「災害心理学」について
一昨日は、あの忌まわしい東日本大震災から6年の歳月を迎えた日だった。この場をお借りして最愛のご家族やご友人を亡くされた方々に心より哀悼の意を捧げます。 筆者が長年任務に就いていた米軍を辞めるきっかけとなったのが、この大震災であると言っても決して過言ではない。ふと30数年に渡り米軍で受けてきた教育や訓練を、一人の日本人として日本へフィードバックすることによって何か貢献出来ることがあるのではないかという思いが芽生えた日でもあった。あの時に思った感覚は今でも鮮明に思い出すことが出来る。
2017/03/13
-

外傷による出血に対してできること
バングラデシュ・ダッカで日本人がテロの犠牲になってしまいました。JICA(国際協力機構)のコンサルタントとして現地の発展のために尽力されていた方々とのことです。同じく同機構の医療チームの末席に身を置く者として、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表します。
2017/03/08
-

画期的!<マイ・タイムライン>ができた
2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川が決壊し、茨城県常総市は市域の3分の1が濁流に没した。その間、被災者から必死の救助要請が殺到した。常総広域消防本部(常総市水海道山田町)と茨城西南広域消防本部(古河市中田)にかかった119番は決壊から3日間で2500件以上に達した。かつてない数字である。市民の逃げ遅れが続出し、ヘリやボートなどで計4258人が救出される異常事態となった。茨城県防災ヘリだけでも、3日間で出動は延べ128機、計1339人が救助された。この数字をどう読むか。
2017/03/07
-

【第1章】災害準備編~本当に準備するべきことは?!(後編)
そして、生き残った後に考えなければならない次のステップが避難生活である。今回の災害対策基本法等の一部を改正する法律案の中でも、このことは新たな項目として追記されている。
2017/03/06
-
世界最大級の治水<地下神殿>~首都圏外郭放水路
2015年9月9日、積乱雲が帯状に連なる線状降水帯が栃木県と茨城県の上空に停滞し、長い間集中豪雨をもたらした。気象庁は「特別警報」を発し最大限の警戒を呼びかけた。記録的豪雨が大地を叩き続け河川の氾濫が相次いだ。大洪水は関東・東北の両地方に集中した。翌10日、常総市三坂町の鬼怒川左岸(東側)堤防が決壊した。堤防を切った濁流は東に流れ下って、常総市の3分の1にあたる40㎢(東京・江東区と同等の広さ)が浸水し、宅地や田畑は泥の海に没した。埼玉県東部でも豪雨が続き、惨事は避けられないとみられていた。ところが、春日部市などの一部地域が浸水した以外は大事には至らなかった。なぜか?春日部市の石川良三市長は追想する。
2017/03/06
-

第10回:SNSのえじきになったらたまらん!
■たいへんです、社長! ある食品会社の営業業務課のパソコンに1通のメールが届いた。消費者からの問い合わせメールだった。次のようなことが書いてあった。 スナック食品Xは今後どうなるのでしょうか。私はXが大好きで、週に2、3回はコンビニで買って食べています。もし販売中止になったらとてもがっかりです。1日も早い解決を希望します。
2017/02/27
-

【第1章】 災害準備編~本当に準備するべきことは?!(前編)
2013年4月12日に災害対策基本法等の一部を改正する法律案が閣議決定された。改正法では多くの改善点が発見できるが、その中で特に注目したいのが、第1章総則の第2条の二にて、「国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること」と書き加えられた点である。
2017/02/27
-

おさらいしようエコノミークラス症候群
熊本県によりますと、一連の地震で避難生活が長引くなか、県内でエコノミークラス症候群で入院が必要とされた患者は、5月1日午後4時現在、46人となり、このうち1人が死亡しています。内訳は、男性が10人、女性が36人で、年齢別では65歳以上が30人、65歳未満が16人となっています。
2017/02/23
-

生死を分けた避難誘導アナウンス
東日本大震災から6年。私は発災直後から3年間ほど毎年2~3回、岩手・宮城・福島3県の被災地を訪ねた。雨滴や泥が染みついたノートや資料類をもとに2万人近い犠牲者を出した未曽有の大惨事での被災地や犠牲者の姿を考えたい。
2017/02/22





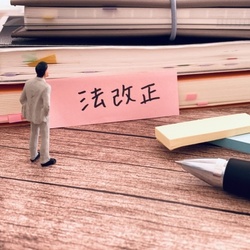







![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





