2011/11/25
事例から学ぶ
富山県黒部市に本社を持つホースメーカーの株式会社トヨックスは、原材料の最大の仕入先が被災する中、新型インフルエンザを機に拡充してきた在庫対応と、万が一の被災時に備え代替生産の依頼をしていた海外メーカーの協力を得ることで、顧客への影響を回避した。
■最大の仕入れ先が被災
トヨックスは、工場機器や家庭の台所、浴室の水回りなど幅広い分野で使われているホースやその継手、ホース加工のコア技術を応用した輻射空調システムなどの製造を手がける。吸引圧力がかかってもつぶれにくいホースや、耐熱性に優れたもの、液体や匂いが付着しにくいものなど、製品によっては市場の7割、8割のシェアを占める特殊製品もある。
東日本大震災では、富山県黒部市は震度1を記録しただけで、同社に地震による直接的な被害はなかったが、茨城県にある原材料の最大の仕入れ先企業の工場が被災し、調達が4カ月にわたり見込めない状態になった。
トヨックスの顧客の中には、同社製品への依存度が100%という企業もある。こうした企業への影響を出さないためには迅速な対応が求められた。幸い、同社では、2009年の新型インフルエンザの流行を機に、国内倉庫で製品の在庫を多めに確保するなどの対策を行っていたため、供給体制に即座に影響が出ることは避けられたが、同社ISO事務局管理責任者の出嶋光之氏は、「お客様への説明責任として、在庫でいつまで耐えられるのか、いま、どのような対策を講じているのか、いつから安定供給ができる体制に戻るのかなどを説明する必要がありました」と語る。
国内の代替となり得る調達先は、それぞれが抱えるメインの顧客への対応に追われていたため、同社が新たに購入を申し出ても、十分な量を仕入れることは困難な状況だったという。原材料を1社から集中的に購買していたことが裏目に出た。
それでもトヨックスでは、イタリアの大手ホースメーカーであるフィット社と技術提携をしていたため、同社に依頼し主力製品の原材料、計500トンを現地で調合してもらい、それをペレット状にして日本に送り届けてもらうことで自社工場での安定生産が継続できる体制を整えた。偶然にも、数年前にトヨックスの宮村正司社長がフィット社を視察に訪問した際、万が一の被災時における応援を要望していたのだ。ホースは、製品ごとに主原料、副原料、配合材、顔料など何十種類もの素材を微妙な割合でブレンドしなくてはならないが、フィット社からは日頃からトヨックスの製品についてよく理解が得られていたことから、スムーズな対応がしてもらえたという。宮村社長は「たまたま食事をしながらお願いしたことが、まさか現実になるとは思いませんでした」と振り返る。
事例から学ぶの他の記事
おすすめ記事
























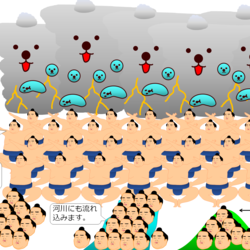














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方