2019/08/01
昆正和のBCP研究室
■行動ステップの構成
3つ目、「BCPでは発災~終息に至るまでの危機対応のフローはどうなっているのか?」について。なぜこのような疑問を持つ人がいるのかというと、ガイドラインなどは要件を羅列しただけなので災害対応の「流れ」が見えにくいからである。そこでBCPを文書化する場合、緊急時の対応からはじまり、BCPの発動そして重要業務の継続から復旧へと続き、終息させるまでの一連の流れがわかるような構成で記述することが大切である。それぞれのポイントは以下の通り。
(1) 初動対応の行動手順
初動対応には、最も初期の行動として、発災の確認、身の安全確保、初期消火、負傷者の救助、最寄りの安全な場所への避難などがある。次に全員の安全が確保された時点で安否確認を行なう。安否確認はあらかじめ伝達ルール(だれが、どこへ、どんな手段で安否情報を伝えるか)を決め、それを記録用紙(安否確認シート)に集約できるようにしておく。
(2) 対策本部の招集と設置
初動対応を終えた後、社内が被災して多くの業務が停止し、混乱した状態にあることが分かったならば、直ちに緊急対策本部を立ち上げる。この際対策本部メンバー全員がBCPを手に、所定の場所(会議室など)に集合することになる。
(3) 被害状況の確認
従業員の安全と自宅の被災の有無、出社状況、ライフライン、道路や交通機関の運行状況、顧客や取引先への影響、IT機器や生産設備の破損、製品の損傷の程度、機械・装置の位置ずれ、倉庫の荷崩れなどの被害状況をチェックする。
(4) BCPの発動
被害状況を確認したところ、多くの業務活動が阻害され、早期復旧の目処がつかめず修理・修復にかなり時間がかかるならば、直ちに対策本部長はBCPの発動を宣言する。よく「BCP発動の是非を客観的に判断できる基準は何か?」が問題になるが、これはむしろ対策本部長による状況判断および意思決定のプロセスと見たほうが自然である(数字だけにとらわれると判断を誤ることがある)。
(5) 重要業務の継続と災害復旧活動
「重要業務の継続」は、中核事業を構成する一連の業務を維持・継続することを指す言葉だが、ここには「いつも通りのやり方で業務が行えないときは代替手段(仮復旧手段)を駆使する」というオプションも含まれている。したがって重要業務の継続方法(代替手段による仮復旧方法)がBCPに明確に規定されていなければならない。対して「災害復旧活動」は、仮復旧で急場をしのいでいる間に、被災現場を通常業務ができる正常な環境に戻すための活動である。
(了)
- keyword
- BCP
昆正和のBCP研究室の他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

-









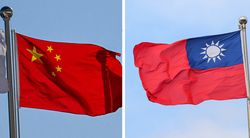















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方