2013/09/25
誌面情報 vol39
東京都 帰宅困難者対策へさらなる理解求め
東京都の帰宅困難者対策への協力が思うように進んでいないようだ。今年4月1日に施行された「東京都帰宅困難者対策条例」では、すべての事業者に従業員3日分の備蓄品を備えるよう義務づけた。また2016年までに、会社や学校などに所属しない、行き場のない帰宅困難者92万人を一時的に受け入れる一時滞在施設を確保することを目指しているが、現状では事業所の備蓄に関しては一定の効果が出ていると見るものの、一時滞在施設については都立施設と民間施設を合わせて11万人にとどまる。都では、民間企業に自助の重要性をさらに呼びかけるほか、駅周辺の駅前滞留者対策協議会などに働きかけ、帰宅困難者対策への理解を得ていきたいとしている。
81万人の居場所がない
首都直下地震においては517万人の帰宅困難者が想定されている。東京都では今年4月1日に都立の200施設を一時滞在施設に指定し、7万人を受け入れることを発表しているが、残りの85万人については民間企業の協力を求めている。一方、民間施設については、施設数は明らかにしていないが、現状で4万人分を受け入れる一時滞在施設が確保できているとする。単純に計算すれば81万人分の協力が必要な計算になる。都では今後も都立施設について受け入れ態勢を整えていくほか、民間事業者に対しても100人以上の受け入れが可能である企業を中心に協力を呼びかけていきたいとしているが、目標の達成には、これまで以上に帰宅困難者対策への理解と、民間事業者の協力が不可欠だ。
帰宅困難者対策の大きな課題となっているのがターミナル駅周辺の問題だ。
新宿駅で約5万人、東京駅で約3万人といった人数が首都直下地震の際には溢れると想定されている。仮に新宿駅周辺で5万人を受け入れるには、100人を受け入れる施設が500カ所必要になるということだ。
そのため東京都は8月に「新宿駅周辺における一時滞在施設の確保等に向けた連携に関する協定」を新宿区と新宿駅周辺防災対策協議会と結んだ。都内には現在約30の同様の協議会があり、災害時駅周辺で溢れる帰宅困難者を受け入れられる体制を整えられるよう進めている。都の総合防災部萩原功夫氏は、「協議会には多くの事業者が参加しています。新宿駅周辺の企業へ一時滞在施設のお願いがしやすくなる」と話す。 ちなみに、横浜市では一時滞在施設への協力を要請する際に、まずは1日で構わないという形で協定を結んでいる。その際には備蓄品はすべて市から提供するという。
法整備など課題も
一時滞在施設には別の課題もある。一時滞在施設に受け入れた帰宅困難者との間の管理責任における法的な問題だ。
帰宅困難者を受け入れた一時滞在施設で、余震で天井が崩壊するなどの事故が起きて帰宅困難者が怪我をした場合、法的には管理責任が施設所有者に及ぶリスクがある。
こうした問題を明らかにして情報共有し、一時滞在施設の確保の促進を図るため、今年6月に設置された「一時滞在施設の確保に関するワーキンググループ」に有識者として参加している丸の内総合法律事務所の中野明安弁護士は、「真面目にやろうとしてくださっている企業や従業員の方が2次被害の責任問題・賠償問題で対応に苦慮されることや、責任問題等を心配して民間企業の協力が得られないことを憂慮している」と話す。
課題を解決するためにある自治体では「一時滞在者の受け入れに協力する企業との間で締結する協定書の中で、“通常の善良な管理者として注意義務を果たして運営している場合は、事業者には責任は及ばない”と合意する例がある」と言う。しかし、こうした協定が万が一裁判になった際に効力が認められるかは未知数。中野氏は、「帰宅困難者対策に会社が安心して取り組めるよう、法的責任論のさらなる検討や、協定書、合意書の効果的な規定内容を考えている状況」と説明する。
確実な結論を得るにはまだ時間がかかりそうだが、中野氏は「私としては、ぜひ自治体が一時滞在施設の運営主体になり、民間企業が施設提供や人的支援という側面で協力するという図式を実現してもらいたい」と国や自治体の理解に期待を込める。帰宅困難者対策の趣旨に鑑みて、リスクや負担は住民全体、ひいては国民全体で分かち合うことが望ましいからだ。
意識改革からの取り組み
一方、民間の備蓄などについても一定の効果は見受けられるが、まだ取り組みが充分とは言い難いようだ。
萩原氏は、「一時滞在施設への協力をお願いする以前に、まだ“自助”が満足に足りていない企業が多い」と指摘する。「自助、共助、公助といっても、自助ができていなければ他人を助けることなんてできない。さらに言えば、そうした方は他人の共助に頼らざるを得ない。どこかの施設に逃げ込めば助けてもらえると思っているとすれば、それはあまりに想像力に欠けている」と危機感を募らせる。
首都直下地震では環状7号線沿線に多い木造の建物が炎上し、東京都を囲むように火の海になることが想定されている。そこを通って、埼玉、千葉、神奈川といった近隣県の自宅へ帰宅することはあまりに危険なことだ。
平日であれば、およそ300万人が近隣県からやってきて日中の都内で活動している。もし家族の安否を確認する手段を決めていなかったり、自宅の家具転倒防止措置をしっかり施していなかったりすれば、なんとか歩いてでも帰りたいという人が出てくることも考えられる。強引に歩いて帰れば緊急車両の通行を妨げることにもなりかねない。「ある大学の先生は、この時無理に帰ろうとする帰宅困難者は“加害者”であるとまで言っている。それくらいの思いで、会社に留まることを決断してほしい」と萩原氏は話す。
オリンピックに向けて
東京都は帰宅困難者を受け入れる企業に対し、備蓄品購入費用への補助金を出している。企業がBCPを策定していることが条件の1つだが、これは「まず自分の会社と従業員の安全を保障して頂かなければ、帰宅困難者を受け入れてもらうのは難しい」との目的からだ。
2020年に東京でのオリンピック開催が決まった。オリンピック期間中は海外から数十万人、国内からは数百万人が訪れることが予想される。オリンピックを成功させるためにも、最低限、現状の帰宅困難者対策は早急に解決すべき問題だろう。
そのためには都と民間企業が一丸となることはもちろんだが、一人ひとりが当事者意識を持ち、自分や家族、自分の会社から対策することがなにより求められている。
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

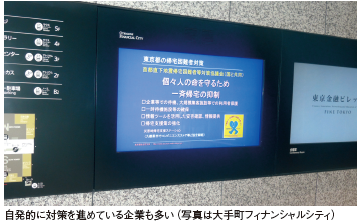



























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方