第124回:企業のレジリエンスを評価するための枠組みの一例
Sanchis他 / Definition of a framework to support strategic decisions to improve Enterprise Resilience

田代 邦幸
自動車メーカー、半導体製造装置メーカー勤務を経て、2005年より複数のコンサルティングファームにて、事業継続マネジメント(BCM)や災害対策などに関するコンサルティングに従事した後、独立して2020年に合同会社Office SRCを設立。引き続き同分野のコンサルティングに従事する傍ら、The Business Continuity Institute(BCI)日本支部事務局としての活動などを通して、BCMの普及啓発にも積極的に取り組んでいる。一般社団法人レジリエンス協会 組織レジリエンス研究会座長。BCI Approved Instructor。JQA 認定 ISO/IEC27001 審査員。著書『困難な時代でも企業を存続させる!! 「事業継続マネジメント」実践ガイド』(セルバ出版)

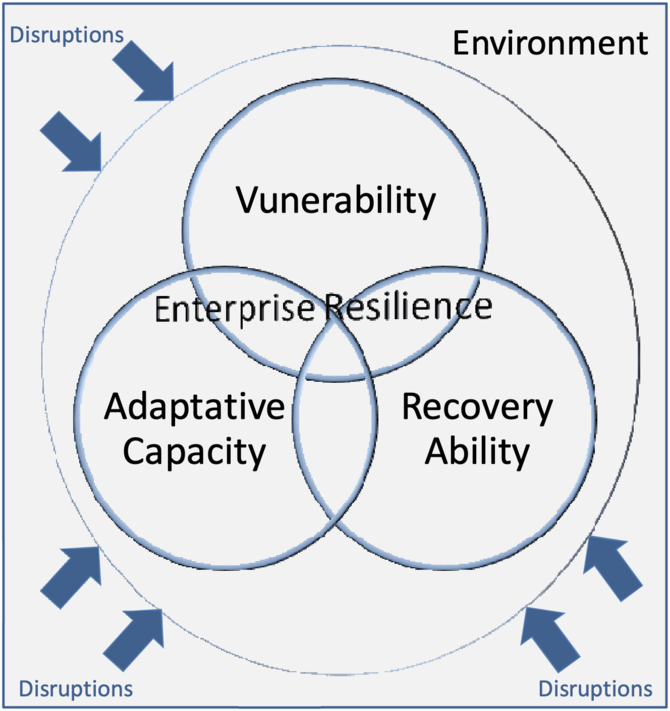
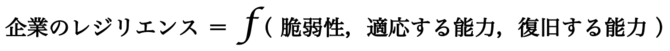



































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方