2021/01/03
2021年1月号 東日本大震災から10年

東日本大震災から今年で10年目を迎える。5年目に当たる2016年には熊本地震が起き、10 年目を迎える今年は新型コロナウイルスにより世界中が混乱に陥っている。その間にも台風や梅雨前線に伴う記録的な豪雨により甚大な被害が度々発生していることを考えると、少なくてもわが国においては、危機のテンポが着実に早まっているかのようにも感じる。
この10 年、政府は企業や自治体にBCPの策定を呼び掛け、その結果、内閣府調査
によれば、令和元年時点で大企業に限っていえば、実に68.4%もの企業がBCPを策定した(策定中を加えれば、80%を超える)。自治体では令和元年6月現在、都道府県の100%、市町村の89.7%(令和元年度内の策定予定を含めると94.4%)がBCPを策定しているという(総務省消防庁調べ)。
さらに莫大(ばくだい)な投資により社会インフラは年々強化され、情報ネットワークの整備や人工知能(AI)の登場により都市機能は飛躍的に高度化し、政府が目指す国土強靭(きょうじん)化は大きく進展しているようである。ところが、災害による犠牲者は一向に減らない、むしろ増えているといってもいい。なぜか。
防災白書をもとに、2011年以降に発生した主な災害を挙げてみた。
2011~13年は毎年のように大雪が降り、多くの人が命を落とした。2016年の熊本地震では、支援物資が被災地に届かないラストワンマイル問題が発生。小規模自治体への支援はまたも大きな課題となり、避難所運営も困難を極めた。民間企業でいえば、多発する余震で被災地の被害状況の確認が手間取ったり、首都圏などにある本社からの支援についても交通手段や宿の確保が障壁となった。
2021年1月号 東日本大震災から10年の他の記事
- これからの国土づくり 「構想力」と「創意工夫」で
- 12月の危機管理・防災ニューストピック【自然災害・国土強靭化】気候変動に危機感増す
- 日本社会は危機に強くなったか
- 東日本大震災から10年 問われるBCPの実効性
おすすめ記事
-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

-









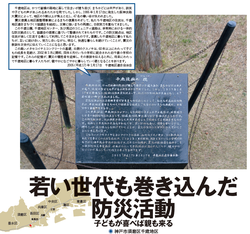

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方