2022/12/04
再考・帰宅困難者対策
「全員抑制」から「きめ細かな指示と判断」の時代に
東京大学大学院教授 廣井悠氏に聞く


工学系研究科都市工学専攻・教授
廣井悠氏
ひろい・ゆう
1978年東京都生まれ。慶應義塾大学理工学部卒業、同大学大学院理工学研究科修士課程修了を経て、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻・博士課程を2年次に中退し、同・特任助教に着任。2012年4月名古屋大学減災連携研究センター准教授、16年4月東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授、2021年8月から現職。博士(工学)、専門社会調査士。専門は都市防災、都市計画。内閣府首都直下地震帰宅困難者等対策検討委員会座長、東京都今後の帰宅困難者対策に関する検討会議委員座長、東京都帰宅困難者対策に関する検討会議座長などを歴任。
帰宅困難者対策が変わろうとしている。内閣府の首都直下地震帰宅困難者等対策検討委員会が発表した新たな方針を受け、国は1年以内をめどにガイドラインを改定する予定。大規模地震後の「3日間一斉帰宅抑制」の原則は維持しつつ、多様な被災状況に応じたきめ細かな情報提供と移動制御を求める方向だ。帰宅困難者対策の現状と課題、今後の取り組みのポイントについて、東京大学大学院教授で検討委員会の座長を務める廣井悠氏に解説いただいた。
(本文の内容は11月15日開催の危機管理塾の内容をQ&A形式にまとめ直したものです)
人の移動が被害を拡大させるおそれ
Q. なぜ帰宅困難者対策が必要なのですか?
先日、韓国ソウルの梨泰院で発生した群集事故で150人以上が亡くなりました。こうした事故は、国内外でひんぱんに起きています。2001年に明石歩道橋で花火大会の見物客ら247人が死傷した事故を記憶している人も多いでしょう。
群集事故は、ハードとソフトと心理のいずれかが機能不全に陥ると起こりやすいといわれます。大規模地震の後はハードが壊れているうえ、交通整理などソフトの誘導も思うようにできず、心理状態も普通ではありません。そこに密集空間が生じれば、群集事故が起きる可能性は平常時よりも高くなります。なので、地震時だからこそ密集をつくり出さないことが重要です。
帰宅困難者対策というと、帰れなくなった人をどう帰すかという発想になりがちですが、そうではありません。帰れなくなった人が一斉に、無理に帰ろうとすると大混雑が起き、結果として人が亡くなる可能性が高まる。これをいかに防ぐかが帰宅困難者対策の第一の意義です。
そして第二の意義は、車道の渋滞防止です。地震後は歩道の混雑とともに、ヘビーな交通渋滞が発生する。このような激しい交通渋滞は、歩道における過密空間の発生以上に長く続くことが知られています。
そうなると、困るのは消防車、救急車、災害対応車両です。帰宅を急ぐ車や家族を迎えに行く車で幹線道路が渋滞すると、緊急車両が動けない。ということは、助けられる命を助けられない、消せるはずの火を消せないことになってしまいます。
このように、人の移動が間接的に被害を増大させる原因となってしまう可能性がある。それが、帰宅困難者対策をしなければならない最大の理由なのです。
Q. みなが一斉に帰宅すると、東京都内の歩道はどのような状態になるのでしょうか?
私は、スマートフォンの位置データなどを用いて、首都圏で一斉帰宅時の人の動きをシミュレーションする研究を行っています。これは都内各所からみなが一斉に帰ったらどれだけ道が混雑するかを可視化したもので、やや強い仮定を置いて計算しているものですが、600万人シミュレーションと呼んでいます。
これによって東日本大震災後の帰宅状況を再現したところ、実は、歩道ではそれほどひどい混雑は起きていません。1平米あたりの人数、すなわち歩行者密度は0.2~0.5人。電話ボックスがちょうど1平米ですから、2個から5個の電話ボックスに1人という割と余裕のある密度です。
東京都内は震度5強でしたから、会社が被災せずに留まれたうえ、一刻も早く家族に会いたいと考える人がそれほど多くなかったからだと思われます。当時の社会調査では、半分ほどの人が比較的ゆっくり帰るような帰宅状況であったことが分かっています。
これが、震度6強以上だったらどうか。会社の建物は壊れ、家族の安否も心配になり、一刻も早く帰りたいと考える人が圧倒的に増えるでしょう。もしそうなったら、つまり600万人が一斉に帰宅したらどれだけ混雑するか、発災から1時間後の歩道の状況をシミュレーションした結果が[画像1]です。多くの歩道がオレンジ、赤、赤紫に塗られていることが分かります。
●600 万人シミュレーションによる歩道の混雑予測 写真はGoogle Earth

赤紫色の部分は、歩行者密度1平米6人です。電話ボックスに6人が詰め込まれた大密集状態。群集事故のリスクが明らかに増大しています。
これに対し、600 万人の半分が会社や一時施設に留まった場合を示したのが[画像2]です。群集事故が起こり得る空間がかなり少なくなることが分かるでしょう。一斉に帰らないこと、それが帰宅困難者対策の第一のポイントです。
●600 万人シミュレーションによる歩道の混雑予測 写真はGoogle Earth

- keyword
- 帰宅困難者対策
- 一斉帰宅抑制
- 600万人シミュレーション
- 廣井悠
再考・帰宅困難者対策の他の記事
- 柔軟な帰宅に向けて判断基準やルールが必須
- 社会損失の最小化には「移動のトリアージ」が不可欠
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-












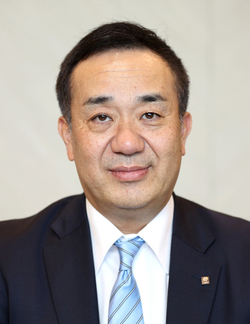















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方