レジリエンス
-

SNSのリアルタイム防災・危機管理情報を地図上で可視化するGISサービス
Specteeと ESRIジャパンは、マップを作成・利用・管理するポータル環境を提供するESRIジャパンのクラウドGIS『ArcGIS Online』上に、スペクティのクラウドSaaS型防災・危機管理ソリューション『Spectee Pro』で取り扱う防災・危機管理情報を配信するサービス『Spectee on GIS』を提供する。
2021/03/22
-

「防災(BOUSAI)」は家族から始まり世界につながる
今回会いに行った防災士さんは、なんとタレントの時東ぁみさんです! 嬉しい! 以前から仲良くさせてもらっていましたが、時東さんが「さくマガ」というサイトで書いている連載のインタビューに呼んでいただいた時、逆に私からもお願いすると、間髪いれずに「OK!」をいただきました。防災士になったきっかけから今後の目標まで、余さずお伝えします。
2021/03/19
-

スポーツ施設で日常使いもできる防災用パネル
総合スポーツ器具メーカーのセノーは、岐阜プラスチック工業と共同開発したスポーツ施設向け器具備品・防災器具のコンセプトモデル『QUADBOARD(クワッドボード)』を展開する。
2021/03/18
-

モバイルバッテリーの発火対策 災害時はどうなるの?
防災に関する商品開発も進んでいます。今回は、近年、火災事故が増えているリチウムイオン電池用の消火フィルムを紹介します。
2021/03/18
-

危機の「察知」「伝達」「対応」 視点は地震と同じ
BCPの各フェーズで、災害発生直後から開始する一連の緊急行動をERP(緊急対応プラン)と呼びます。ERPは地震なら地震、感染症なら感染症と、災害固有の行動に応じてさまざまに策定できますが、気候変動に対処するERPはどのような点に留意すればよいでしょうか。今回は気候変動のなかでも、急性リスクに対処するERPについて解説します。
2021/03/18
-

システム監視・ログ管理・AI予測をワンパッケージで提供するソフトウェア
セキュアヴェイルの100%子会社であるLogStareは、次世代マネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」シリーズから、システム監視・ログ管理・AI予測をワンパッケージで提供するオンプレミスのソフトウェア「LogStare Quint(ログステア・クイント)」(5月以降順次出荷予定)を販売する。
2021/03/17
-

第138回:12年間にわたって続けられているBCIのサプライチェーン・レジリエンス調査
BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCIが「Supply Chain Resilience Report 2021」という調査報告書を2021年3月9日に発表した。これはBCIが主に会員を対象としてサプライチェーンの途絶に関するアンケート調査を実施し、その結果をまとめたものである。
2021/03/16
-

破損箇所からの雨・風の侵入を防ぐ「全面粘着ブルーシート」
日東電工グループのニトムズは、自然災害や暴風雨などで破損した窓や壁、屋根などの一次補修として、貼るだけで簡易補修ができる「全面粘着ブルーシート」を販売する。粘着剤が塗布されたブルーシートで、従来必要だったテープなどがなくても単体で簡易補修を行えるようにしたもの。
2021/03/16
-
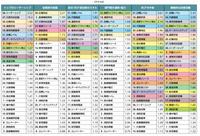
初動対応でBCP以外に必要な要素地震想定シミュレーション型アンケートその2
リスク対策.comは、地震災害時の自社の被害状況や対応状況について具体的にイメージをしながらアンケートに回答してもらう「シミュレーション型アンケート」を実施しました。前回は全体の回答結果の傾向を解説しましたが、今回は回答結果から見えてきた防災やBCPの課題を解説します。
2021/03/15
-

エスカレーターは歩く? 歩かない?
2021年3月4日に「全国初『エスカレーター歩かない』条例案提出 事故防止へ 埼玉」という記事がありました。 転倒による事故を防ぐのが目的で、エスカレーターで走ったり歩いたりせず、止まって乗ることを努力義務とする条例案を埼玉県議会に提出したようです。ちなみに努力義務なので、違反に対する罰則はありません。
2021/03/15
-

掘削作業や雪かき作業の負荷を低減するアシストスーツ
ダイヤ工業は、工事現場での人力掘削作業の負荷低減を図る目的で清水建設と共同開発したアシストスーツ「ワーキングアシストAS」を販売する。埋設物があり自動化が難しい掘削作業のある建設現場や道路舗装の工事現場等、スコップを使った掘削作業者を対象に販売を行うほか、豪雪地帯での雪かき作業や、夏場の草刈り作業などでの活用も提案するもの。
2021/03/12
-

第2回 平時から備える本社機能バックアップ体制
第2回となる今回は、大阪で実際に本社機能のバックアップ体制を構築されている先進事例として、明治安田生命保険相互会社様の取り組みをご紹介しながら、平時から本社機能バックアップ体制を構築しておく必要性について考えたいと思います。明治安田生命保険相互会社で災害対策をご担当されている総務部の藤山佳希氏と、大阪本部の馬場清聡氏にお話を伺いしました。
2021/03/12
-
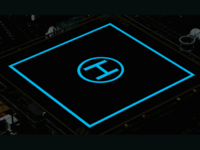
災害救助の暗闇対策となる12時間発光可能な蓄光塗料
高輝度蓄光塗料推進協会は、災害時における救助活動の暗闇対策として、既存コンクリート素材などに塗布可能で、長期耐久性を備えた「RM蓄光塗料」(RM=Relief Marking)を開発し、全国の塗装会社と連携して展開する。
2021/03/10
-

CO2濃度と経済活動を可視化
データサイエンスで企業の課題を解決するDATAFLUCTは、大気中の二酸化炭素やメタン等の濃度を測定できる温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の衛星データを活用し、CO2の濃度と経済活動を可視化する環境モニタリングサービス『DATAFLUCT co2-monitoring.』(データフラクト シーオーツーモニタリング)』を提供する。
2021/03/09
-

第137回:サプライチェーンがこれからの環境変化に適応していくためのレジリエンスとは
英国の雑誌『The Economist』の調査部門であるEconomist Intelligence Unitが、サプライチェーン・マネジメント協会からの委託を受けて実施した調査結果を、「The Resilient Supply Chain Benchmark」という報告書にまとめて2021年2月に発表した。この報告書は、2020年10月に米国の上場企業の中から308社を対象として行われたサプライチェーンのレジリエンスに関するベンチマーキングの結果と、各社から公開されている情報、およびさまざまな分野のエキスパートへのインタビューをまとめたもの。
2021/03/09
-

コロナ禍での複合災害対策本部を考える~ITフル活用と新たなマネジメント、変質する組織~
4月のPRO会員勉強会は、プリンシプルBCP研究所所長の林田朋之氏を講師にお招きし、コロナ禍での複合災害に備えたリモート災害対策本部のあり方を考えます。従来の怒号飛び交う大部屋の設えに代わるかたちとは? 部屋別分散やテレワーク環境を利用した運営はうまく機能するのか? そして、リモート災害対策本部の本質とは? ぜひいっしょに語りましょう。
2021/03/09
-

IoT機器の脆弱性情報分析を約80%短縮
日立製作所は、製造業の製品セキュリティ担当者向けに、IoT機器などの製品セキュリティにおける脅威・脆弱性情報を収集・分析する「脅威インテリジェンス提供サービス」(AI機能強化版、4月1日発売予定)を提供する。
2021/03/08
-

ピックアップ特集 東日本大震災から10年
東日本大震災か10年。いま、日本社会は新型コロナウイルスによる危機に直面しています。10年前に比べ、BCP策定企業の数は飛躍的に増えました。しかし、本当に問うべきものは問われたのか。がれきに誓った思いは実現をみたのか。もう一度、危機対応について語りましょう。何が壊され、何が残り、何が再生し、何が変わったのか、事例紹介やインタビューを通じて追体験しましょう。
2021/03/07
-

「買い物客」守る初動マニュアル 訓練で実効性担保
東北地方を代表する老舗百貨店の藤崎(仙台市青葉区、藤﨑三郎助社長)は3.11を機にBCPを策定。災害時の基本方針とワークフローを明確化するとともに以前から行っていた防災訓練を充実、各地の小規模店舗も網羅しながら初動にかかる従業員の練度を高めている。また、早期復旧と地域支援を事業継続方針に掲げ、百貨店が地域に果たす役割を問い直しつつ、取引先や顧客との新しいつながりを模索する。
2021/03/07
-

改良を積み重ねたサプライチェーン管理手法
東日本大震災では、部品供給網の寸断が大きな課題となった。その後も、災害がある度にサプライチェーン問題が顕在化している。製品に使われる部品そのものが複雑になっていることに加え、気候変動などに伴う異常気象が追い打ちをかける。日産自動車では、東日本大震災前からの継続的なBCPの取り組みと、過去の災害検証を生かしたサプライチェーン管理の仕組みにより、災害対策に手ごたえを感じ始めている。コーポレートサービス統括部担当部長の山梨慶太氏に聞いた。
2021/03/07
-

スマホ10台同時急速充電できるEV再利用バッテリー
リチウムイオン蓄電池システムの開発を手掛けるベイサンは、国産電気自動車のリユースリチウムイオンバッテリーをアップサイクルし、スマートフォン10台を同時急速充電できるデスクトップパワーユニット「R-ARCA(アールアルカ)」を販売する。
2021/03/05
-

交換回数減らせる非常用簡易トイレ
大塚ホールディングスの子会社である大塚包装工業は、災害用備蓄品「トワレスブランド」から、自然災害等でトイレが使用できなくなる緊急時に対応する「非常用簡易トイレ エチケットタイプ」を販売する。
2021/03/04
-

災害多発時代の事業継続オプションとしてのテレワーク
ソーシャルディスタンスを確保するためのリモートワークも、元の「通勤型」に戻りつつあります。感染予防策を徹底すれば通勤型でも在宅型でも問題ありませんが、気候変動にともなう災害が多発するであろう時代を考えると、テレワークやオンライン会議を「非常時の業務継続オプション」として生かすことは十分に意義あること。今回は危機対策本部のリモート体制について考えます。
2021/03/04
-

OKRを応用した新たな管理手法「OTD(Objectives & ToDo)」
前回の投稿では、災害対策本部をウェブ上で構築・運用する方法として、災害ポータルサイトの活用について説明しました。今回は、その災害ポータルサイトを活用してテレワークされた複合災害対策本部全体の組織的なマネジメントをテーマにしたいと思います。
2021/03/04
-

防災の根本問題は、避難所需要に対して資源が圧倒的に少ないこと
東日本大震災からこの10年間、日本は大規模自然災害に次々に襲われた。被災者が入る避難所も、さまざまな経験を経て10年前に比べればかなりの改善が見られる。 東京大学生産技術研究所の加藤孝明教授は、公共施設を前提とした避難所は、避難所の需要に対して圧倒的に少ないと指摘。民間の「災害時遊休施設」の活用や「災害時自立生活圏」を増やして需要を減少させることが必要だと訴える。
2021/03/03


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



