レジリエンス
-
地域未来戦略本部を設置=地方経済の活性化推進―政府
政府は11日、地方経済の活性化に向け、高市早苗首相を本部長とする「地域未来戦略本部」を設置した。これまでの地方創生の取り組みに加え、産業拠点の形成や地場産業の付加価値向上など、経済に重点を置いた政策を検討する。 木原稔官房長官と黄川田仁志地方創生担当相が副本部長を務める。
2025/11/11
-
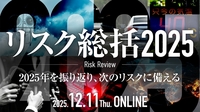
リスク総括2025
今年は猛暑・豪雨など自然災害が頻発し、多重被災への備えが課題。DX進展でサイバー攻撃が深刻化、企業活動に影響。品質不正や人権問題も顕在化し、国際情勢変化で地政学リスクが増大。危機管理体制の再構築が急務。いま、企業は何をすべきか、どう備えるべきか。本セミナーでは今年起きた出来事とその対応を振り返り、危機管理の見直しのポイントを探る。
2025/11/10
-
「修理」選択、解体の約半数=能登6市町の全・半壊住家―背景に費用高騰や業者不足
昨年の能登半島地震や豪雨で「半壊以上」の被害認定を受けた石川県七尾市以北6市町の住家のうち、修理費用の一部を自治体が負担する「応急修理制度」を利用したのは公費解体を選択したケースの約半数にとどまることが6日、分かった。
2025/11/07
-

未曽有の分断の実像と日本への影響
未曽有の分断が世界規模で進み、ビジネスにも影響を与えています。折しも先月はアメリカのトランプ大統領が来日し、高市新総理の外交が注目されたところ。一方、ロシアはウクライナとの停戦に応じる気配がなく、西側諸国との対立姿勢を崩しません。今号は両国の政情に詳しい専門家に分断の実像と日本への影響、今後の行方を聞きました。
2025/11/05
-

第5回リスクアドバイザー情報交換会1年間の経験を共有し、来年に備える
リスクアドバイザーの情報交換会を開催します。
2025/11/04
-

2026年リスク地図 解説セミナー― 危機管理白書で読み解く次の備えとDX戦略 ―
2025年に直面した多様なリスクを振り返りながら、2026年に向けた重点対策を考えます。年末に発刊される「危機管理白書2026」をベースに、企業のリスク担当者が押さえるべき10のキーワードを解説。さらに、災害時の通信手段やドローン活用など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の可能性について、最新の調査結果と先進事例をもとに分析・議論します。
2025/11/04
-
来夏に成長戦略策定=AI・造船など17分野に重点投資―高市首相
政府は4日午前、高市早苗首相が掲げる「力強い経済成長」の実現に向け、全閣僚による「日本成長戦略本部」の初会合を首相官邸で開いた。本部長の首相は席上、「来年の夏、成長戦略を策定する」と表明。
2025/11/04
-
火山防災でオンデマンド研修=人材不足に対応、各地で対策強化―内閣府
内閣府は、火山防災についての専門的な知識を持った人材を育成するため、自治体担当者ら向けにオンデマンド動画方式の研修を始めた。火山災害の発生は頻度が少なく、経験を持つ人材が不足している現状に対応。より多くの担当者に学んでもらい、避難計画作成をはじめとした対策の強化を各地で後押しする狙いだ。
2025/11/04
-

実践的「対策本部」設置・運営講座【2026年2月18日開催】
本講座では、対策本部の設置・運営に必要な基本的な考え方を学び、ワークショップや訓練を通じて実践的な知識・ノウハウを身につけます。
2025/10/30
-
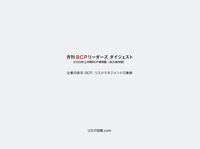
月刊BCPリーダーズ2025年上半期事例集【永久保存版】
リスク対策.comは「月刊BCPリーダーズダイジェスト2025年上半期事例集」を発行しました。防災・BCP、リスクマネジメントに取り組む12社の事例を紹介しています。危機管理の実践イメージをつかむため、また昨今のリスク対策の動向をつかむための情報源としてお役立てください。
2025/10/24
-

第8回 ややこしい米国の「従業員のソーシャルメディアでの政治的発言」
多くの人々が政治的に重要な問題について意見を表わす上で、ソーシャルメディアは公共の場となっている。中東紛争、ロシアとウクライナの進行中の戦争、アメリカの政治、政治家の暗殺など、話題が何であれ、従業員はX(旧Twitter)・Facebook・Instagram・TikTokなどのプラットフォームを利用して意見を共有することが増えている。
2025/10/24
-
NTT東子会社、コンテナ型データセンターに参入=北海道石狩市に1基目導入
NTT東日本子会社でDX支援などを手掛けるエヌ・ティ・ティ エムイー(東京)は22日、コンテナ型のデータセンターに参入すると発表した。比較的狭い敷地でも設置でき、ビル型より短期間で構築できるのが強み。1基目を北海道石狩市に設ける計画で、2027年4月の稼働開始を目指す。 。
2025/10/22
-
通信大手が避難所支援で連携=地域分担で復旧迅速化
NTTグループとKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信大手各社は22日、地震など災害時の避難所支援で連携すると発表した。スマートフォン向けの通信サービスや充電設備を提供する地域を分担し、より迅速にバランスよく支援が行き渡るようにする。
2025/10/22
-
高市首相、防災庁の来年度設置堅持=復興相が準備担当兼務
高市早苗首相は21日の就任記者会見で、2026年度中の防災庁設置を目指す石破前政権の方針を堅持し、準備を進める考えを示した。復興庁の知見を生かすため、牧野京夫復興相に防災庁設置準備担当を兼務させると説明した。
2025/10/22
-
「副首都」構想を注視=「オールジャパン」求める声も―各知事
自民党と日本維新の会による連立政権では、維新が掲げる「副首都」構想に関する検討が進む見通しとなった。東京一極集中の是正や大規模災害時の首都機能確保が目的で、各知事はその行方を注視している。
2025/10/21
-
KDDI、ドローンを石川・能登に配備=災害対応力を強化
KDDIは16日、人工知能(AI)を搭載したドローンを石川県の能登地域の公共施設4カ所に常設配備したと発表した。モバイル通信を用いた遠隔操作が可能で、災害発生時には被災地から離れた場所でも操作できる。地域の災害対応力の強化に向けてまずは能登地域に配備し、将来的に全国1000カ所への常設を目指す。 。
2025/10/16
-
緊急地震速報に活用開始=四国・九州沖の沖合海底観測網―気象庁
気象庁は15日正午に、防災科学技術研究所が四国・九州沖に整備した「南海トラフ海底地震津波観測網(N―net)」のうち、沖合システムについて、緊急地震速報への活用を始めた。南海トラフ沿いで大きめの地震が発生した場合、同速報が最大で約20秒早くなるという。
2025/10/15
-
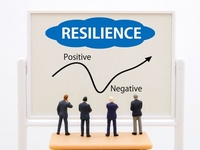
BCPは時代の要求に追いついているか?
前々回、BCPは「守り」から「攻め」へ転換していると申し上げました。BCPは企業のサスティナビリティ戦略の一環として、価値創造のうえで重要な要素。複合災害を含め予測困難なリスクにも対応できなければなりません。オールハザード型BCPが不可欠ですが、いまだ課題が多いのが実情です。あらためてオールハザード型BCPの課題を整理します。
2025/10/15
-
NTT東、東京・八丈島で通信設備周辺が地盤崩落=台風22号で、本格復旧に時間
NTT東日本は14日、台風22号の影響で八丈島(東京都八丈町)の固定電話約120回線が不通やつながりにくくなっていることに関し、通信設備周辺での地盤崩落を確認したと発表した。現地調査を進めているが、本格復旧には時間を要する見通し。利用者には緊急通報などは携帯電話や公衆電話を使うよう呼び掛けている。
2025/10/14
-

第7回 企業組織のリスク・レジリエンス構築への道
組織は、かつてないレベルの経済的・技術的・地政学的混乱に直面しており、より積極的なリスク管理戦略が求められている。あらゆる組織にとって、全領域のリスク管理とレジリエンス能力を構築するだけでなく、リスクとレジリエンス計画を実践するための実践的な戦略を策定することが重要である。
2025/10/14
-
街路樹安全確保で指針策定へ=自治体向け、交通量考慮し重点化―国交省
国土交通省は、街路樹の倒木や枝の落下による事故を防ぐため、自治体向けのガイドライン(指針)を策定する。重点的に点検を行う路線を選定する際、交通量や樹齢を考慮するといった留意事項を盛り込む。自治体の人手や予算に限りがある中、効率的な巡回を後押しして安全確保につなげる狙いだ。
2025/10/09
-
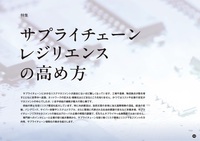
サプライヤー支援を強めるグローバル企業
サプライチェーンにかかるリスクマネジメントがかつてないほど難しくなっています。ネットワークの巨大化・複雑化はとどまるところを知らず、そのうえ供給の混乱を招くリスク要因は多様化。サプライチェーンリスクマネジメントの強化はグローバル企業の喫緊の課題です。サプライチェーンを取り巻くリスク環境と強靱化の動きを紹介します。
2025/10/05
-
KDDI、「防災ボード」を自治体向け提供=地図上に情報一元化、AIで情報収集も
KDDIは1日、雨雲レーダーやハザードマップなどの情報を1枚の地図上に重ねて表示できるサービス「防災マップボード」を、自治体向けに同日から商用提供すると発表した。複数のシステムなどを行き来せずに一元化した情報を確認でき、緊急時の意思決定をスムーズに行えるよう支援する。 。
2025/10/01
-

【危機管理塾】パナソニックのBCP進展とDXによる発展
2025年11月の危機管理塾は11月19日(木曜日)16時から行います。今回はパナソニックオペレーショナルエクセレンスの青江 多恵子氏を講師に迎えて、大阪にて開催します。
2025/09/30
-

【危機管理塾・大阪開催】パナソニックのBCP進展とDXによる発展
2025年10月の危機管理塾は10月23日(木曜日)16時から行います。今回はパナソニックオペレーショナルエクセレンスの青江 多恵子氏を講師に迎えて、大阪にて開催します。
2025/09/30


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



