容認すべき失言を糾弾する社会構造の問題点
第92回:嘘と真実を語る失言(4)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2025/07/30
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
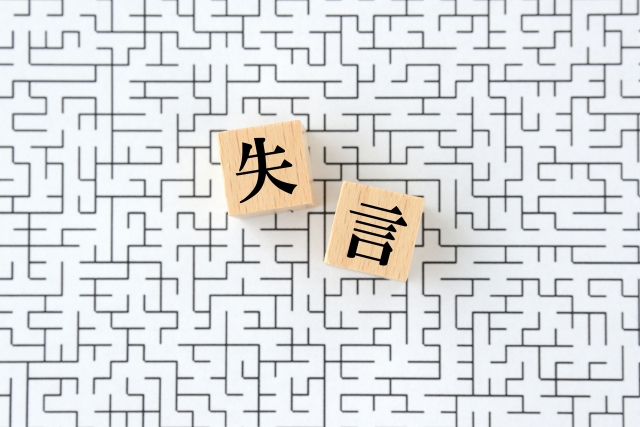
ここまで、嘘の構造に関して語り、前回は炎上にスポットをあてた。今回はその表裏一体でもある失言の側面から検討したい。
政治家や著名人のなかには失言を繰り返す人物も多く、メディアがこぞって集中攻撃をする事態を目の当たりにすることは少なくない。それでも、失言は繰り返される。しかし、その失言を一つ一つ丹念に見てみると、その構造にはいくつかの種類があり、それを以下に簡単に示してみる。
まだまだあるかもしれないが、まずはこのあたりで留めよう。こうやって客観的に記述すると冷静に見極められると感じそうだが、実社会でこれらが混在する状況で本当に見極められるだろうか。
大別すると①~④はポジティブで⑤~⑧はネガティブといってよいだろう。統計を取っているわけではないが、傾向として、このポジティブな発言の方が失言として糾弾される傾向が強いように思う。一方でネガティブな発言の方は失言とされず、納得や共感さえもたらす傾向にあることが、感覚的に理解いただけるのではないだろうか。

誤解を恐れずにいわせていただくと、このポジティブな発言を失言とする扱いはレッテル貼りであり、人として痛いところを突かれた時の防御反応や、自らの既得権益・安住の地を脅かす存在に対して攻撃性を帯びてしまった結果の現象にほかならないと感じる。このことは筆者の勝手な推測に過ぎないが、その推測が間違っていたとしても、本来この種のポジティブな発言は糾弾どころか推奨されるべきものであることは揺るがないだろう。
組織に属し、何らかの改革や改善手段を講じようとした経験があればおわかりだろうが、その改革が抜本的で本質的であればあるほど、強い抵抗勢力が生まれる。当事者であれば、この抵抗勢力とどうやって対峙し、御するかが重要戦術になるが、周囲にいる第三者から見た場合はどうなるだろう。
抵抗勢力の発する攻撃は、表向きは論理的で正義をかざしているように第三者からは見えることが多い。その攻撃に異を唱えた瞬間、次の攻撃のターゲットにされる可能性があるため、尻込みもするのだろう。つまり、集団いじめの構造に似ているのである。

これが閉鎖的な空間の話なら、第三者としてのスルーも許されるかもしれない。しかし、社会的に糾弾されている失言は、第三者のようでいて、実は当事者でもあるので厄介だ。判断ができず、第三者としてサイレントマジョリティ姿勢を貫くのは、実は沈黙の同意となり、既得権益側の攻撃を容認する行為になる。つまり物言わぬ第三者は、本質的な改革を目指す者にとっての抵抗勢力になっていることを自覚するべきだ。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26



報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23


※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方