2019/10/01
ペットライフセーバーズ:助かる命を助けるために
3 検討
(1) 国家賠償法に基づく損害賠償請求の要件
ア 避難所を管理している自治体に問いうる法的責任はいわゆる国家賠償法に基づく損害賠償請求である。
同法に基づく損害賠償請求は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた」場合に認められる(同法1条1項)。
イ そして、上記にいう「違法に」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することとされる(最高裁判所判決昭和60年2月3日民集39巻7号153頁)。
ウ そのうえで、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められるためには「一般には公務員がその権力を恣意的に過大に行使して国民の生命・身体、自由、財産等を積極的に侵害する行為が考えられる。公務員の不作為つまり権力の過小な行使は原則として加害行為とはなりえない。しかし、法令上具体的な作為義務(国民を保護したり情報を周知させる義務のごとし)をもつ公務員が義務に違反して職務を怠り、その結果国民に損害を生じさせた場合には、その不作為(権力の過小な行使)は違法となり加害行為とされる」とする見解が有力である(※4)。
(2) 原則論
ア 上記2(1)の通り、動物愛護管理法には自治体に同伴避難を可能にすることを義務づける規定はない。また災害基本法、災害救助法には動物に関する規定そのものがない。上記2(2)の通り、動物救護に配慮した防災計画・ガイドラインの整備が進みつつあるが、防災計画・ガイドラインは自治体への法的義務を課したものではない。
従って同伴避難を認めることが公務員にとって「個別の国民に対して負担する職務上の法的義務」や「法令上具体的な作為義務」に当たるとは言い難いのが現実である。また仮にこれらの点をクリアしたとしても認められる賠償額は上記2(3)の裁判例等に照らし、多くとも数十万円程度にとどまると考えられる。従って、飼い主の救済としては不十分である。もちろん額の多寡を問わず事後的に賠償が行われても命を失った動物自身の救済にはならないことも当然である。
これは日本の法制上、動物を人から離れた独自の権利を持つとは捉えていないことが要因の一つである。
イ この点について日本における動物保護法制に関し「西欧法を比較対象とした際の日本法の相対的特徴として(1)動物法の歴史が浅いこと(2)動物法は質量ともに充実していないこと(3)動物法が近年になって急速な発展を始めたこと(4)動物関連諸立法を「動物法」という問題関心のもとに体系的に把握しようという意識が弱い」旨の指摘がある(※5)。そこで以下では視点を転じ、西欧法の状況を概観する。
(3) 諸外国における動向と展望
ア 諸外国における動向
ドイツでは憲法上「国は、来るべき世代に対する責任を果たすためにも、憲法に適合する秩序の枠内において立法を通じて、また、法律および法の基準に従って執行権および裁判を通じて、自然的生活基盤および動物を保護する」旨(基本法20a条)が、民法上「動物は物ではない。動物は特別法により保護される」旨(90a条)が、民事訴訟法上動物に対する人間の責任が言及され(765条a条1項3文)、動物保護法上「この法律は、同じ被造物としての動物に対する人の責任に基づいて、動物の生命および健在を保護することを目的とする。何人も、合理的な理由なしに、動物に対して痛み、苦痛または傷害を与えてはならない」旨(1条)がそれぞれ定められている(※6)。
イギリスではマーチン法(蓄獣の虐待を防止する法律、1822年)が制定されたのち法整備が進み、世界で最も手厚いとされる2006年動物福祉法が成立している(※7)。
スイスでは憲法上「連邦は、動物、植物、および、その他有機体の生殖細胞および遺伝形質の取り扱いに関する規定を公布する。その際、連邦は、被造物〔生物〕の尊厳、ならびに、人間、動物、および、環境の安全を考慮し、かつ、動植物種の遺伝上の多様性を保護する」旨(1999年新憲法120条2項)が定められている(※8)。
さらに、欧州全体として1987年にペット動物の保護に関する欧州条約が成立している(※9)。
これは、国民意識として動物を単なる物ではなく、動物を人から離れた独自の権利を持つと捉える考え方、つまり「感覚性をもつ動物は道徳的地位を持っている。すなわち、彼らの利害-あるいは集合的にいうと彼らの福祉-は独自の道徳的重要性をもっている。言い換えれば、われわれは動物に対して義務を負っており、その義務は単に人間の利害を理由とするものではない。動物自身が〔固有の価値ゆえに〕虐待されてはならないのである。われわれは動物を彼ら自身のためによく扱うべきである。」という考え方を背景にしている(※10)。アメリカにおいても類似した考え方が主流となっている(※11)。
イ 展望
上記アの通り、現時点の日本における動物保護法制が西欧と比較して未整備であることは否定できない。
しかし、日本が歴史的に見て動物保護の分野において遅れているとはいえない。
すなわち、日本においては養老5年(721年)に殺生禁断令が定められ、その後も同様の法令が断続的に制定されてきた。特に江戸幕府第5代将軍徳川綱吉によって貞享4年(1687年)に制定された生類憐れみの令は動物愛護の先駆的事例であるとして再評価されつつある(※12)。
国民意識としても「日本ではアニミズムや多神教的な感性に基づく神道や、衆生(有情)や輪廻転生という仏教の教えにより、古代から人と動物の命に明確な区別をつけず同等に扱われることが多かった」と指摘されている(※13)。現時点の日本における動物保護法制が西欧と比較して未整備であることは日本が明治期などに外国法を継受した際、当該外国法において動物保護の規定が不十分だったからに過ぎないと考えられる。
近時、動物が理由なく死亡したり殺されたり、また傷ついたり傷つけられたりしないような施策を講じる義務を国が憲法25条(生存権規定)に基づいて負うとする新しい見解が主張されている(※14)。
このような見解は上記日本の歴史的経緯、国民意識からすれば十分支持されうる。このような見解への支持が広がれば同伴避難の問題を含めた災害時の動物救護に関して法的にも大きな前進が可能となる。このたびの台風第15号による災害を契機としてさらなる国民的議論がなされることが期待される。
以上、南部先生の法的アドバイス。
- keyword
- ペットライフセーバーズ
- 同行避難
- 避難所
- ペット
ペットライフセーバーズ:助かる命を助けるためにの他の記事
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-
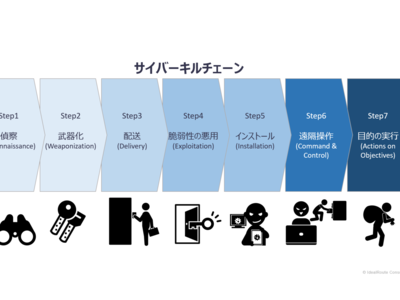
-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方