2017/04/12
熊本地震から1年

熊本地震では、多くの研究機関が被災する中、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、産業技術総合研究所、防災科学技術研究所の地震研究者らが「2016年熊本地震合同地震観測グループ」をつくり、緊急地震観測を開始した。長崎県島原市にある九州大学地震火山観測研究センター島原観測所の松本聡氏に、観測を開始するまでの対応とその後直面した課題などを聞いた。
一泊四日の緊急事態

前震とされる地震が起きた日、僕は東京にいました。翌日、ヨーロッパで開かれる学会に向け出発する予定だったので東京に泊まっていたのです。地震の後、夜10時ぐらいに地震研(東京大学地震研究所)に行き、同研究所の方と朝方までかけて何をするかを決めました。
こういうイベントが起きた時にどう振る舞うかは、大学の中では、おおむね合意されています。基本は、震源に近い地域の大学が全部面倒を見る。つまり観測活動の準備をする。もし駄目だったときは、地震研か防災研(京都大学防災研究所)が面倒を見るということになっています。研究者は観測をしたい人がたくさんいるので、混乱しないようコントロールしようということで、どのくらいの観測が必要だという議論を行いました。
地震が起きた時には、震源に一番近い観測点が機能停止しているということがよくあるので、地震研には、そこをまず復旧することをお願いしました。翌日は予定通り学会が行われるウィーンに向け出発しました。
ウィーンには夕方に着き、時差ぼけでしたが就寝し、夜中にふと目が覚めて熊本で再び地震があったことを知りました。気象庁のホームページを見たら、震源分布が九州を横断して真っ赤になっているのです。学会発表を諦め、すぐに飛行機を手配し、翌日帰国しました。1泊4日の旅です。
M6.5に続く余震なら、震源域周辺や九州の内陸に40カ所ぐらいの地震計を臨時で置いていたので、Hi-netに比べて倍ぐらいの密度があるし、特に震源域は重点的にやっていたので、精度などやデータの量については大丈夫だと思っていたのですが、まさかのM7.3でした。
17日の昼には成田に着き、そこから飛行機を乗り換え九州に帰りました。九州に到着したのが夕方です。
センターに必要な危機管理体制
結果的に、16日未明に起きたM7.3の地震についても観測に実質的な支障はなかったのですが、今振り返って「やばかった」と思うのは、危機管理の問題です。つまり、スタッフの安全に対しての十分な配慮ができていなかった。幸い、何もありませんでしたが、スタッフが少ない状態だったので、何かトラブルがあったら、とても対応ができなかったと思います。
現地センターは、教員3人、研究員1人、そして技術員が2人います。あとはパートの方と学生です。でも、学生も含めて現地に観測に行った人はみんな本震を体験しているわけです。もちろん、誰がどこに泊まっているかは把握していますが、被災したら連絡がつかないし、何か起こった時に判断・対応できる状態ではなかったと思います。
いずれにせよ、17日の夕方にセンターにたどり着いて、それからは3日ぐらい寝られませんでした。まず、現場にいる人を集めて、方針を伝えました。第一に現状の確認と観測点の配置の見直しを指示しました。M6.5が起きたときとM7.3は違いますので、再度仕切り直した形です。
次の時代に役立つデータをとる
地震が起きた瞬間から、現状で自分たちが何をすべきかをずっと考えていました。具体的には、長期的な次の時代にも役立つようなデータを取ることと、今現在のモニタリングに資するようなことをすることです。
我々の観測には、電波を飛ばしてリアルタイムで取るデータと、現地に設置して時々計測するデータの二種類がありますが、リアルタイムのものをどこに置いてモニターすれば一番いいのかを考えていました。簡単に余震の予知ができるわけではないのですが、観測器を置かなければ絶対わからないし、確実に変なことが起きているのであれば傾向が見えるかもしれないと思ったのです。
最終的にモニタリングできたのは断層周辺の10カ所ぐらいでしたが、断層周辺といっても、どこにウエートを置くかというのがあって、震源が南に伸びることが心配でした。

熊本地震から1年の他の記事
おすすめ記事
-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

-












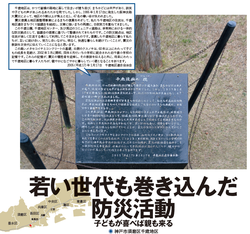














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方