2020/06/05
危機管理の神髄
ハリケーン・アイリーンがニューヨークを襲いかかった時、われわれは沿岸ストーム計画と実働部隊を稼働させた。市長は沿岸地域に強制退去命令を出した。約35万人が避難するように命令されたのである。
われわれは80カ所以上のシェルターを開設し、ある時点で1000人以上の特別な治療が必要な人も含め1万人以上を収容した。この災害対応のいずれかの期間に5000人もの市職員が働いたのである。
そして、われわれがシェルターを閉鎖した1カ月以内に、ニューヨーク市は召喚状を送達されたのである。2011年7月26日ブルックリン障害者自立のためのセンター(BCID)が、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、ブルームバーグ市長とニューヨーク市が緊急対応計画に障害を持った大人や子供たちの特別なニーズを含めることを怠り、彼らを差別したと訴えた。
訴状によると、ブルックリンに居住し、車いすを使っているタニア・モラレスは、ハリケーン・アイリーンの際に緊急シェルターから追い返された。シェルターへ入る傾斜路の門が施錠されシェルターの職員は鍵を見つけることができなかったためだったと、彼女は言っている。
訴状は、障害者の生活を“無視する行動類型”と“あからさまな軽視”があると主張する。
われわれはショックを受けた。
ハリケーン・アイリーンの際の緊急シェルター活動は、決して過ちのないものではない。どの緊急シェルター活動とも同じように、かなりひどい部分もあることは事実である。
マネジャー、職員、クライアント(避難者) も、80カ所のどのシェルターにおいても、発見した問題に光を当て、未開梱の荷物を開け、立上作業をし、クライアントの受付をしながら、最初の数分から問題や間違いに行きあたる。研修で習ったことを忘れたり、シェルターの解説書が行方不明になったりするスタッフがいるが、そのうちにそれを埋め合わせしなければならないと感じるようになる。そして、病気の人や停電などのもっと深刻な問題がある。スタッフはこれらの多くの問題をシェルター運営センターに持ち込み、そこで一つずつ解決していくのだ。
われわれは問題や失敗を注意深く見ており、緊急シェルター活動はいつもうまくいっているわけではないが、人々の安全は確保してきた。シェルターの管理マネジャー、スタッフ、クライアントが互いに団結した勇敢な努力のおかげで、オペレーションは成功であると考えていた。
われわれはモラレスの主張を立証できなかった。われわれの内部調査では、だれもどのような理由であれ、どのシェルターからも追い返された事例は見つからなかった。われわれは訴訟防御の態勢に入っていき、裁判所で争うべく法務部と働いた。NYPD、FDNY、保健局を含めた数十の関係省庁の人々、災害計画の立案と実施に携わったほとんどの人たちの証言録取を行った。私は数日費やして、障害者権利擁護(DRA)団体の原告弁護士の質問に答える宣誓証言を行った。
2013年3月ロウアー・マンハッタンのパール通り500番地の連邦裁判所において、訴訟の審理が開始された。市の訴訟代理人は、緊急事態計画プログラムは継続して進化し改善されてきていると主張した。一方、DRA弁護士はそれでは不十分であると一歩も譲らなかった。
そこで、ニューヨーク南部地区連邦地裁ジェッシー・ファーマン判事は判決を下した。
われわれは敗訴した。
ファーマン判事は、市が緊急事態と災害に対する計画策定と対応において、“非常に困難な仕事”に向かい合っていることと、全てに住民の災害時のニーズを満たすために市が広範な努力をしていることを認めたけれども、
しかしながら、争点は市が障害をもつ人々に対して、緊急時対応プログラムに関する意味のあるアクセスを十分に提供したかどうかである。この質問に対する答えは、「実施してこなかった」ということである。
BCID対ブルームバーグ訴訟NY南部地区連邦地裁11Civ/5590(JMF)(2013)
判事は双方が和解するように命令し、2014年9月20日に双方はファーマン判事が判決の中で述べた欠陥を改める包括的な合意を発表した。この合意は、特にニューヨーク市が運動障害を持った人を自宅から避難させる能力を改善し、避難中にアクセスできる利用できる交通手段を提供し、アクセスできるシェルターを提供し、停電で閉じ込められた人がいないか地域を巡回することを要求している。
新聞第一面ではなかったけれども、ニューヨークポスト紙の見出しはこのようなものであったろう。“ニューヨーク市は不十分とファーマン判事”。
問題なのは、BCID対ブルンバーグ訴訟までわれわれは何が十分なのかということを知らなかったことだ。
われわれはいつも計画作成において要支援障害者について検討してきたが、その策定の拠り所とする明確な基準がなかった。ファーマン判事がわれわれ全員に何を見るべきかに明確な線引きをしてくれた時に、われわれは持っている時間とリソースを使ってできるベストのことをやっていたのだった。この基準は連邦裁判所の判決であるので、ニューヨークは実施するための資金を見つける他に選択肢はなかった。
そういうわけで、われわれは敗訴したが、多くの面でそれは偉大な勝利であった。障害者・アクセスと機能の要支援者(Disabilities, Access and Functional Needs : DAFN) だけでなく、またニューヨークの人だけでもなかった。私が本当に理解したのは、私がニューヨーク市を退職した後であった。BCID対ブルームバーグ訴訟の教訓は、私にもまた傲慢の責任があるいうことなのだ。
もちろん、災害計画の全ての面で要支援障害者を受け入れることは難しいことである。しかし、これは私の仕事なのだ。それなら、何を考える?誰もそれが難しいかどうかを私に聞かない。
このことは、現場で直接人々と働くときには非常に明確になる。それはあなたが要支援障害者(DAFN)は使命の重要な部分ではなく、使命そのものであると学ぶ時である。
BCID対ブルームバーグ訴訟は画期的な訴訟となった。この和解とその要求事項は、われわれのレジリエンスの中にある境界の隙間を定義している。連邦司法省はこの隙間を正すために積極的に行動した。その公民権法は、緊急事態計画とその対応の全ての局面において要支援障害者(DAFN)の公平な機会を要求している。連邦と各州政府の役人は、新規則の解説と何がなされなければならないかについて数千ページのガイダンスを発行している。
しかしながら、われわれには1つの問題がある。
このようなことを実際に行う責任を負っている人たちがどのように実施すればいいのか見つけ出すのに苦悩しているのだ。
地元の災害専門家たちは努力をしている:彼らは支援ネットワークと計画を作成している。しかし、地元の自治体職員はすでに働き過ぎで、余力も資金もなく、それを実行するに必要な支援もないのである。現実は、この判決が要求することを実施することに誰も近づくことができないのである。
(続く)
翻訳:岡部紳一
この連載について http://www.risktaisaku.com/articles/-/15300
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-








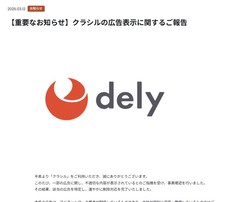


















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方