2020/06/22
事例から学ぶ
稼働率を維持し事業収入を確保し続ける
事業の影響度分析も行った。特別養護老人ホームで10%、ショートステイとデイサービスで20%、それぞれ稼働率が下がった場合を想定して財務諸表をシミュレーション。収入が減少する割に変動費が下がらないことが明確になった。
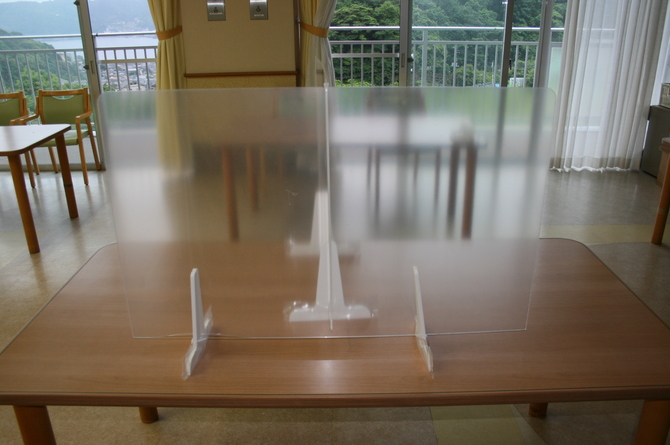
「例えばデイサービスで通常25人の利用者が10人になっても入浴は必要です。変動費は大きく変わりづらく、もちろん人件費も変わらない。感染症の場合は事業がゆるく継続できるがゆえに、そこでどれだけ利益が圧迫されるか定量的に把握することが重要」。資金や在庫、人員など、どのような備えが必要かの根拠を明確にし、固定量と変動量を明らかにする必要性を、長谷川氏は強調する。
「運営コストがかかる施設サービスは、将来への備えとして現金が必要。しかし現在働いている人への投資も必要で、バランスが難しい。そのためやはり、感染症拡大時も最低限の稼働を維持し、事業収入を確保しながら皆が安全に過ごすことを考えないといけない」
「ICT」「広報」「関係性」の大切さを実感
経営資源の備えとして、必要性を実感したのがICTだという。昨年12月に非接触型の体温測定器とタブレットを連動させた記録システムを導入していたことが奏功し、業務が大幅に効率化した。
「100人近い施設利用者の体温を人の手で1日2回測り、その都度ソフトに入力していたら、それだけで時間が終わってしまう。その点で今回、介護の現場は必要なハードを持っていないと今後の情勢変化のスピードについていけないことを実感した」とする。
見直しの必要性を実感したものもある。一つは危機広報のあり方。「病院や福祉施設のクラスター発生を伝える報道を見るたび複雑な感情にとらわれた」といい「公表が原則といわれるが、慣れていない者が大変な状況で情報発信しても正しく伝わるとは限らない」と説く。行動履歴を記録しているのは、危機広報に備える意味も大きい。
「必要なのは、全てをつまびらかにすることではなく、根拠とプロセスを明確にすること。『私はこの情報に対しこう考え、こう行動し、結果こうなった』というためには、記録とフォーマットが必要です」
もう一つはさまざまな人とのつながりだ。スタッフや取引先をはじめ、ステークホルダーとの良好な関係性以上に心強いものはないと、長谷川氏は実感を込めて話す。
「恐怖におびえて不安が続く日々になっていくと、誰もが自分を守る姿勢になる。とくスタッフが疲弊し、離職が起き、法令で定められた人員配置がとれなくなれば事業は継続できません。そのようにしないことがとても重要。そこにもBCPの役割があるのではないでしょうか」
https://www.risktaisaku.com/articles/-/33653
※7月7日の危機管理塾は終了しました。
事例から学ぶの他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/23
-

-

-

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方