2014/07/25
誌面情報 vol44
地震の揺れを再現して建物全体を揺らすなど、最先端の実験技術を取り入れた「減災館」が今年5月、名古屋大学(名古屋市千種区)に完成した。阪神・淡路大震災以降、地域に根差した防災活動を進めてきた同大学が、地元企業らの支援を得て設立した減災連携研究センターが入居する防災・減災の拠点だ。平時は研究と教育、各種セミナーなどで市民にも施設を開放し、大規模災害時には各種機関と連携しながら、大学や地域の災害対応拠点となる。福和伸夫館長(名大減災連携研究センター長)に減災館の機能と役割を聞いた。
減災館は、防災・減災に関する「研究推進の場」、防災を担う人づくりなど「地域の備えの実現の場」、巨大災害発生時の「対応拠点の場」としての3つの機能を持つ。
建物は、地震の揺れを低減する免震構造が採用されており、基礎をジャッキで引っ張って離すことで、建物自体を震度3程度に揺らすことができる「世界初の実験施設」(福和氏)だ。さらに屋上には震度5~6での大振幅長周期の揺れを再現できる実験施設も備え、これを建物全体を揺する加振機としても利用できる。非常用発電施設は1週間分の燃料を蓄え、都市ガスとプロパンガスを切り替えて燃料供給が継続できるようにし、空調を確保している。
通信なども冗長化されており、「官庁施設が集まる三の丸地区が被災した際には、代替拠点として対応にあたれるまでのレベルになっている」(福和氏)という。
内部は、1・2階が市民向けコーナーで、3・4階は研究施設。1階には、地震時に高層ビルが襲われる、振れ幅の大きな横揺れ「長周期地震動」が体感できる電動振動台がある。高層建物の中で巨大地震に遭遇した時の揺れを映像とともに振動台を使ってリアルに再現。床面には名古屋市と周辺市町村の空からの写真が投影される。
防災・減災に関するさまざまなセミナーや、減災カフェも1階の減災ホールや減災ギャラリーで開催される。このほか、これまで名古屋大学が10年以上にわたり取り組んできた耐震化活動の教材、データなどが展示されている。
2階はライブラリースペース。地震災害に関する歴史資料や古地図、過去に行ってきた100回にも及ぶセミナー映像、防災に関する10年分以上の記事やビデオなどがまとめられている。
誌面情報 vol44の他の記事
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-














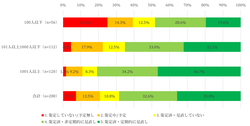















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方