2017/12/14
講演録

BCP(事業継続計画)をどうやって浸透させるか、BCPの本質とは一体何か。これは「人材」をどうやって作っていくか、ということに帰着します。社員の意識啓発をどのようにすれば、BCPを浸透させられるのか。
BCPのポイントとして3つ単語をご紹介します。「安全配慮義務」、「善管注意義務」、そして「内部統制」です。企業においては、損失に関する規定を会社の中で定めておくことになっています。内部統制を行う時は、安全管理をしっかりし、損失を回避する。つまり、BCPを財務面だけでなく、自然災害の面でも作っていかなければいけません。
BCPに重要なのは人材づくり
BCPはどうしても経営者目線、財務目線で考えますが、緊急時に判断できる人材を作っておかなければBCPは回りません。つまり、一人残された社員が最低限のことができる、いざという状況になったときに一緒にフォロワーになってくれる人を作っていくことです。また同時に、マニュアルを整備し、組織図を一度見直すことです。
では、組織の中で、どうしたら防災やリスクが自分ごとになるのか。どうやって災害を、人の目線、生活目線で考えていくのか。
被災後、最初のニーズは、実は生活のニーズです。被災したときにこそ、当たり前の生活が非常にシビアになってきます。子どもの教育、介護、保険。さまざまな立場に置かれた方々が生活に困りごとを抱えます。
命が助かったあとで、地域のために、会社のために働かなければいけない。しかし、その間も、実は自分たちの生活にも同時並行で悩みが押し寄せてきます。支払いや支援と葛藤し、家族と自分の生活の見通しをつけながら、自分からは決して言わない悩みを抱えたまま、現在進行形で先に進んでいくのす。
生活再建の悩みを解決するために
では、この部分をどうやって学んでいくか。日頃のみなさんの当たり前の生活を考えてください。南海トラフや首都直下地震で、家が壊れ、事業所が壊れ、活動が停止し、あるいは会社が維持されていても、自分の仕事が当面動かなくなったときに、我々は一体どういう悩みを抱えるでしょうか。
「住宅ローンを抱えているが、マンションが全壊してしまった。これから住まいの再建をどうしたらよいのか、見当もつかない」「当面の生活費を捻出することも困難になってきた。どうしようもないのか」という生活再建の悩みが東日本大震災でも熊本地震でも押し寄せていました。
たとえば「自然災害債務整理ガイドライン」という制度は、本来なら被災者のほぼ全員に知っておいていただきたい、特にローンを抱えている方に知っておいて欲しい単語です。こうした良い制度がたくさんあるにも関わらず、話題にならないし、誰も教えてくれない。組織の職員であれば、いずれ何らかのかたちで直面する話題です。ぜひ企業として知っておいていただきたい。そのためには、日頃の社員研修や幹部研修の中で、「生活再建の知識の備え」を学ぶ研修を行っていく必要があります。社員研修に新しい項目を作っていくことになるでしょう。
被災することを一個人目線でとらえ、組織の人間を守るため、予防策として福利厚生的にしっかりとこうした知識を与えておくことで、組織の環境としては非常に良くなっていくと思います。
(了)
講演録の他の記事
おすすめ記事
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/09
-

-

-

-
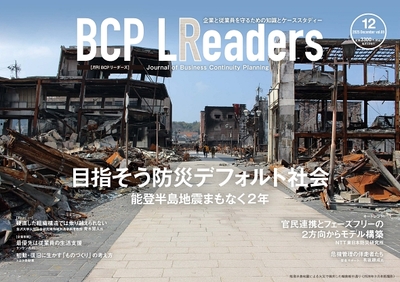
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/12/05
-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる
予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。
2025/12/04
-
























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方