2018/08/13
安心、それが最大の敵だ
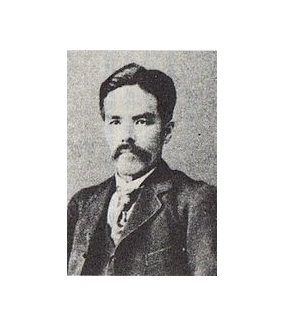
<不敬事件>とそのトラウマ
明治23年(1890)10月30日、教育勅語が発布された。アメリカ留学から帰国した内村鑑三は、この年9月、第一高等中学校(後の第一高校)の嘱託教員として勤めることになったが、時代の荒波にのみ込まれた。月給は65円で、担当は英語と地文(人文地理学・地学)であった。同校では、新年の1月9日授業開始に当たり、天皇自ら親著の教育勅語を受領したばかりであったので奉読式が挙行された。教頭が教育勅語を奉読した後、教員と生徒が勅語に記された明治天皇の署名に対し御真影と同じように「奉拝」することになっていた。鑑三は初めてのことでとっさの判断がつかずためらいがあったようで、わずかしか頭を下げなかった。内村が、自らが信仰するキリスト教の像以外には頭を下げるべきでないと考えていたことは間違いあるまい。
無二のアメリカ人親友ベルに宛てた英文の手紙で「私には恐ろしい瞬間だった。ただちに自分の行動の結果がわかったからだ」と書き送っている。この行為は新聞などを通じて「キリスト教徒による不敬事件」として喧伝された。一連の報道などで心労も重なり鑑三が重い流感にかかり病床に伏している間に、何者かによって辞職願が学校当局に提出され受理された。内村は職を奪われ、友は離れた。教会からは避けられ、暴徒の襲撃を受け、「国事犯人」として旅館にも泊まれなかった。内村はそれ以降20年間ゆっくり眠れなかったと回顧している。この事件は内村の一生を決定づけただけでなく、日本の進路も決めてしまった。
その後、内村は明治30年(1897)以降降、黒岩涙香(くろいわるいこう)発刊の新聞「万朝報」での明治薩長藩閥政府批判などの辛辣(しんらつ)な論説活動によって、マスコミの寵児となり知的青年層(東京帝大、高等師範(現筑波大学)、高等女子師範(現お茶の水女子大学などの学生ら)の心をとらえた。眠れる獅子が立ち上がり咆哮(ほうこう)しだしたのである。内村はジャーナリストとしての才能も豊かだった。
クリスチャンとしての良心と反戦思想
帝国日本は大国ロシアとの無謀な大血戦に突入する。明治36年(1903)夏、ロシアのシベリア鉄道はバイカル湖の迂回線を除く全線が開通した。同国の東清鉄道とその南部支線もつながった。ロシアは清に約束した撤兵期限を過ぎても満州に駐留し、兵力を増強する動きも見せた。東京帝大教授・戸水寛人(とみずひろんど)ら7人の博士は桂太郎首相に「対露開戦」を迫る意見書を出した。これにより一気に開戦の世論が高まった。だが戦力、財力、物量全ての面で日本に勝ち目は薄かった。主戦派の軍人たちでも、いざ戦争を指揮するとなると及び腰になった。
日本国内では日露開戦をめぐって新聞は賛否両論の激しい言論戦を展開していた。東京・大阪の「朝日新聞」「時事新報」「大阪毎日」「国民新聞」は対露強硬論・開戦支持に傾き、「万朝報(よろずちょうほう)」、「二六新報」は非戦を主張した。内村鑑三は、東京一の販売部数にのし上がり一流紙の仲間入りした「万朝報」によって絶対非戦論を叫んだ。明治36年6月30日、彼は「万朝報」に「戦争廃止論」を書いた。
「余は日露非開戦論者であるばかりでない。戦争絶対的廃止論者である。戦争は人を殺すことである。そうして人を殺すことは大罪悪である。そうして大罪悪を犯して個人も国家も永久に利益を収め得ようはずがない。(中略)。世には戦争の利益を説く者がある。然り、余も一時はかかる愚を唱えた者である。しかしながら今に至ってその愚の極なりしを表白する。戦争の利益はその害毒を贖(ルビあがな)うに足りない。戦争の利益は強盗の利益である。これは盗みし者の一時の利益であって(もしこれをしも利益と称するを得ば)、彼と盗まれし者との永久の不利益である。盗みし者の道徳はこれが為に堕落し、その結果として彼はついに彼が剣を抜いて盗み得しものよりも数層倍のものを以て彼の罪悪を償わざるを得ざるに至る。もし世に大愚の極と称すべきものがあれば、それは剣を以て国運の進歩を計らんとすることである」(以下略)。
9月1日付の記事で、内村は再び訴えた。
「余はキリスト教の信者である。しかもその伝道師である。そうしてキリスト教は、殺すなかれ、汝の敵を愛せよと教うるものである。しかるに、もしかかる教えを信ずる余にして開戦論を主張するがごときことあれば、これは余が自己を欺くことである」
陸軍は児玉源太郎に最後の望みを託した。内務大臣である児玉は、国政のかじ取りを担い、戦地に赴く立場ではない。それを戦地に引き戻す人事的な降格を求めねばならない。桂は申し訳ない人事になるが戦争の指揮をとってくれないか、と児玉に申し入れた。児玉は内務大臣を辞し、陸軍史上最初にして最後の降格人事を受け入れた。参謀次長として陣頭に立つ決心をした。参謀総長には薩摩閥の元老大山巌が就いた。
明治36年10月9日、内村は「日露戦争絶対反対」を主張し、幸徳秋水、堺利彦らの論客とともに「万朝報」を去る。内村は社長黒岩に宛てた辞表で言う。
「小生は日露開戦に同意することを以て日本国の滅亡に同意することと確信致し候」
明治37年(1904)2月4日、天皇の御前会議に伊藤、山県、大山、松方、井上の5元老と、桂首相、小村外相、曾彌蔵相、山本海相、寺内陸相ら閣僚が集められ開戦の断が下された。原敬は「少数の論者を除くほかは、内心戦争を好まずして、しかして実際には戦争の日々に近寄るもののごとし」と2月5日の日記に記した。さらに「一般国民、なかんずく実業者は最も戦争を厭うも、表面これを唱うる勇気なし。かくのごとき次第にて国民心ならずも戦争に馴致(じゅんち、慣らされること)せしものなり」(「日記」2月11日付)と書いた。日露戦争は総兵力109万人、戦費19億8000万円を費やし、8万7000人の戦死者を出した。未曾有(みぞう)の犠牲を強いた消耗戦であった。
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-













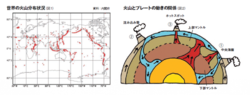











![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方