「言霊」の国で議論は形骸化しリスクは隠される
第87回:情報環境の激変で顕在化するリスク(8)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2025/05/17
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

前稿にて少し触れた「言霊」の弊害について、もう少し考えておく。「言霊」が日本の歴史・文化に脈々と根付く風土「和」と対極になり得ることは興味深い。そう筆者は感じている。
「和」とは、古くは十七条憲法の第一条に示された「和を以って貴しと為し」であり、五箇条の御誓文の第一条「広く会議を興し、万機公論に決すべし」に示されるように、独断で決めずに話し合って決めるべきだという教えにも通じるものである。

話し合うためには言葉が必要であり、その言葉に制限があっては、本来話し合いは成立しない。それはそうだろう。「言霊」を前提に、実現しては困ることを話題にできなければ、健全な話し合いにはならない。タブーを許し、そのことを避けた話し合いは、形だけ整えるだけの形骸化したものになるだろう。
平安貴族が治安維持機能を忌避し、都が荒廃していったのは、まさにこの弊害と考えられる。本来の話し合いとは、本質的な課題に皆の知恵を結集させるというものであるはずだ。
この弊害は歴史だけでなく、現代の我々にも大きく横たわっている。具体的な事例の一つが原子力発電問題だろう。
原子力発電に関しては、根強い反対派が存在する。一方で、最近は少々状況が変わってはいるが、それでも安全神話も存在する。この両者による話し合いは論理的に成立し得ない。

筆者自身は現実的な原発推進論者ではあるが、それでも安全神話を元にした、リスクを語らない姿勢には断固として異を唱える。確かに、リスクを語った瞬間に揚げ足を取られ、感情的な攻撃に晒される可能性は高い。しかし、それでもリスクを語らずに安全を語れるわけがなく、避けて通ることはあり得ない。
原発も他のリスクと同様に発生確率と発生時のダメージの大きさの積でリスクを評価するべきであるが、原発事故が起きた際のダメージは極大になるのは誰でも理解できるだろうから、発生確率を極小化するリスク対策が重要になる。それは、リスク発生要因を正面から議論しなければできるはずがない。
断っておくが、ここでリスク事象を語ったからといって、それがリスクを顕在化させる要因には決してならない。
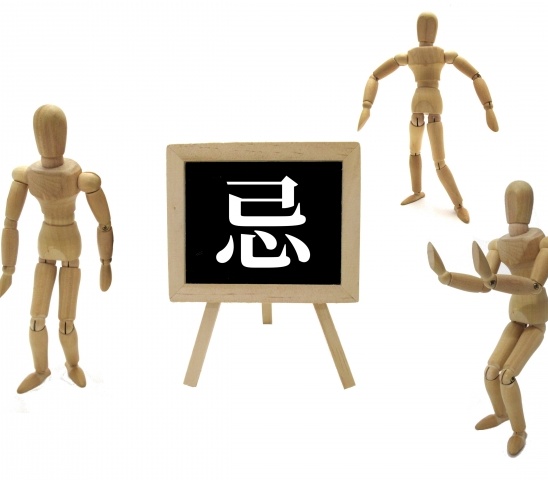
繰り返しになるが、リスク想定にタブーは禁物であり、想定外もあるべきではない。世の中で想定外といって逃げるのは、その内実は、考えられる事象を上まわるものに限り受容される領域のはずである。受容とは、そのリスクが万が一発生した場合は受け入れる想定との意味だが、こういうとゼロリスクを前面に押し立てた感情的な攻撃も激しくなるかもしれない。困ったことである。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事





今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12


中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方