2014/01/06
セミナー・イベント
※開催終了

災害時に、人命を守り、その影響を最小限に抑えるためには、組織が単独で、あるいは他の関係機関部局と協同して、効率的な危機対応を実施できるようにするための「指揮調整」という機能が必要になる。指揮調整に必要な体制 、プロセス 、 そして、その実現に必要な資源は何か。本セミナーでは、TIEMS日本支部の代表理事である京都大学防災研究所の林春男教授が危機対応の国際規格であるISO22320における「指揮・調整」について、東日本大震災で岩手県防災危機管理監として災害対応の陣頭指揮を執った岩手大学地域防災研究センター教授の越野修三氏が3.11における岩手県の災害対応と指揮調整の実際について、また株式会社セブン&アイHLDGS総務部グループ渉外シニアオフィサーの成田庄二氏が、民間企業のBCPにおける指揮調整についてそれぞれ解説する。
※本セミナーの参加者は国際危機管理学会日本支部の会員に限定しております。会員になられていない方は、本セミナー申込みとは別に、会員登録をしてください(入会費・年会費無料)
会員申込みはこちらから⇒国際危機管理学会日本支部
開催概要
■ 日時:2014年1月24日(金)
13:00~17:00 第5回パブリックカンファレンス (受付開始 12:30~)
17:30~ 交流会
■参加費:無料 (交流会参加費は5000円)
■資料代:2000円(任意)
※資料は有料とさせていただきます。ご理解下さいますようお願いいたします。
■会場:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター9F ホール9A
(〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地)
http://tkpichigaya.net/about.shtml
※毎回、会場が異なり申し訳ございません。お間違えのないようお気を付けください。
■定員150人
※申し込み多数となることが予想されるため、キャンセルされる場合は、必ずご一報下さい。
第5回パブリックカンファレンス プログラム
|
13:00~13:50 |
ISO22320における指揮調整について 京都大学防災研究所教授 林春男氏 |
 |
|
13:50~14:40 |
3.11岩手県における災害対応と指揮調整の実際 岩手大学地域防災研究センター教授 (元岩手県防災危機管理監) 越野修三氏 |
 |
|
14:40~15:30 |
3.11の対応とBCPにおける調整の重要性 ~もうひとつのライフラインの構築に向けて~ 株式会社セブン&アイHLDGS総務部 |
 |
|
15:30~15:50 |
休憩 | |
|
15:50~17:00 |
パネルディスカッション コーディネーター:リスク対策.com編集長 中澤幸介 パネリスト:京都大学防災研究所教授 林春男氏 岩手大学地域防災研究センター教授 株式会社セブン&アイHLDGS総務部 株式会社藤縄地震研究所取締役会長 藤縄幸雄氏 |
【お問合せ】
TIEMS日本支部広報事務局
新建新聞社 リスク対策.com編集部
電話 :03-3556-5525
メール:risk-t@shinkenpress.co.jp
セミナー・イベントの他の記事
おすすめ記事





















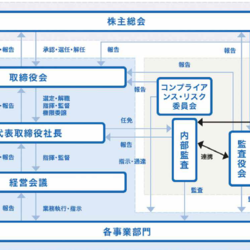













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方