2019/08/26
安心、それが最大の敵だ

ファン・ドールンと安積疏水の成功
大久保の非業の死後を継いだ内務卿伊藤博文は福島県の安積疏水計画について大久保の遺志を最大限尊重し、伊藤の後を受けて内務卿となった松方正義に計画のすべてを担当させた。松方はファン・ドールンに疏水の設計を命じ、これを受けてドールンは明治11年1月現地郡山に入り調査報告を受けた。翌12年(1879)1月5日、彼は設計を完了して、詳細な計画書「猪苗代湖疏水工事調査復命書」(政府翻訳官熱海貞爾訳)を、内務省土木局長石井省一郎に提出した。同年10月、工事はこの計画書に基づいて早くも開始された。
安積疎水計画は、ファン・ドールンの日本での代表的業績のひとつである。その原点が「復命書」である。この猪苗代湖・疎水工事計画書は四章からなり、いずれも施設計画の基本的な緒元を計算した根拠を示している。この内、後の農業水利計画にひとつの標準的な手法として採用された所要水量算定に注目しなければならない。この所要水量算定法について、彼は第一章「所要ノ水量ヲ定ム事」で、水田一町の所要水量を、世界各地(オランダ領東インド、イギリス領インド、エジプト、イタリア、スペイン)の実例をあげて比較検討している。所要水量は地質によって多寡があると述べ、良好な粘土質の水田は少なく、砂質の水田、ことに下層に砂礫化があると多量の水が必要だと指摘している。
しかし彼は、この基本式を元に安積原野で数値を測定して計画を作っている訳ではない。安積原野での所要水量の算定考え方をまとめると次の4点である。第1に、緯度を他国と比べている。これは気温についての比較である。第2に、スペインでは夏の間全く雨が降らないのに対して、ここでは5~6月は少ないながらも定期的に雨が降り、8月も湿潤のため蒸発散が少ないとしている。第3に、福島県の水田の土質は、良好の粘土からなっていて浸透量は多くないとしている。第4に、日本の水田では、高いところの田で使われた水がまた低いところで用いられるとの反復利用が指摘され、以上を総合するとスペインで用いられている数値(毎町毎秒時尺立方七勺)で十分としている。
彼が世界各地の水田用水量のデータを保有していたことに注目したい。オランダの植民地経営にとって、水田灌漑に関する技術とデータの蓄積は特に重視されたに違いない。これらの貴重な情報をもとに、ドールンは安積原野の所要水量を見積もったのである。彼の現地調査にあたっては、奈良原繁、南一郎平ら政府官僚(事務官)の「抜群ナル助」があったと彼自身も感謝している。日本人技術者による現地調査が相当なところまで進められていたと思われる。
◇
政府は、明治12年10月、ドールンの設計に従って安積疏水事業を起工し3年後の明治15年(1882)10月に完了した。水路の幹線52キロ、水路78キロの一大工事であり、延べ85万人が動員された。11月1日に郡山・開成山大神宮で通水式が盛大に挙行された。右大臣岩倉具視ら政府要人が出席し、国家的大プロジェクトの成就を祝った。当初「安積三万石」と見下されていたコメ生産額は昭和15年(1940)には「20万石」にも達した。
昭和6年(1931)10月14日、ドールンの功績を讃えて猪苗代湖の北西湖畔の十六橋・橋頭に、高さ8尺(2メートル40センチ強)のファン・ドールン像が建立された。数千人の参会者が見守る中、銅像の除幕式が行われた。銅像の考案製作者は本山白雲で、銅像の背面には文学博士竹越与三郎(三叉)の撰による碑文が刻まれている。
「安積碑文」の一部を引用する(原文カタカナ。現代語表記とし句読点を適宜付す)。
「人生は短きも事業は長きこと実にファン・ドールン君に於いて之を見る。君名はコルネリス・ヨハンネス、千八百三十七年和蘭ハル邑(むら)に於いて牧師の家に生れ、完全なる技術教育を受け、幾多の職務に於いて実験を積み令名あり。維新の後、政府全力を殖産興業、治水・築港に注ぐ。明治五年君聘せられて内務省土木局の長工師に任じ数人の部下を率えて来朝し、利根川・信濃川・淀川等の改修、大阪・仙台湾等の築港に関して計画を立て、工事を監督して大いに成績を挙げ、治水事業の基礎を確立す」
「九年内務卿大久保利通、福島県安積地方一帯の原野に猪苗代湖の水を澆(そそ)ぎて新田を起し、失業士族衣食の道を開かんと欲し其事業を君に命ず。君親しく山野を跋(ふ)み藪沢を渉(わた)り、水量を測り、風雨に由る変化を察し、疎水墾田の実行を得べきを見、設計拝命書を呈す。政府即ち其計画に基き十二年十月工を起し、十五年十月完成し東北を初め数県の士族を移して耕食せしむ。之より地方の生意勃然として盛んに政治上の妖気亦為に薄らぐ。唯君が十三年職を辞して本国に還り、親しく其完成を見ざりしを遺憾とするのみ。君人品醇厚にして懇切、深く日本を愛して後来のために謀る所多きを以て、人皆之を愛惜す。朝廷君が積年の功に賞して勲四等に叙し、旭日小綬章を授く。君終生婚せず、千九百六年アムステルダムに没す」
「安積疎水普通水利組合及び土木学会の賛同を得て、茲に君の銅像を建つ。像は遠岫(えんしゅう)近樹湖光島影と相点綴(てんてい)して一幅の書図を作す。君の流風之より山の如く高く水の如く長からん
昭和六年十月 貴族院議員正四位勲二等 竹越与三郎撰 正三位勲三等 杉渓言長書」
安積疏水は、会津盆地における既得水利権を侵さないように特に留意している。これは特筆に値する。湖水の水位変化が長年にわたって観測された結果、大正4年(1915)、猪苗代湖水力発電の事業が実現した。猪苗代第一発電所から遠く東京都心までの220キロに115キロボルトの当時世界でも最高の電圧による長距離送電が行われた。日本の電力開発史上画期的な成果といえる。
参考文献:拙文「ファン・ドールン研究」、「日蘭学会会誌」(第9巻、第2号、高橋裕論文)、筑波大学附属図書館資料。
(つづく)
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-











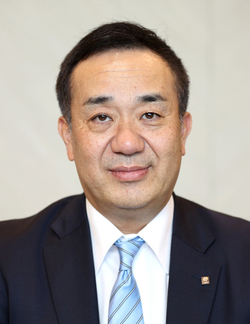















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方