2019/11/20
危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識
意思決定に使える豊富な情報を生かす
気象情報や防災情報を利用して自ら判断できる力を磨いていくのが最大の近道です。そもそも避難勧告や河川の水位に関する情報などは防災情報や気象情報の中のごく一部です。限られた情報だけを使って意思決定をしようとしているところに実は問題があります。
避難勧告や水位に関する情報など以外にも自ら危険性を判断するために使うことができる情報は次のようにいくつもあります。
・気象ニュースや気象庁の記者発表などで伝えられる雨量の見込み
・これまでに降った雨の量や今後の雨の量に関する情報
・気象レーダーに映る雨雲の様子や今後の雨域の見込み
・河川水位の上昇具合
・内水氾濫や中小河川の外水氾濫が起こる可能性を示す情報
・土砂災害が起こる可能性を示す情報
・暴風のピークに関する情報 など
これらの情報の多くは気象庁のホームページなどを利用して入手することができます。ただし、受け身的に情報を待つのではなく、自分から積極的に取りに行くという主体性が必須です。
危険性を把握するための情報として例に挙げた情報の中には意思決定や体制判断の基準に組み込むことが難しい情報もあるかもしれません。読み取るのに多少の習熟がいる情報もあるでしょう。しかし、だからと言って自ら情報にアクセスすることなく意思決定をするのは目隠しをしながら判断するようなものでお勧めできません。
さまざまな気象情報を通じて迫り来る危険を察知できるようになると、避難勧告や警報などといった「伝えられた情報」のみをただ使う場合に比べて、大局的な判断や、確信を持った判断ができるようになります。危機管理の担当者として、ぜひそうしたレベルで情報を使ってもらいたいと願っています。
まとめ:災害の危険性を見抜くために積極的・能動的に気象情報を使おう
今回の記事ではまずは気象情報との向き合い方についてテーマにしてきました。ぜひ覚えておいてほしいことは、「伝えられる情報を使うだけが防災対策ではない」ということです。受け身的に情報を利用する限り、手持ちの判断材料が非常に限られた中で意思決定をしなければならない状況に自らを追い込んでしまいます。また、情報の出し手側の成否にあなたの対応も引きずられてしまいます。気象情報や防災情報を積極的・能動的に使っていくことで、このような制約をぜひ打ち破っていってください。
気象情報を積極的・能動的に使うための具体的な方法については今後の記事の中で随時ご紹介していきます。
(了)
危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識の他の記事
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/13
-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-















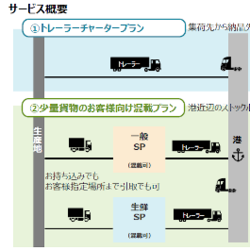











![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方