BCPの実効性を阻害する要因は内部にある
第1回:低いリスク意識とITリテラシー

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
2020/10/01
企業を変えるBCP

林田 朋之
北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。
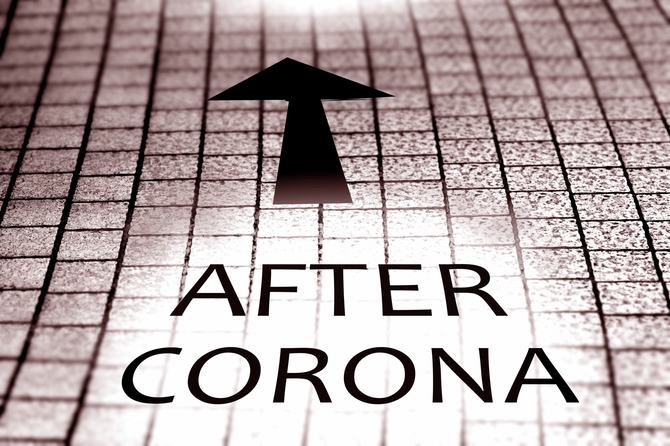
昨年までのBCP(事業継続計画)のテーマであった首都直下地震や南海トラフ地震、あるいは台風や大雨等の気象災害への対応。ここへきてやっと、担当者はコロナ以外の危機管理作業ができる状況になってきたのではないでしょうか。
ここ数年、筆者が行う講演会やセミナー、またクライアントとの雑談において、BCP策定(策定中)企業が抱えるある特徴的なキーワードが浮かび上がってきました。それは「実効性」への不安です。
企業によって経営者の考え方や現場の考え方、投下できる予算、社内文化などはさまざまですが、共通のキーワードとして「実効性」への課題があるように思います。
例えば、大企業に多く見られるケースはこうです。
BCPはかなり以前に策定したマニュアル等が陳腐化、さらに担当者が人事異動になって社内に危機管理のプロがいない、訓練も長い間実施していないためにいざという時に機能するかどうか…そもそも経営陣の危機感と現場の感覚がズレていて、対応策自体に不安がある…。
中堅企業は、こんな悩みはないでしょうか。
十分な危機管理対応予算が付けられない、帰宅困難者を3日間オフィスに泊めておくなど不可能では? そもそも自社のBCPが他社と比べて見劣りしていないか…。
中小企業では、こうしたケースが見られます。
助成金などの補助を受けられるにも関わらず、経営陣や管理職にBCPや危機管理の本質的な議論がない、助成金の範囲でモノを買うことだけの危機管理、いわゆる備蓄品の購入でしかBCPを考えていない…。
企業の危機管理担当者によって悩みはまちまちでありながら、いずれも実効性に対しての不安を口にされています。
企業を変えるBCPの他の記事
おすすめ記事


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方