2015/03/25
誌面情報 vol48
IT×災害情報発信チーム
情報通信プロボノプラットホームがまとめた「東日本大震災情報行動調査報告書」によると、3.11で最も活用されたソーシャルメディアはTwitter。輻そうにより携帯電話などの通話が困難になるなか、友人や家族の安否をTwitterで確認した読者も多いのではないだろうか。昨年、埼玉県和光市はTwitterを活用した防災訓練を実施し、その直後に大雨が発生。市民から自主的に発信された情報で、市内の被害情報を共有した。IT×災害情報発信チームは、災害時の自治体や個人におけるITを活用した迅速な情報把握、伝達、発信による防災・減災を目指す。

IT×災害情報発信チームも、IT×災害会議から生まれた活動の1つだ。メンバーの1人である小和田香氏は、大手通信会社に勤務しながら、国家公務員非常勤、NPO理事などさまざまな顔を持つ。

小和田氏は「数年前に難治性の病気にかかり、会社を休職していた時に、定年後もやりたい仕事がないことに気がついた。そのころからソーシャルメディアを活用し、地域を元気にする活動をしようと考えた」と話す。
当時からソーシャルメディアを活用した地域のインターネットテレビ番組のプロデュースなどを行っていたが、東日本大震災を機に「助けあいジャパン」の立ち上げに関わるようになり、情報発信チームリーダー、理事などを歴任した。「助けあいジャパン」は官民連携プロジェクトであることが特徴。小和田氏は、「助けあい-」のホームページ上で、当時新設された内閣官房震災ボランティア連携室からの情報や、各省庁がバラバラに発信していた支援情報を分かりやすく整理してホームページに掲載するなど、情報発信による被災地支援に携わった。
小和田氏は「内閣官房ボランティア連携推進室は当時ホームページがなかった。さらに、国主体の更新では、公平性などに慎重になるため機動力に欠ける。官民連携により、スピードと自由度と分かりやすさを心掛けた」と当時を振り返る。
支援情報の偏りが課題に
「助けあい-」のホームページには、国からの情報だけでなく、当初はマスメディアなどの情報を選別して掲載していた。しかし情報を発信するうちに、「声が大きい情報」から取り上げており、支援が偏っていることに気付く。報道でも、例えば宮城県石巻市の避難所の情報は多数放送されても、隣の山元町の避難所は放映が少ない。サーバの流出などにより、自治体で情報発信機能を失っている場所もあることに気付いた。
「本当は、報道機関は各地に分散して取材して欲しいくらいだった」(小和田氏)
小和田氏らは情報の偏りによる支援の偏りをなくすため、それぞれの町の状況を一覧化するページを開設。被災地情報を求め、各市町村ごとにボランティアの募集情報や、そこで支援活動をしている団体や個人のブログをリンクした。
小和田氏は「何も発信できていないところが、本当に支援が必要な場合もある。特に発災初期に大切なのは、目に見える情報だけではなく、全体として何が起こっていて、支援の優先順位が高い場所が分かる、情報のトリアージが必要だった」と話す。これらの反省が、現在のIT×災害情報発信チームの取り組みにつながっていく。
Twitterを全県、全市町村に
冒頭既述したように、災害時に最も活用されたソーシャルメディアはTwitterだと言われている。東日本大震災では、発生の24分後の15:10には、消防庁が「災害情報タイムライン」というTwitterの災害時運用を開始。その後、総理官邸をはじめ、多くの官庁もTwitterでの情報発信を開始した。官庁や自治体の場合、既存のホームページでは所定の手続きを経ないとアップすることができないため、リアルタイムの情報発信には不向きだ。さらにアクセスが集中した場合にはサーバが耐えられないという問題点もあった。Twitterは現在1秒間に14万アクセスでも耐えられるサーバを保有しているという。
2014年8月、IT×災害情報発信チームは自治体のTwitter使用状況を調査した。集計結果によると、全国47都道府県のうち、公式Twitterを導入していたのは35、全国1741市町村では28%の491。東京都では80%、中国四国地方は20%以下と、地域に差があることも確認された。
小和田氏は「災害時の情報共有のため、市民と連携した自治体のTwitter活用が不可欠。さらにコストもほとんどかからない。まだ導入していない自治体の担当者には、ぜひTwitterの活用を検討して欲しい」としている。
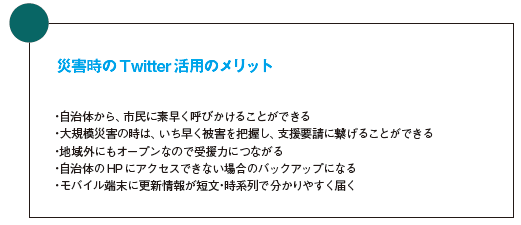
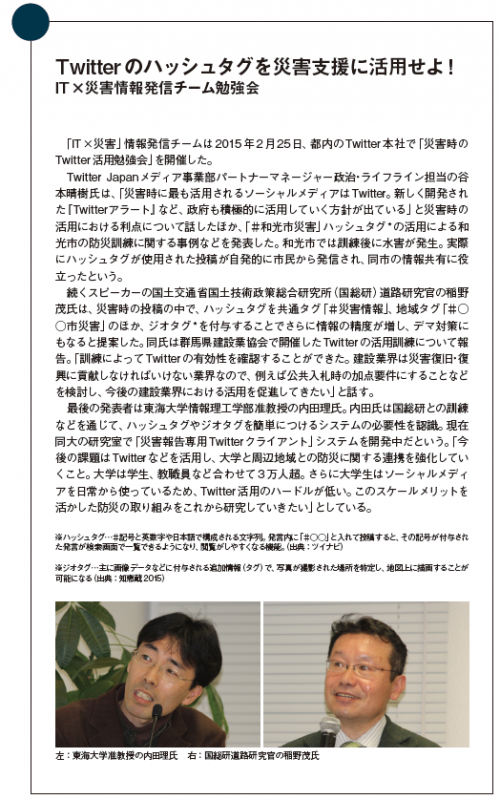
誌面情報 vol48の他の記事
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方