2019/11/15
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
対策4 公務員への要求が少ない
これもハリケーンやストーム対策というべきものではないのですが、以前イタリアの避難所を書いた際、こんな事も書きました。
■イタリアの避難所ですぐ届くもの3つって何でしょう?アルファ米とかお弁当とかじゃないですよ!なんと!?
https://www.risktaisaku.com/articles/-/6286
イタリアでは、被災した地域の公務員は、被災業務をしないで通常業務を実施します。被災業務をするのは支援に入った人たちです。被災地の公務員が泊まり込みで業務にあたるなんて、人権上、問題があるのでありません。被災地の公務員が家族旅行に行ったとしても(行かない人がほとんどですが)誰も責めたりしないということでした。災害時の対応というのではないのですが、PEIでも公務員である教師の普段のしばりが少ないのだなと思った事例がこれです。

有料のアスレチックやジップスライドが小学校の横にあるのです。小学生にも大人気のこの場所、経営者は小学校の体育の先生です。先生の副業は禁じられていないので、現役の先生が経営者でも誰も何も言わないし、気にしていません。公務員や教員がひとりの人として人生を楽しむことを誰もが応援している雰囲気を感じます。ちなみに余談ですが、PEIでは先生と相性が悪いからと生徒や保護者が先生を変えてもらうことは普通にあるそうで、クレーマー扱いされるわけではないようです。相性がよくないためにお互いが大変になるより、もっと相性がよい人に先生になってもらうことは、お互いにとっても幸せなことと考えられているようです。
対策5 自分で考えて行動すること 率先避難者になること

これも対策という訳ではありませんが、もしも、避難しなければならない事態になった際、隣の人が逃げてないから逃げ遅れるなんてことはPEIではなさそうだと思っています。というのも、子どもたちは教育の中で自分で考えて行動するよう、幼少期から徹底されているからです。息子が2歳の時PEIを訪れたのですが、2歳の子連れ親子と一緒に食事に行きました。何を食べると聞かれ、その子と同じ食事を頼んだ息子に、その子はすかさず「NO COPY!」と言いました。常に自分の意見を求められているってことですよね。大事なことだなと思いました。

そしてもうひとつ、災害時、たくさん情報を得てもなかなか避難を決断できないという問題があります。これも自分で決断することに慣れていないという幼少期の教育の問題もあるように思っています。例えば、おもちゃの取り合いがあったとします。日本のママたちから子育てあるあるとして、みなさんに共感してもらえるのが、「貸していいよ問題」です。お友達におもちゃを「貸して」と言われれば、国内で、子どもが答えるべき選択肢は「いいよ」一択です。「貸して」と言われれば「いいよ」と言う練習さえします。有名なトロッコ問題よりも選択肢がないです。で、これをPEIでは親がどんなセリフを言っていたかというと「Noの場合は、ちゃんとNoと伝えなさい。そのかわり相手を説得しなさい」というものでした。自分の意見を言っていいんですね。その代わり、自分の意見には責任が伴うということです。PEIで親の全員が子どもにこう言うわけではないですが、自分の意見を述べる訓練をしておらず、周りに合わせるのを良しとする日本の幼児教育からの積み重ねの中にあっては、責任が伴う決断をするのは、ハードルが高すぎることかもしれないと思います。
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事
おすすめ記事
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/27
-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26
-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23
-

-

-











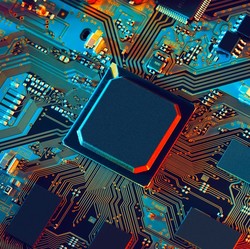













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方