AIで淘汰される職業の最有力候補
第46回:IT後進国から脱却できるのか(6)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2023/08/30
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
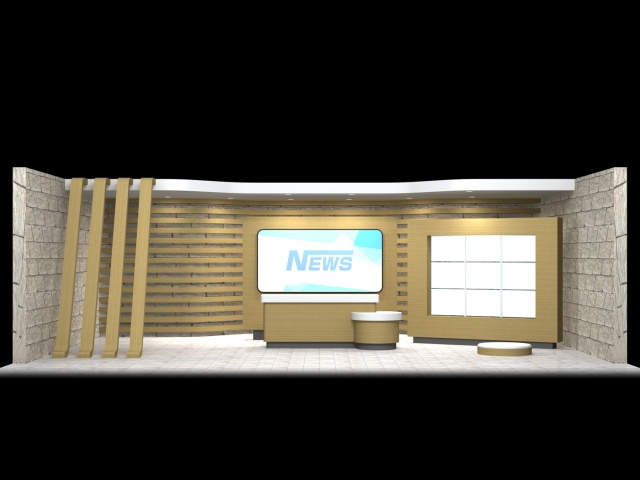
AIが拡大普及することで多くの人の職が奪われると危機感を煽る論調があるが、筆者はこの説に同意しない。
これまでも、機械化やロボット技術、センシング技術などの進展で効率化が進み、人の労働負荷は大幅に軽減された。同時に低コスト化が図られ、サービス品質も向上し、産業拡大につながっている。それでも労働力が余剰になるどころか、労働力不足の状況にあり、外国人労働者に頼る方向の政策が検討されているのが現実である。
労働力の余剰や過不足は、結局のところ経済原理に左右され、失業率という指標で示されるものと考えられる。資本主義自由社会において科学技術の発展は、確かにそれまでの人間の役割を減少させるかもしれないが、それ以上に新たな労働分野を生み出すのである。

つまりAIが拡大普及し、便利になり、価値観も変容することで、イノベーションが生み出され、市場としてはむしろ拡大の原動力になり、雇用が生み出されると考えるべきだろう。ただし注意すべきは、かつてのベストセラー『チーズはどこへ消えた』のメッセージに込められたように、環境変化へ適合できず、井の中の蛙になってしまうと、淘汰される側になってしまうことだ。
では、その危険性はどこにあるのだろう。筆者の個人的感覚で申し訳ないが、その最有力はメディア業界、情報を取り扱う業界ではないだろうかと危惧し、警鐘をならすべきと考えている。
もちろん、私ごときが指摘するリスクなどはすでに認識されており、対処しているかもしれない。それならそれで単なる老婆心となるだけなので、社会にとってはむしろよい方向である。筆者の懸念など笑い飛ばしていただいてよい。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事


中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05





発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方