2013/08/06
防災・危機管理ニュース
4)海外勤務・海外出張については、定期航空便等の運行停止の可能性を踏まえる
海外勤務・海外出張する従業員等および家族については、次の点を押さえることとしている。
●発生国への海外出張については、やむを得ない場合を除き、中止する
●感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運行停止により帰国が困難となる可能性があること、感染しても現地で十分な医療を受けられなくなる可能性があることにかんがみ、発生国以外の海外出張も原則中止・延期することも含めて検討する
●海外勤務者・海外出張者がいる企業は、情報収集に努め、これら従業員の人員計画(現地勤務を継続させるか、いつどのように帰国させるか)を事前に決めておく
●即座に全員を帰国させる航空機を確保することが難しいことも想定されるため、安全にとどまるための方法についても検討しておく(海外発生期において、新型インフルエンザ等の国内への侵入を防止するため、発生地域から来航または発航する航空機・旅客船の運航制限の要請が行われることがある)
4.企業として考えておくべきこと
特措法、行動計画、そしてガイドラインは、新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命および健康を保護するとともに、国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小になることを目指して作られたものである。しかしその一方で企業として、今後起こり得る新型インフルエンザ、そして新たな感染症の流行に備えて、考えておくべきことは従来と大きく変わらない。
(1)自社の感染防止策とBCPを、もう一度見直す
新たに施行された特措法には、緊急事態宣言を含め、企業が新型インフルエンザ等対策を進めるにあたり、十分に理解しておくべき項目が含まれている。また行動計画や改定されるガイドラインについても同様である。これを機会に自社の感染防止策とBCPについて、もう一度見直し、その内容を向上させることが求められる。
(2)最悪のシナリオも想定する
2009年に流行した「インフルエンザ(H1N1)2009」の病原性は季節性インフルエンザ並であったが、今後、致死率が高い鳥由来型の新型インフルエンザが発生する可能性がなくなったわけではない。企業が、病原性の低い新型インフルエンザ対策だけを前提としていたのでは、足をすくわれる可能性がある。
想定される被害については、まず最悪のシナリオ、つまり懸念されている病原性の高い新型インフルエンザも想定して、対策やマニュアルを策定する必要がある。その上で、実際の流行においてはその状況に応じて柔軟に、そして適切に運用することが望ましい。
(3)リスクコミュニケーションを十分に行う
2009年の流行で、企業や社員の新型インフルエンザに対する認知度はあがったものの、4年が経過した現在、正しい情報や危機感が維持されているかどうかは疑問である。むしろ、「再び新型インフルエンザが流行しても被害は大きくない」という油断や、手洗い・咳エチケットなどが実践されていないという状況が起こっているのではないだろうか。
また特措法において、登録事業者は、あらかじめ特定接種対象者数を検討し登録することになっているが、その際、ワクチンについては副反応のおそれがあること、効果が未確定であるため接種後にも感染防止策を講じなくてはならないこと、また発生状況に応じて特定接種が行われない場合があることなど、事前に従業員に説明し同意を得ておくことも必要となる。企業は従業員に対して、これら国の新型インフルエンザ等対策の内容を含め、様々な情報提供を行うとともに、自社の感染防止策やBCPについて、あらためて理解を求めることも必要であろう。
■参考文献・資料等
1)世界保健機関(WHO)H.P.
2)厚生労働省H.P.
3)内閣官房H.P.
4)「新型インフルエンザ対策行動計画」(平成23年9月20日)
5)「新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年2月17日)
6)「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年5月11日公布)
7)「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(平成25年6月7日)
8)「新型インフルエンザ等対策ガイドライン(案)」(新型インフルエンザ等有識者会議(第9回)配布資料)
※注)
1)指定公共機関
独立行政法人等の公共的機関および医療、医薬品または医療機器の製造または販売、電気またはガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの
2)登録事業者
医療提供業務または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって、厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの。
【お問い合わせ】
株式会社インターリスク総研
TEL 03-5296-8911(代表)
※ 本稿は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。
転載元:株式会社インターリスク総研 RMFOCUS Vol.46
- keyword
- 感染症・労働災害
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/23
-

-

-

-

-

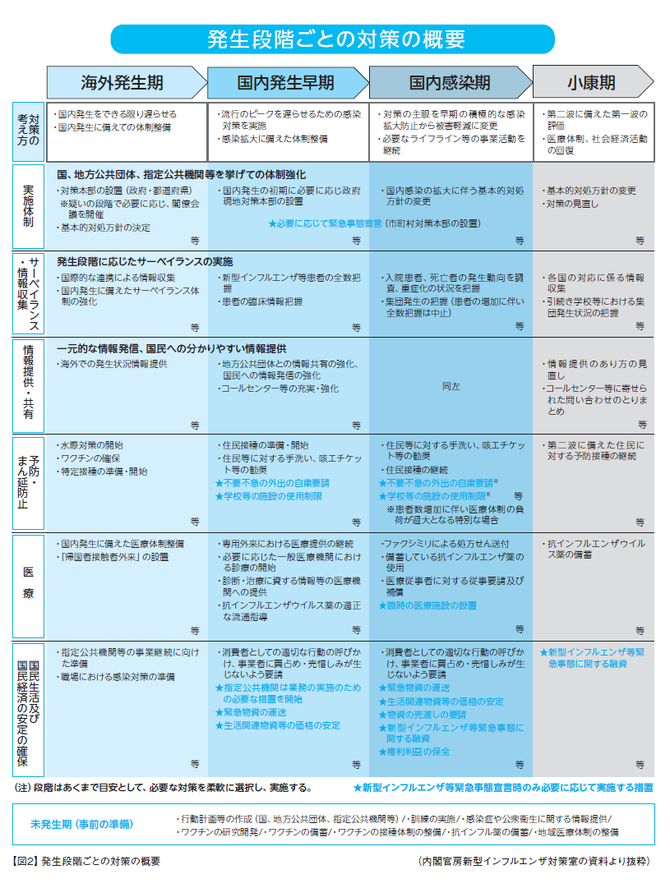


























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方