第6回 賃貸不動産所有者(オーナー)の事業継続

小山 和博
外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。
2016/06/17
業種別BCPのあり方

小山 和博
外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。
編集部注:「リスク対策.com」本誌2013年11月25日号(Vol.40)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年6月17日)
前回は、賃貸不動産管理業の事業継続計画について検討を行ったが、ある方から質問をいただいた。「賃貸不動産管理業とオーナーの間の賃貸不動産管理契約には、物件の滅失により契約は終了する旨の条項が含まれていることが多い。震災により物件が滅失した場合でも賃貸不動産管理業に一定のサービスを期待することはできるのか」というものである。
このような条項が含まれていることが多いかどうかについて、筆者は参考とすべき資料を持ち合わせないが、そのような契約になっていれば、契約は終了することになるだろう。
このような事情を考慮すると、オーナー自身が自らの不動産事業を継続するための方策を検討しておかなければならない。そこで、今回は、視点を変えて、オーナー自身の事業継続について検討する。なお、オフィスビルもしくは賃貸住宅(貸家およびマンション)を個人所有している事例が多いことから、この2つを対象とする。また、問題となった事例が多いことから、今回の想定リスクは地震とする。
建屋の耐震性確保がオーナーの事業継続の基礎となる
不動産賃貸借契約の趣旨に立ちかえって、オーナーの義務を改めて考えると、その中核となるのが「建物や土地を使用収益させる義務」(民法601条)である。そして、この建物には、瑕疵がないことが求められる(工作物責任、民法717条)。よって、使用収益させる建屋に瑕疵がないかを確認しておくことが非常に重要である。これを可能にするのが、いわゆる「耐震診断」である。特に耐震基準が改正された昭和56年5月31日以前に建築確認が行われた建屋については、耐震診断を実施することを強く勧める。
また、耐震診断の結果に応じた補強措置もしくは建て替えについては、費用、効果、リスクのバランスをよく考慮しなければならない重要な判断になる。古い建屋を補強するよりも、建替えに踏み切る方が不動産経営上有利な場面もあるだろう。必要に応じて、賃貸不動産管理業、弁護士、建築士、税理士、保険代理店といった専門家のアドバイスを受け、判断することを勧める。
耐震診断を実施し、その結果、瑕疵がないことを証明できれば、以下に紹介するような損害賠償請求リスクは十分回避できる。そもそも適切な耐震補強を行っていれば、建屋が地震により倒壊する可能性は相当程度まで下げることができる。リスクマネジメントの観点から目指すべき姿である「そもそも事件・事故を発生させないこと」を実現することができる。
耐震性確保のコスト
具体的な耐震診断の結果、耐震補強措置が必要になれば、その場合の費用は木造アパートでも数百万に上ることがある。また、マンションやビジネス用の雑居ビルであれば、耐震診断だけでもその費用は数百万から一千万円超になることがある。この費用がオーナーの耐震診断への取り組み意欲を大きく削いでいることは事実である。
東京都の都市整備局が2013年5月に公表した「マンション実態調査結果」によれば、東京都内の旧耐震基準により建築されたマンションのうち、耐震診断を行っているマンションは、分譲で全体の17.1%、賃貸マンションでは全体の6.8%にとどまる。
この調査で、耐震診断を実施しない理由として挙げられたのは表1の通りであった。
この調査では、旧耐震基準で建築された分譲マンションの耐震診断に反対する意見についても調査を行っている。その中で最も多い意見は「資産価値が低下する」であった。
以前、筆者が賃貸不動産オーナーの集まりに出講した際、「もともと古い建物であれば、もらっている家賃も安い。地震があれば壊れるリスク込みでお互い賃貸借している。オーナーからすれば、耐震診断は百害あって一利なしだ」との指摘を受けた。不動産賃貸物件管理業の方からもオーナーの意識について同様の話をいただくことがある。
建物に瑕疵があることによるリスク
民法717条は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」として、所有者の無過失責任を定めている(工作物責任)。この責任は建物に瑕疵があれば成立し、過失の有無は問われない。「寝た子を起こすな」という議論は結局のところ誰にとっても不本意な事態を引き起こしかねない。
神戸地裁平成11年9月20日判決は、昭和39年に建築され、もともと十分な耐震性を有していなかった賃貸マンションが阪神・淡路大震災により震度7の揺れに見舞われ、一階部分が押しつぶされ、住人が死亡した事例について、マンションの建屋自体の瑕疵を認め、賃貸人・所有者に対して工作物責任を認めた。賠償額は、原告7名に対して合計1億2900万円である。この判決では、「建物の設置の瑕疵と想定外の自然力※とが競合して損害発生の原因となっている場合は、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨からすれば、損害賠償額の算定に当たって、右自然力※の損害発生への寄与度を割合的に斟酌するのが相当である」として、全損害額のうち5割の賠償を命じている。
※判決文中の自然力とはいずれも地震動を指す
また、この判決では、「仲介業者は建物の構造上の安全性については建築士のような専門的知識を有するものではないから、一般に、仲介業者は仲介契約上あるいは信義則(※)上も建物の構造上の安全性については安全性を疑うべき特段の事情が存在しない限り調査する義務まで負担しているものではない」として、不動産仲介業者の責任を否定している。つまり、こ の裁判例の趣旨に従えば、もともと瑕疵がある建屋を貸していて、被害が生じた場合、責任はオーナーだけにあることになる。
※信義則とは、人は社会共同生活の一員として,ある一定の事情のもとでは相手方から期待される信頼を裏切ることのないように,誠意を持って行動すべきであるとする民法の基本原則をいう。民法1条2項に定められている。
さらに、神戸地裁平成10年6月16日判決は、昭和39年6月に建築され、度の増築が行われたホテルにおいて、2近隣の木造建屋に倒壊などの被害が出ていないにもかかわらず、昭和44年に増築された建屋の4階~6階で天井が崩落し、下敷きとなって2名が死亡した事例について、オーナーに約1億円の損害賠償を命じた。オーナーは不可抗力を主張したが、判決は「被災増床以外の本件建物や近隣の古い木造家屋が倒壊していないという状況を踏まえて、不可抗力(中略)を認めることはできない」とした。この裁判例では、賠償額の減額は認められなかった。
このような責任を回避するために、賃借人から「倒壊時の責任を負わない」旨の念書を交わすことを勧める向きもあるようだが、(特に90条、民法公序良俗に反する契約は無効となる )や消費者契約法の趣旨に照らして、このような合意の効力には疑義がある。オーナーはこのようなリスクがあることを知らないことが多いため、詳説した。
業種別BCPのあり方の他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
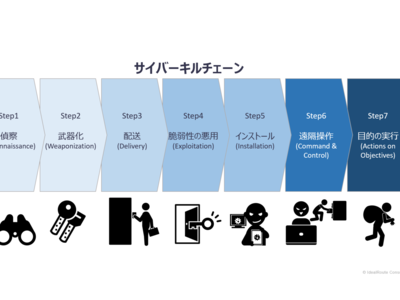




発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方