2016/06/15
誌面情報 vol55
年金機構の情報漏えい事案から学ぶ
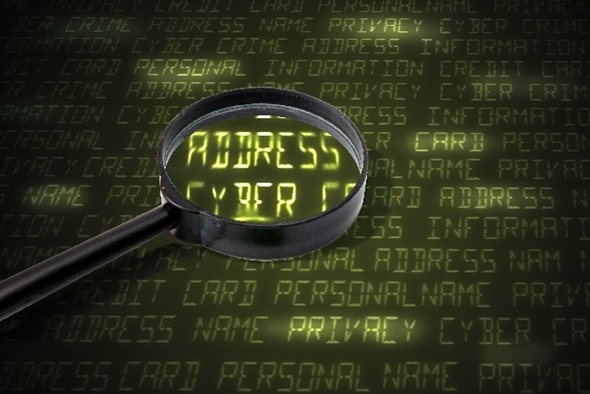

東京電機大学教授 佐々木良一氏
サイバー攻撃の被害は増えている。例えばインターネットバンキングの被害は2013年に14億円だったのが2015年には30億円になった。最初のターゲットは都銀や地銀だったが、これらの銀行が被害を受けて対策を進めたので、現状では信金などの組織での被害が増えてきている。
サイバー攻撃にはこれまでに2つのターニングポイントがあった。1つは2000年頃に科学技術庁などのホームページが改ざんされたとき。一般の人もサイバー攻撃を意識しはじめたのがこのころ。2001年には電子署名法がスタートした。
2つ目のターニングポイントは2012年ころ。典型的な例はMicrosoftWindowsで動作するワームであるStuxnetの出現になる。この2つの時代を比べると何が変わったかわかる。以前はハッカーが実力を示すため面白半分でやっていたが、今ではスパイや軍人、犯罪者などが参加するようになった。攻撃対象もホームページなどウェブサイトの書き換え程度だったものが重要インフラに変わり、不特定多数を狙ったものではなくターゲットを絞った標的型になった。Stuxnetは米国とイスラエルが協力して開発したと言われるマルウェアで、イランの核燃料製造用の遠心分離機を破壊した有名なウイルス。WindowsのPCからPCに感染し、普段は何もしないが、遠心分離機の回転を制御するソフトを見つけると動き出す。
イランの核燃料製造施設はネットワークにつながっていなかった。それでも攻撃された。それはUSBメモリを介して従業員のPCに侵入して感染が広がったからだ。
日本年金機構への攻撃
日本年金機構への標的攻撃は2015年5月8日にメールが届き、職員がURLをクリックして始まった。

メールの送付先は日本年金機構九州支部の職員だった。感染がなぜわかったのか。日本年金機構のネットワークを監視している内閣サイバーセキュリティセンターが検知した。そして厚生労働省を経由して日本年金機構に伝えられた。5月8日のメールは巧妙で、添付ファイルにウイルスが仕込まれているわかりやすいものではない。不審メールの件名は「厚生年金基金制度の見直しについて(試案)に関する意見」でリンク先は商用オンラインストレージだった。そしてこのURLをクリックした。内閣サイバーセキュリティセンターが検知して、全職員に注意喚起があった5月18日、複数の部署に「給付研究委員会オープンセミナーのご案内」という不審メールが届いた。これを1名が開封した。5月19日の段階で警視庁が捜査を開始したが、5月21~23日にかけて大量の情報が漏れた。
誌面情報 vol55の他の記事
- セキュリティとレジリエンシーの融合
- サイバー攻撃の正体
- 止める判断が求められる 企業のBCPにおける自然災害とサイバーリスク
- 年金機構の情報漏えい事案から学ぶ サイバー攻撃最悪のシナリオ
- IT-BCPの発展と課題
おすすめ記事
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方