2016/10/13
業種別BCPのあり方
2)お客さまと乗用車の安否確認
自動車販売業に勤務する一人のセールスパーソンには、年間で数十台の乗用車を販売することが求められている。これを長年にわたり継続することにより、自動車販売業の各社には相当多数のお客さまがいることになる。緊急事態が発生した場合は、これらのお客さまの状況を確認し、必要な支援を行うことが対応の基本となる。
また、緊急事態では、お客さまの安否確認に加え、乗用車についても状況を確認する必要がある。被害が出ていれば、早急に工場への入庫を誘導する必要があるからである。
発生した緊急事態の内容によって、乗用車に対し求められる対応は異なる。例えば単に強い地震が発生した場合であれば、乗用車に対する被害はそれほど大きなものにはならない。乗用車には走行時の揺れなどを吸収する装置があるためである。
一方、洪水、高潮、津波といった地表面への冠水を伴う緊急事態では、各店舗からお客さまに対し連絡をとるだけではなく、新聞への広告や貼り紙などを通じて、水没した乗用車がある場合は、手を触れず、早急に販売店まで連絡するよう告知することが望ましい。
これは、水による災害の場合は、多数の乗用車に同時に被害が生じる上、水没した車に手を触れると、二次被害が生じる可能性があるからである。水害発生時に水没した車には手を触れず、販売店などに連絡するように呼びかける等の取組みは自動車販売業に期待される社会的責務の一部と考える。
実例として2000 年の東海豪雨と2011 年の東日本大震災での事例を紹介する。
まず、2000 年の東海豪雨の際は、現在の清須市や名古屋市天白区を中心に5 万8 千台に水没被害が生じ、国内損害保険会社の支払額は合計で545 億円に達した(株式会社レスキューナウの調査による)。
また、2011 年の東日本大震災では、津波により損傷・冠水したことにより乗用車約7 万台が自走不能や使用不能の状態となり、被災地の自治体により処分された(公益財団法人自動車リサイクル促進センター等の調査による)。
このように水による災害は、乗用車に大きな被害を与える傾向が強いため、自動車販売業各社が連携し、業界団体などを通じて社会に安全な処理方法などを伝えていく必要が強いと考える。
3)被災車の取扱いに対する必要なアドバイスの実施
過去の事例から分かることとして、いったん水没した乗用車を再度使用できる状態にすることは非常に難しく、多くのお客さまは廃車を選択せざるをえないことが挙げられる。
これは、車が水没すると、車内の至るところに泥が入り込むためである。泥が入り込んだシートなどの布製品は、臭気を発するため交換するほかない。また、乗用車に多数搭載された運転制御用の電子部品や電子機器は、水没の影響によりほとんどが通常に機能しなくなる。これらをすべて交換して乗り続けるのは経済的合理性に欠けるという結論になることが多いのである。
大規模な水害の後は、自動車販売店各社でも在庫が払底することもあることから、買い替えを検討するのであれば早い方が望ましいというアドバイスが必要になる。
発生した緊急事態の内容によっては、別のアドバイスが望ましいこともあるだろう。自動車販売店は、単に自動車を売るだけではなく、お客さまのカーライフを支えることが事業の柱である以上、発生した緊急事態の内容に応じて、適切なアドバイスをできる体制を作ることが社会から期待されていると考える。
業種別BCPのあり方の他の記事
- 第23回 事業中断対策の今後(1)
- 第22回 自動車販売業の事業継続
- 第21回 緊急事態における企業の対応要員の行動
- 第20回 ガス業の事業継続(2)
- 第19回 ガス業の事業継続(1)
おすすめ記事
-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

-












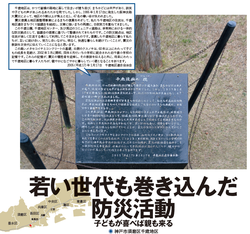














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方