2018/05/10
熊本地震から2年、首長の苦悩と決断
復旧・復興の3原則
職員には、災害対応について3つの原則を示しました。1つ目は、被災された方々の痛みを最小化すること。2つ目は、単に元あった姿に戻すだけでなく、創造的復興(Build Back Better)を目指すこと。3つ目は、復旧・復興を熊本の更なる発展につなげることです。多くの人が避難をしている大混乱の最中、これを言うのは知事といえどもかなり勇気が必要でした。期待値として誰も考えてもいないことを言うわけですから。マスコミあるいは職員の目も、少し冷ややかだったと思いますね。
この原則は、平成24年7月に発生した熊本広域大水害で阿蘇地域が大きく被災した時に考えたものです。被災者の痛みの最小化の理念は、仮設住宅を木造で整備したことに生きています。阿蘇の大災害では、仮設住宅を全て木造で整備して、住民に喜ばれており、痛みの最小化が実証されています。このため、今回も国と協議して敷地を従来よりも広くしたり、ペットを飼うことを認めてもらったりして、被災者の精神的な負担軽減に努めました。
創造的復興には、単に元の姿に復旧させるだけでなく、もう少しお金を出せば活性化につながる可能性があるので、視野を広げて考えよう、というメッセージを込めています。「元に戻すまでの復旧には支援を行うが、それ以上は被災自治体が自らやるべき」という国の基本的な理念は今も変わりません。しかし、プラスアルファを生み出す部分がとても大事であり、創造的復興というのは、ピンチをチャンスに変えることができる考え方だと思います。これは、「逆境の中にこそ夢がある」という私の信念にも通ずるものです。ただ、創造的復興というのは、初動がうまく進まないとなかなか言えないものです。そういう意味でも初動が非常に大事です。そして、更なる発展につなげていくという復旧・復興の原則を示すことで県民に希望を与えることが何より大切だと思うのです。
ハンティントンのギャップ仮説
発災当初から私が一貫して考えていたのが、恩師であるハーバード大学教授の故・サミュエル・ハンティントン氏が唱えた「ギャップ仮説」です。この理論は、簡単に説明すると、人々は多くの期待を持っていますが、その期待値は非常に短期間のうちに変化します。その期待に実態が素早く追いつかないと不満を生み、それが暴動にまで繋がるというものです。つまり、期待値が小さいうちに期待に沿う状態を可能な限り早く作らなくてはいけないということです。
リーダーの仕事は展望を示すこと
ギャップ仮説における期待値と実態の差を小さくするには、次に何が起こるかという予測が必要です。例えば人命救助を中心とした初動期では、救出の後に、水と食料、そして避難所を確保しなくてはいけない。避難所を確保した後は、仮設住宅を建設するなど本格的な応急期に移り変わります。最初はどの段階でも期待値は小さい。しかし、実態が伴わないと、すぐに不満が出てきます。
ところが、すべてのことに対して、素早く対応できる訳ではありません。その場合は、リーダーが「展望」を示すことが大切です。併せて、「いつまでにやります」と具体的な期限を設けることで、アナウンスメント効果により、県民の不満が和らぐと思います。例えば、中小企業に対して施設などの復旧費用の4分の3を補助するグループ補助金については、平成28年6月から公募をはじめました。もし対応がもっと遅くなっていたら、どんどん倒産する企業が出ていたでしょう。補助金がすぐに出せなくてもいつ頃には出せるなど展望を示すことが大事です。4分の1の自己負担で済むということを知っているのと知らないのでは、経営への影響が全く違います。最も考えなくてはいけないことは、被災者自らに立ち上がる力を出してもらうことだと思います。
緊急時にこそ知事の姿を見せる
他方で、多くの批判を受けたのが、初動期に知事がテレビに出てこないということでした。しかし実際は、毎日1回ぐらいは県内メディアの取材には応じているんです。なぜ出てこないと言われたかというと、マスコミが全国化してしまっていたのです。東京からキー局が来て、地震の甚大な被害の報告とか、国レベルの対応ばかりを取り上げ、地元ニュースより優先されて放映されるため、県民からすると、知事の姿が見えず、不安が生じたのだと思います。やはり知事はメディアに出て、自分の言葉で県民に説明しないと駄目だと痛感しました。災害対策本部から発信するだけでは弱かったのではないかと思っています。大規模災害では必ず「メディアの全国化」が起こるので、全国の首長はどう対応するか災害前から考えておく必要があると思います。
早い段階で復旧・復興の道筋を示す
本震の翌月の5月には「くまもと復旧・復興有識者会議」を設けました。私以外に、理念も含めてしっかりと考え助言してくれる人が必要と考えたからです。本震2日後の4月18日に、熊本県立大学理事長の五百旗頭真先生に電話して、五百旗頭先生を座長に、副座長としては東京大学名誉教授の御厨貴先生に、その他には、地震学者の河田惠昭先生や東大時代の同僚の方々にもお願いをして、5月10日に有識者会議を立ち上げました。皆さんは私の友人で、時間的緊迫性を理解していただいていましたから、震災から2カ月となる6月19日に、提言書をいただきました。それをもとに熊本地震からの「復旧・復興プラン」をまとめ、8月3日に県民に示すことができました。
マスコミの人たちからは、人命救助や水・食料の確保が大変な段階で、そんな有識者会議で哲学が必要なのかと、冷ややかな指摘もありました。しかし、前述の「ギャップ仮説」にあるように、人よりも早く考えないと「期待値」と「実態」はすぐに乖離してしまいます。
熊本地震から2年、首長の苦悩と決断の他の記事
- 熊本地震を乗り越えた首長に学ぶ、災害時のリーダーのあり方
- 『熊本地震の経験を、日本全体の教訓に』(熊本県知事 蒲島郁夫氏)
- 『最悪を想定した訓練が奏功』(西原村長 日置 和彦氏)
- 『震災1年後に新村長に就任』(南阿蘇村長 吉良清一氏)
- 『公平な支援が必要』(嘉島町長 荒木泰臣氏)
おすすめ記事
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-








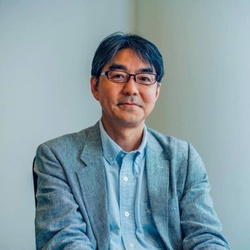
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方