2018/05/10
熊本地震から2年、首長の苦悩と決断
具体的にいつまでにやるかを約束
「復旧・復興プラン」でロードマップを示した項目のうち、県民生活に特に深く関わる「重点10項目」について、私の3期目の任期までにやることを具体的に県民に示しています。行政は、普通、時間まで約束しないのですが、バッシングを恐れて何もやらないと次第に遅れていくので、あえて期限を設けました。例えば、住まいの再建は、あと2年で全ての被災者の方が本格的な住まいに移行できるように後押ししています。東日本大震災では7年近くたった今でも何万人もの方が仮設住宅におられますが、被災者にもそれぞれに事情があることなので約束するのは難しいことです。
しかし、これを実現するために、現在、4つの支援策と予算を準備しています。例えば、高齢の方々がリバースモーゲージ制度を利用してお金を借りる場合に、月々1万5000円の返還で一生そこに住んでいただいて、最終的に息子さんなど身内の方が残金を支払えなければ土地と建物で清算できるようにする。あるいは、子どもを持った若い世代の方々も毎月の支払いが2万円で済むよう、県が利息分を助成するというような「熊本型」住まいの再建支援の仕組みをつくり、被災者にお知らせをしています。
「地方負担の最小化」の選択
痛みの最小化というのは、市町村の財政負担の最小化ということでもあります。県も市町村も復旧・復興にものすごく膨大なお金が必要になりますが、東日本大震災では増税措置があったことで、被災自治体は財政負担ゼロでやることができました。今回の熊本地震でも、当然それと同じことを皆さんが期待するわけですが、最終的に国と折り合いをつけたのは「地方負担の最小化」ということです。地方負担ゼロを求めるなら特別措置法の整備や増税措置が必要になり、かなりの時間を要します。時間がかかる分、最終的なトータルコストは高くなり、プロジェクトの費用対効果は縮小してしまいます。ですから、どちらの方がいいかと判断するのではなく、どちらが効率的かと考える必要があると思うのです。災害時における県民総幸福量の増大の観点から、私は、時間的緊迫性のもとで地方負担の最小化を図ることが重要だと判断しました。
無駄遣いはしないという哲学
もう1つ、私が大事だと思っているのは、復旧や創造的復興に必要な財源は国民の血税ですから、納得の得られる使い方をしなければいけないし、それを私はきちんと示さなくてはいけないということです。今、熊本県では災害対応以外の予算はすべて20%の節約をしています。例えば補助金を20%カットしたことで、さまざまな事業や団体にも影響が出てきています。そういうしわ寄せが出た時こそ、無駄遣いをしてはいけないという哲学を行動で示さなくてはいけないと思います。
国の財政支援制度の常設化
私は、こういう大規模災害が起こった時に、県・市町村が躊躇なく復旧・復興に取り組めるよう、国はあらかじめ財政支援制度を常設化しておく必要があると思います。そうでないと、災害のたびに知事や市長が東京の各省庁を回って要望することになり、結果として、被災地の復旧・復興が遅れてしまうからです。
緊急時のリーダーシップ論
私は緊急時のリーダーシップというのは、動じないことだと思います。リーダーがおろおろしたら終わりです。いかに対応するべきか全て分かるわけではありませんが、過去の歴史があります。私は、地震発生後に震災関連の書籍を短期間で読み、対応を学びました。
私が日頃からリーダーとして心がけていることは、方向性を示すことです。すべてのことを知事がやれるわけではありません。私は方向・方針を示した上で、実際の対応と判断は各部の実務者に権限を与えて、すべて任せていました。当然、スタッフも大変ですが、頑張ってやってくれています。私はそういうリーダーシップのあり方で、これまで10年間の県政を進めてきましたので、県庁の職員にも浸透していると思っています。
リーダーが言わない限り、何も起こらないし、何も変わらない。これが私のリーダーシップ論です。
被災者の「心の復興」を目指して
これから、被災者の暮らしを再建する上で一番大事なのは、「心の復興」です。どんなに建物が立派になっても、どんなに交通インフラが良くなっても、仮設住宅にいる間は、被災者は復興を感じられないと思います。極端なことを言えば、仮設住宅の入居期間を1年延期するよりも、そのお金で住まいの再建を支援して自立していただいた方がいいのではないか。だから、県は時間的緊迫性を考え、国に措置いただいた復興基金を活用して、今まさに、住まいの確保の支援に取り組んでいます。自宅の再建が叶い、本当の意味での「心の復興」ができて初めて、災害対応がうまくいったという評価になると思っています。
熊本地震から2年、首長の苦悩と決断の他の記事
- 熊本地震を乗り越えた首長に学ぶ、災害時のリーダーのあり方
- 『熊本地震の経験を、日本全体の教訓に』(熊本県知事 蒲島郁夫氏)
- 『最悪を想定した訓練が奏功』(西原村長 日置 和彦氏)
- 『震災1年後に新村長に就任』(南阿蘇村長 吉良清一氏)
- 『公平な支援が必要』(嘉島町長 荒木泰臣氏)
おすすめ記事
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03
-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26
-








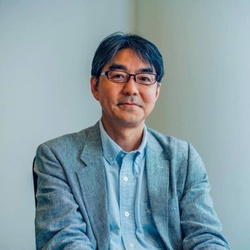
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方