企業のAI導入が失敗するシンプルな理由
第47回:IT後進国から脱却できるのか(7)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2023/09/13
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

これまで、AIの特徴や功罪面にスポットをあて、ITも含めて便利な道具として適切に使い効果を上げるべきであることを主張してきた。同時に、IT 環境の変化にともない、環境変化に適合して自分自身も変化していく必要性を訴えてきた。それらを踏まえ、実社会でのAI活用にどのように向き合うべきか、どのような注意が必要なのかを論じていきたい。
いま、多くの企業で「AI」あるいは「対話型AI」の実用を促すトップダウンの指示がなされている。新聞紙上でも、多くの企業に同様のアンケートが実施されている。さて、そのトップダウンを受けて、現実にはどのような動きになっているだろうか。
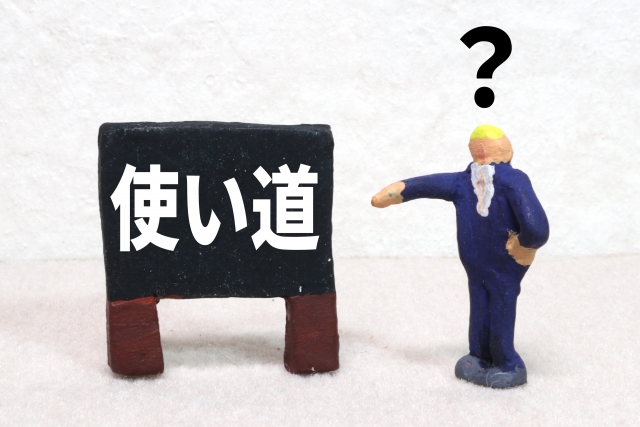
トップダウンを受けた組織は、最初に勉強から始めるのではないだろうか。その場合、指示と同時に、コンサルタントが作成した利活用の事例が配られ、ときには勉強会などで説明を受ける。そしてその事例を自部門の業務に当てはめ、適当な業務を選定し、効果想定した数字を添えて提案して実行に移す。これがAI利活用の実績となる。
コンサルの立場でもある筆者がいうのもなんだが、このコンサルによる誘導が本質的な利活用を妨げ、指示待ちの受け身姿勢を生み出し、イノベーションを阻害するのではないかと感じざるを得ない。結局、必要性に応じた導入ではなく、使うこと自体が目的化してしまっているのだ。
つまり、AIを使用している進んだ企業であるというプロパガンダを重視し、各組織に導入を競わせている。実際、東京都庁の発表では、全部局へ導入し5万人規模の利用者とのことだ。が、この構造で生み出された実績は虚構でしかない。ユーザーの必要に寄り添っていないからだ。
システム開発を成功に導く秘訣の一つとして古くからいわれているのが、ユーザー参加である。それは、ユーザーが実際に困っていることを解決し、実施したいことを実行する手法として、システムという道具を利用すべきだからだ。そこでユーザー側の要件定義が肝になるのは当然である。
確かに変化と冒険を嫌う日本社会の気質で新しい道具を実用化するには、トップダウンによる強力なリーダーシップは必要不可欠だ。が、だからといってユーザー側の需要を無視して有効な実用化につながるはずはない。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26



報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点
ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。
2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン
家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。
2026/01/23


※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方