「日本人と愛国心」憲法改正は軍をつくること
さらに国内用の武装鎮圧部隊ができる

高崎 哲郎
1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。
2019/08/19
安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎
1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。
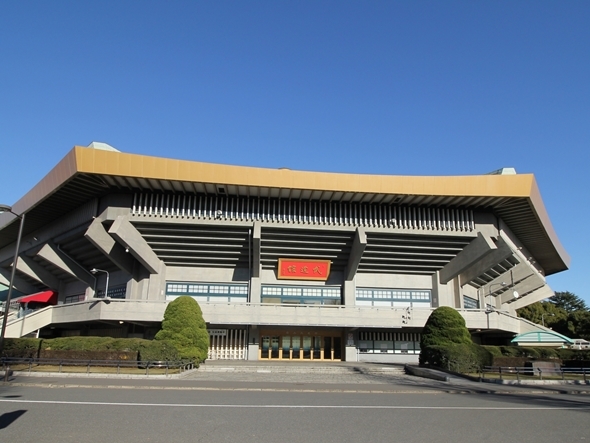
「日本人と愛国心」(半藤一利・戸高一成両氏の白熱の対論、PHP文庫、2014年刊)。
何とも刺激的なタイトルの新書本である。だが、<歴史探偵>を自称する作家半藤氏の著作の大半を愛読してきた私は、本書も一気に通読してしまった。半藤氏(戦前派)の対論者の戸高氏(戦後派)は、呉市海事歴史科学館館長で海軍史がご専門である。同書は私の期待を裏切らない好著であった。中でも半藤氏の鋭い論法に快哉を叫ぶことがしばしばだった。以下、私が深く同意した氏の勇気ある発言を紹介する。
「対米英戦争(太平洋戦争)に終始反対だった昭和天皇は、『昭和天皇独白録』の中で、『私が開戦に最後までノーと言ったならば、おそらく幽閉されるか、殺されるかもしれなかった』という意味のことを語っています。現在の若い人には考えられないような話のように思われるでしょうが、ともかく昭和天皇ご自身がそう思われていた。
これは昭和天皇に限った話ではなく、(日独伊)三国同盟に反対していた海軍の山本五十六も身の危険を感じて『戦地で死ぬのも国内で殺されるのも同じだ』という意味の遺書をしたためていましたし、最終的には同じ海軍の米内光政のはからいで暗殺されないように連合艦隊司令長官として海に出ることになります。
このような漠とした恐怖心、あるいはどのような立場の人間であれ脅迫があって自由に発言ができないという重苦しい空気の背景には、昭和7年(1932)の5.15事件と昭和11年(1936)の2.26事件がありました。
陸軍青年将校によるクーデターだった2.26事件は、昭和天皇の頑とした拒否の姿勢によってあっけなく失敗に終わるのですが、この事件が日本人に与えたショックはとてつもなく大きなもので、その後の昭和史にはずっと2.26事件の影がついてまわることになります。
そもそも、日本における陸軍は西南戦争を鎮圧するための国内鎮圧部隊として、本格なスタートを切っています。
これは意外と見過ごされることですが、陸軍の本領は敵地への進出ではなく、第一に国内の鎮圧なのです。陸軍とはそもそもが巨大な武装治安部隊であり、そして外国の侵略を排除するのはそもそも海軍なんです。
武装治安警察という意味で考えるなら、陸軍は国民に対して常に権威を見せつける必要がありました。だから国民の目から見て「陸軍は態度がでかい」とか「陸軍は横柄だ」というのは、ある意味では仕方がない面もあったのでしょう。
ですから、当時の子どもたち(戦前に育った子どもたち)は、私も含めてみんな海軍ファンでした。
とにかく陸軍というのは、いつも自分の身のまわりにいる部隊なんですね。しかも軍刀をガチャガチャぶら下げて長靴を履いて偉そうにしているから、なんとなく気に食わない。それが海軍は海や港にいるだけでしょう。たまに見ると、スマートでかっこよく見えちゃうわけです。
ただ偉そうだとか何となく気に食わないというレベルなら話はそれで終わるのですが、陸軍にはもっと大きな問題があります。
要するに陸軍は『武装クーデターが起こせる集団』なんですね。
いまでも世界各国から武装クーデターのニュースが飛び込んできますが、それはほとんどすべてが陸軍です。
クーデターが起こせるということは、それだけ国内への発言力や影響力を増してくる。私が自衛隊を『軍』に変えることに反対している、最大の理由はそこです。
もちろん、陸上自衛隊の方々が災害救助などに大変貢献されていることは素晴らしいことですし、その必要性も大いに認めるところであります。
しかし、いまの自衛隊は行政組織の中にある、行政各部の一部としての『隊』です。
これが軍隊になると行政組織の外に出てしまいます。軍隊はそもそも3権の外にあるものです。軍隊の権限は『原則自由』で、例外的に国際法の制限に服するものです。それが軍隊です。
もちろん、現在の日本おいて武装クーデターなど考えられない、現実的にあり得ないという声が多いことは百も承知です。
ただ、ここで私が言いたいのは『武装クーデターを可能にする仕組みをつくるな』ということです。いわゆる軍ができることによって『軍隊による安全』を国民は期待できます。同時に、『軍隊からの安全』を常に憂慮しなければなりません。軍隊が民主主義の脅威になってはならない。それが昭和史の教訓であります。
憲法改正の議論が出ると、野党からは『また戦争するつもりか』という声が上がります。しかし、問題はそこにあるのではない。軍をつくるということ、それはこの国に国内用の武装鎮圧部隊ができるということなのです」。(引用者:「軍をつくるということ、それはこの国に国内用の武装鎮圧部隊ができるということなのです」にこめた半藤氏の反戦への祈りをかみしめたい)。
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事


海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05



中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/03



発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ
2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。
2026/01/26

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方