2020/06/22
講演録
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によってもたらされる新たな日常「ニューノーマル」へ向けた働き方のシフトが加速してる。こうした動きに対し、企業は今後、どのように危機管理やBCPを見直していけばいいのか。リスク対策.comでは6月2日、「コロナ後のニューノーマルにおけるBCP」をテーマにウェビナーを開催し、ニュートン・コンサルティング株式会社取締役副社長の勝俣良介氏が講演した。東京商工リサーチ 情報本部情報部部長の松永伸也氏が講演した。2回に分けて、本ウェビナーの講演内容を紹介する。
①ニューノーマルの動きと、BCP見直しのポイント
ニュートン・コンサルティング株式会社
取締役副社長 兼 プリンシパルコンサルタント 勝俣良介氏
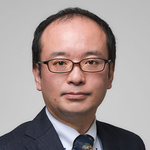
新型コロナウイルス感染症のBCPシナリオとして、これからどんな問題が考えられるだろうか。キャッシュフローの心配や、在宅勤務に関する悩みや不安が聞こえてくる。BCPがうまく活用できていないという声もよく聞く。新型インフルエンザ用にBCPを用意していたが、うまく合わずに苦労している企業もある。こうした問題を、「今」「短期的」「中長期的」という時間軸で整理してみたい。
まず「今」というところでは、予防が大きなポイントになる。Withコロナの状態で、感染しないで働く環境をどう作るか。この1点に尽きる。手洗い、うがい、消毒液、レイアウト変更のほか、人の物理的な交流機会を減らすため、大きな会議室の活用や、大勢での集合会議の禁止も見られる。
通勤リスクによる感染リスク低減も大きなテーマになる。通勤の機会を減らす目的で、2日出社2日休みにする方法や、車や自転車での通勤を許可するところも増えてきている。現場の改善では、ビニールの間仕切りや動線変更、同じ役割・機能を担う者を一緒に行動させない2チーム編成などが見られる。感染者の検知能力を上げるという点では、会社での出退勤管理をはじめ、店舗での検温や入場制限、出入り口の管理などがある。そのほか、教育の実施やリスクアセスメントなど、諸々の施設内での感染予防策が講じられている。
環境は個々で異なるため、専門家が言ったことを完全に正解としてコピーして導入してもダメだ。自組織の環境を見極めた上で、固有の対策が必要になる。まずは施設などの物理的な環境のリスクアセスメントを行うことが非常に重要になる。当然、自社で気づかないこともあるので、他社の先進事例も常にウォッチして取り入れることが社会全体での免疫力の底上げになるかと思う。
講演録の他の記事
おすすめ記事
-

今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/10
-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/02/05
-

-

-

-

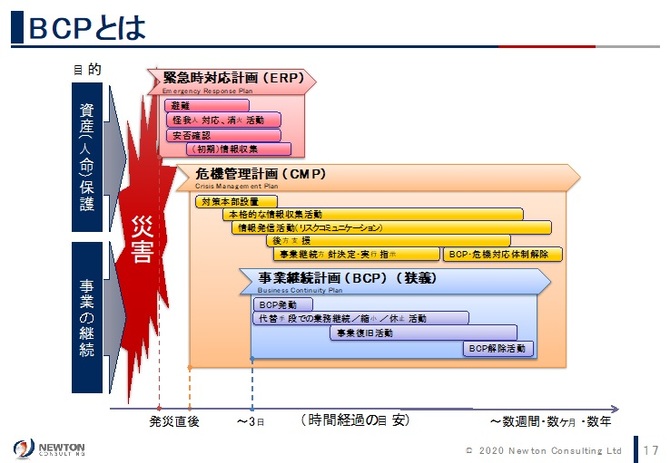











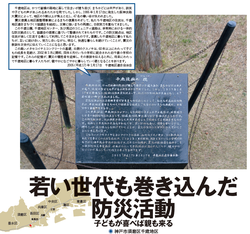














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方