連載
-
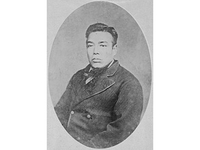
薩摩閥三島通庸、土木建築の成果と民衆弾圧
明治期の政治家三島通庸(みちつね、1835~88)ほど、県令(現知事)として勤務した東北地方で評価の極端に分かれる人物も少ない。辣腕(らつわん)政治家三島は初任地山形県では<土木県令>として「後進県」の近代化に尽力し、帝都に通じる道路やトンネルをつくり、同時に県庁など公共施設の近代建築化に果敢に挑んだ。その目を見張る土木建築事業の成果は、恩恵として、また遺産として同県人に高く評価されている。ところが山形県の後に赴任した福島・栃木両県では評価は逆転し、自由民権運動を弾圧する憎むべき<鬼県令>として語り継がれている。悪評ばかりとも言える。
2019/04/01
-

リスクの強烈さ 大災害、高まる脆弱性
「ようこそ、世界の交差点へ」 路線①の電車がタイムズスクエア地下鉄駅へ入線してくると何十年来使い古されたスピーカーから車掌の大きなよく聞こえる音声が流れる。ニューヨーク、それは金融・テクノロジー・アート・ファッションの国際センターである。ハドソン湾とイーストリバーが合流して大西洋に注ぐところにできた広大な自然の港を取り囲んでいる。エンパイアステート・ビル、セントラルパーク、そしてタイムズスクエアのネオンなどを見に訪れる観光客は毎年6000万人にのぼる。それは眠らない都市である。しかし、そこで暮らす850万人の住民にとっては、ビッグアップルのバイタリティには、日常の仕事をやっていくうえで不都合な点もある。
2019/03/29
-

野菜が乏しい災害食
写真ACスーパーの店頭には、まず果物、野菜売り場があり、奥に魚や肉の売り場が続きます。なぜ野菜が入り口近くにあるのでしょうか? 多分、献立を考えるときの決め手が、まずは「野菜」ということなのでしょう。野菜が「主役」なのは、買い求める分量で野菜が一番多いからです。
2019/03/26
-

軍部に屈しなかった政界重鎮・牧野伸顕
私は千葉県柏市に移り住んだ際、是非とも訪ねてみたいと願った同市やその周辺(東葛飾地方)の歴史的由緒のある地が少なからずあった。その中の一つが、戦前国際協調派の政治家・外交官として知られる牧野伸顕(まきの のぶあき)が晩年を過ごし永眠した柏市十余二(とよふた)の寿町(ことぶきちょう)である。私は近現代史に関心を持つものとして、牧野の生涯に関する書籍や文献を通読してきた。隠棲地・十余二で身内のみに見守られて静かに息を引き取った牧野は傑出した政治家といえる。その80年余りの激動の人生をスケッチしてみよう。
2019/03/25
-

安全基準を少しだけ下げて落札した企業
私は、リスクマネジメントの目的はズバリ「会社を倒産させないため」だと思っています。会社が倒産する理由は最終的に「収入」<「支出」という財務的破綻が原因となりますので、リスクマネジメントとは「収入」に係るリスクと「支出」に関わるリスクを管理する手法とも言えます。でも、社長や財務部門だけが考えればいいことではありません。収入や支出に関わるリスクとは、言い換えれば本来あるべき姿との「差」であり、その差を生じさせる要因は、社員一人ひとりの行動にある、その行動を管理するのがリスクマネジメントです。従って、経営への影響を考えないリスマネジメントはあり得ませんし、従業員一人ひとりにどう当事者意識を持たせるかがリスクマネジメント活動の最も重要で、難しい部分にもなります。
2019/03/25
-

第3回 社内調査における ヒアリング手法(1)
今回は社内調査の重要ツールであるヒアリングがテーマです。ヒアリングに関しては検討すべき事項も多いため、2回に分けて解説します。今回はヒアリングをめぐる一般的・総論的な事項を解説し、次回は個別のヒアリング・テクニックに言及します。
2019/03/25
-

第2回:経済資本と組織資本について
これから数回にわたり、東日本大震災の被災自治体の事例を基に、「キャピタル×システム」概念がどのように過去の教訓を一般化することができるのか、書いていきたいと思います。
2019/03/20
-

第2回:「災害は増えている」はフェイクか?
数年前、アマゾンのサイトで「地球温暖化」をテーマとする本を探していたところ、「地球温暖化なんてうそである」という主張の本が人気ランキング上位にずらりと並んでいるのを見てあ然としたことがあった。今でこそある程度バランスのとれた本が並んではいるが…。
2019/03/20
-

災害食「カップ麺を斬る」その2
2016年8月から、手持ちの飲み物でカップラーメンが食べられるか実験を行いました(20015年にはアルファ化米について同様の実験済み)。では「お湯がなければカップ麺が食べられない」というあなた様の常識を斬ってあげましょう!
2019/03/19
-
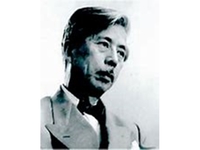
都市計画家・石川栄耀の孤独な戦い
昭和20年(1945)8月15日、太平洋戦争は昭和天皇の玉音放送によって終わりを告げた。敗戦国の民衆を襲ったのは極度の飢えと虚脱感それにささやかな解放感であった。戦災による犠牲者は約185万人、領土は戦前の40%を失った。日本は北海道・本州・四国・九州の4島に押し込められ「三等国」に転落した。8月30日、GHQ(連合国軍総司令部)最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が愛機「バターン号」で厚木飛行場に到着した。日本が初めて体験する「無血占領」と「間接統治」の始まりであった。
2019/03/18
-

最悪の事態における初動対応シナリオ
「一体この地獄絵は何なのだ」 大統領に別の携帯電話が手渡されるが何の応答もない。 「もしもし私だ」 「はい、申し訳ありません、大統領。それらはつい15分前から撮影された衛星写真です。ニューヨーク市で核爆発が起きたようです。写真から計算すると5~7キロトンの核出力と思われます」
2019/03/15
-

災害食「カップ麺を斬る」その1
何気なく食べているカップ麺。いつでも、どこでも、誰でもおいしく食べられるカップ麺。そんなカップ麺が東日本大震災時の避難所でひんしゅくを買っていたことをご存じですか?
2019/03/14
-

2時間以内に最初の情報提供をしなさい!
記者は直後から殺到します! イラスト:フォトライブラリーある大手部品メーカーの工場で正午に火災が発生しました。直後から報道各社の記者が一斉に取材に動き出し、17時に同社では謝罪文を配布、記者会見が行われたのが21時という事例があります。
2019/03/14
-

近所づきあいが事業継続力を高める秘訣
町内会などの活動のように、一見自社の業務に関係なさそうな地元の集まりに顔を出すことは、自社の事業継続を考える上で実は、大変重要な情報を得られるチャンスになるんです。 今回はその理由について考えてみたいと思います。
2019/03/12
-

日本にもようやく春(液体ミルク)がきた
やっと日本にも液体ミルクの製造が認可されました。遅すぎませんか? 災害のたびに避難所ではミルクをもらえない乳児が泣きわめいていました。
2019/03/12
-

停電に向けたビジネス・レジリエンス・トレーニング
あるオーストラリアの銀行が、ビジネスにおけるレジリエンス訓練を実施し、その中で、週末にかけて実際に電力をとめ、自社の事業継続計画(BCP)をテストすることにしました。
2019/03/11
-
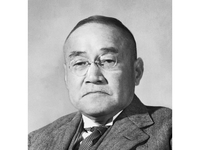
戦時下の外交官吉田茂・検挙事件
戦前の英米派外交官吉田茂(後の首相)の戦時下における反軍思想とその苦闘を考える。
2019/03/11
-

第7回 相次ぐ建設現場における火災
■2018年7月26日 東京都多摩市唐木田で建築中のデータセンター(地上3階・地下3階)の地下3階から出火し、男性作業員5人が死亡、約40人が負傷(うち25人が重傷)。鉄筋切断作業中に火花が断熱材に引火したとみられる。
2019/03/08
-

第2回 内部通報と社内調査を開始するか否かの判断基準
社内調査の端緒には、内部通報、財務監査を主とする定期監査などがあります。捜査機関による捜査によって社内調査をする必要性が発生する場合もあります。官公庁、例えば国税庁による査察等によって社内調査をしなければならなくなる場合もあり、さらにマスコミによる報道なども調査の端緒となり得ます。こうした社内調査の端緒については次のように2つの類型に分けて考えるのが有意義です。
2019/03/08
-

第1回:もう一つの危機的事態
「BCP(事業継続計画)」という言葉は、今やビジネスの世界では「防災・減災」と同じくらいに一般用語として定着している。一昔前なら、初めて会う人にBCPのことをあれこれ説明するのは少し億劫に感じたものだが、今ではBCPと口にしただけで「ああ、BCPね」とすぐにあいづちを打ってくれる人が増えた。
2019/03/07
-

3つの原則を覚えるだけで対応が劇的に変わる!
リスクマネジメントというと、専門的な用語に聞こえるかもしれませんが、要は、危機を予測し、できるだけその影響を受けない、あるいは小さくすることの活動です。これに対して、危機が発生したときにダメージを最小限に抑えるための活動をクライシスマネジメントというような言い方をしますが、実は、危機の発生直後は、当事者でさえ何が起こっているのか情報を正確に把握できないことが多いものです。たとえば、某食品会社で食中毒事件が発生したとき、総務部の社員でさえ、何が起きているのかまったくわからなかったそうです。そこで役に立つのが「危機管理広報」です。
2019/03/07
-

第1回:大規模災害対応のための「キャピタル概念」
私たちの住む都市は、複雑で、ダイナミックなリビング・システム(生きたシステム)です」――と言っても何のことか分かりにくいですよね。ごめんなさい。
2019/03/06
-

訪日外国人が驚く災害食とはなんでしょう
私がアメリカを訪問していた時のことです。大型スーパーで魚の缶詰を買って持ち帰り食べていました。途中で「あっ、これひょっとしてペットフードじゃあない?」と気付いたときはすでに遅く半分以上食べた後でした。悔しい!うらめしや!
2019/03/05
-

<米将軍>徳川吉宗と<紀州流の祖>井澤弥惣兵衛
近年、大水害が頻発している。異常気象による<想定外>の豪雨などが要因との指摘を聞く。だが無堤地のままの中小河川や管理者のいない農業用ため池、湿地・沼地の宅地用乱開発、森林・原野の管理放棄などが被害拡大の背景にあるのではないだろうか。ここで江戸中期の大規模新田開発の成果と大水害の多発の因果関係を考えてみたい。
2019/03/04
-

カタストロフィー(大災害)を想像する
海面下すれすれのところで艦長はエンジンの停止を命じる。艦長は受話器をとり短いやり取りをした後、電話台に戻り、副官の顔をみる。 「準備でき次第、発射」のラジオ音声が船内を流れて船尾の発射室に伝わる。 誰もが手を握り締める中、長い3分間が経過し、スチーム大砲が60トンの飛行体をハッチから海面へ向けて発射するとき、その爆発は艦艇を揺るがす。KN11/Pukguksong-1(ポラリス1)弾道ミサイルは水中から飛び出す。ロケットエンジンは着火し、大空へ向かう。
2019/03/01













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





