<没後55年記念特集>青山士のパナマ運河開削時代~青春の情熱、唯一の日本人土木技術者~最終回
突然の帰国と偉大なる足跡

高崎 哲郎
1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。
2018/05/01
安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎
1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。
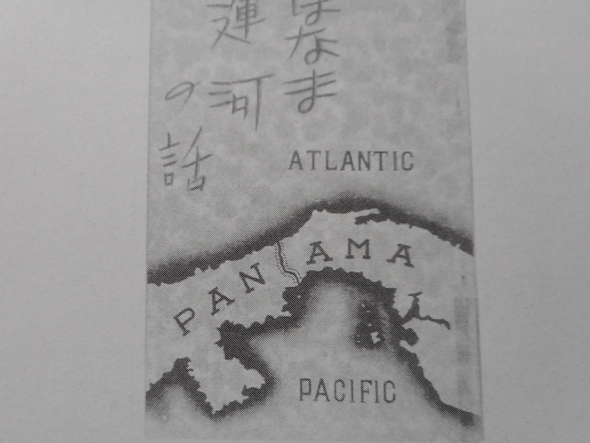
明治37年(1904)6月7日、熱帯の夕日が燃えるパナマ大西洋側の港コロンに測量隊を乗せたユカタン号が接岸した。大勢の隊員中、日本人は背丈の低い青山だけである。晩年になって、青山は当時を振り返って言う。
「熱帯無人の境における測量は中々費用を要するのみならず、天然との戦争で大いなる苦痛を伴うものでありますが、今になって顧みると血湧返(わきかえ)るを覚えて愉快のこともあります」(「ぱなま運河の話」)。
青山は現場を愛し現場にすべてをかけた土木技術者であった。カリブ海に面したコロン港は不潔であり、生水を飲むことは厳禁であった。良い宿泊施設もないため、測量隊は船中で一晩を過ごした。翌日、測量隊の隊員各人に蚊帳(かや)と毛布1枚が渡され、港から7マイル(約11km)離れたチャグレス川河畔の村ボヒオまで歩いた。(ボヒオはガトゥンダム人造湖の湖底に沈む。パナマ運河の重要な水源となるガツン湖は琵琶湖より一回り大きい。)。青山は、ドーズ班長が指揮するチャグレス川支流トリニダード川測量部隊の一員になった。「闇の奥」ジャングルとの戦いの始まりである。その晩は、フランスの運河会社(すでに撤収)が残して行った古い朽ちかけたコロニアル風洋館に入り、殺菌用の石炭酸水で床や壁を洗い、鼻を突く石炭酸水の臭気が残る部屋で寝た。屋根裏には何千匹ものコウモリがギイギイと鳴き、床にはアブラムシがはいまわっていた。その後、この廃屋を前線基地として使うのである。
青山は、サウナの中のような異常な湿度と暑さの中、テント生活を続けながら野外測量班の班員として蚊よけの網を頭からすっぽり被り、ダム候補地の測量と地質調査を続ける。ひとつ班は5人ないし6人の現地労働者に加えて、荷物食糧運搬人と料理人の5人ないし6人の編成である。測量の結果は、その日のうちに班長が白人の上司(組長、技師)に報告し、それをもとに組長が図面に地形や地質をプロットしていく。
明治39年(1906)から、セオドア・ルーズベルト大統領の発案で、現地の労働者・技術者をゴールド組とシルバー組に分けた。ゴールド組は2年間勤続し優秀な成績をあげれば金メダル(高級な金貨)が与えられる白人高級技術者らを中心とする幹部グループである。優秀な技術者確保のための褒章制度である。シルバー組は現地労働者らであり、その大半が黒人であったが、中国人も少なくなかった。青山の遺族宅には、青山が獲得した純金のやや小ぶりな金貨が残されている。金貨は赤い布に包まれており、白い縦長の布に「汗ト涙トヲ以テ獲タル」と青山は筆で書きこんでいる。アメリカ人の中でも、この金貨を与えられた技術者は必ずしも多くはなかった。
当時のアメリカ人の日本や日本人に対する認識は薄く、日本国がどこにあるかを知らない者が多く、また黄色人種に対する人種差別的行為もあった。「(現場作業は)下から認めてやらしてもらうので容易ではなかった。気候は暑く不衛生地で蚊が物凄く、家は金網張りだからいいが、作業は袋をかぶってやる事には閉口したが、よく生きて帰れたものだ」。
青山は後年内務省の後輩技師に述懐している。(牧野雅樂之丞「青山士句君追悼号」、旧交会刊行)。「日本などどこにあるかわからない労働者」(青山)の中に入って蚊や毒蜘蛛などから身を守るネットをかぶりながら働くのである。工事初期、特に1905年頃は黄熱病などが激しく発生し、逃げ帰る者が相次ぎ、またパナマへ働きに来るや途中恐ろしい話に勇気を失い、コロン港へ着くや、ここには死が住んでいるといって次の船で帰る者もあった。
「我々は天幕中に帆布のコット(注:折りたたみ式簡易ベッド)に蚊帳を吊って寝、土人は大概パーム(注:ヤシ)の種類の葉にて葺(ルビふ)いた掘建(ほったて)小屋で(中略)毛布一枚へくるまって寝るのであります」
青山はこう書いている。(「ぱなま運河の話」)。
青山はゴールド組に所属していたが、黄色人種の技術者であり、現場作業の経験もないことから、低い地位からスタートせざるを得なかった。1905年頃撮影された技術陣の記念写真を見ても、まっ黒に日焼けした青山は、アメリカ白人のグループ(士官グループ)に属していたことは間違いない。彼は現地労働者の逃亡やストライキを日記などに記述しており、末端労働者に同情を寄せている。アメリカ政府は、疫病や事故の防止策として風土病根絶対策を徹底して行った。現場の福利厚生の充実にも努めた。
青山はジャングルの中で下痢にかかり何の手当ての術もなく3~4日絶食を強いられ、1週間後にめまいのする身体を労働者に背負ってもらい前線基地に帰って来た。雨期には、豪雨に打たれての作業である。豪雨で水かさが増した川幅10mほどの谷川を測量手帳(野帳)を口にくわえて渡っている際に、激流に流され滝壺の直前で濁流から脱出して岸にたどり着いたこともあった。
「死んではならぬ。パナマ運河で働く唯一人の日本人なのだ。死んではならぬ」と自らを励ました。猛獣、大蛇などの爬虫類、ワシやタカなどの猛禽類に出くわすことはたびたびで、大きなアリやハチに刺されることも珍しくなかった。明治38年(1905)には、伝染病の黄熱病が大流行した。「恐怖の年」と言われ、帰国者や作業現場を捨てて逃亡する労働者が続出した。こうして「泥と汗にまみれた」2年半のジャングル生活が経過する。
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事


中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17





今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12



海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方