不安定な運営基盤を意識したガバナンス指針
第9回:「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」について3

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2022/03/30
スポーツから学ぶガバナンス・コンプライアンス

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。

前回、スポーツ庁より策定・公表されている「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に関して、そもそも中央競技団体とはどういった組織なのか、その規模等の実態についてご紹介しました。
まず、人的規模(役職員)の観点では、①役員と職員等との人数比に照らすと、意思決定機能と業務遂行機能との関係で、業務遂行機能が脆弱であるのではないか、②役職員における非常勤・非正規の占める割合の大きさに照らすと、意思決定機能においても、業務遂行機能においても、不安定な要素が大きいのではないか、ということが推察され、一部の規模の大きな団体は別として、意思決定においても、業務遂行においても、脆弱性をはらむ人員構成・組織構成になっているということができるかもしれないことをお伝えしました。

次に、収入の観点では、約2割を「補助金・助成金」(=公的資金)に頼っていることから、仮に不祥事等を理由にそれらが打ち切られてしまうと、組織運営・業務遂行に支障を来してしまい、ひいては当該スポーツの振興が滞ってしまうであろうことは想像に難くない財務基盤であることをお伝えしました。
スポーツ振興等の要の役割を担っている中央競技団体に公的資金を投入することは、スポーツ振興にとって有益であり不可欠なのですが、それはあくまで公的資金の源泉たる国民・市民(=社会)によるスポーツへの信頼・応援があってはじめて可能となるものです。
そして、スポーツ団体(この場合は中央競技団体)の適正・適切なガバナンスがなければスポーツ・インテグリティが損なわれてしまい、その帰結として、国民・市民(=社会)によるスポーツへの応援・信頼が失われてしまうという関係にあるのです。
こういった事態を防ぐために「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」が策定・公表されていると理解することができます。
それでは、同ガバナンスコードは、スポーツ・インテグリティを確保するためにどういった定めを設けているのでしょうか。連載第9回となる今回は、これについてご紹介したいと思います。
スポーツから学ぶガバナンス・コンプライアンスの他の記事
おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/09/16


ラストワンマイル問題をドローンで解決へBCPの開拓領域に挑む
2025年4月、全国の医療・福祉施設を中心に給食サービスを展開する富士産業株式会社(東京都港区)が、被災地における「ラストワンマイル問題」の解消に向けドローン活用の取り組みを始めた。「食事」は生命活動のインフラであり、非常時においてはより一層重要性が高まる。
2025/09/15


機能する災害対応の仕組みと態勢を人中心に探究
防災・BCP教育やコンサルティングを行うベンチャー企業のYTCらぼ。NTTグループで企業の災害対応リーダーの育成に携わってきた藤田幸憲氏が独立、起業しました。人と組織をゆるやかにつなげ、互いの情報や知見を共有しながら、いざというとき機能する災害対応態勢を探究する同社の理念、目指すゴールイメージを聞きました。
2025/09/14



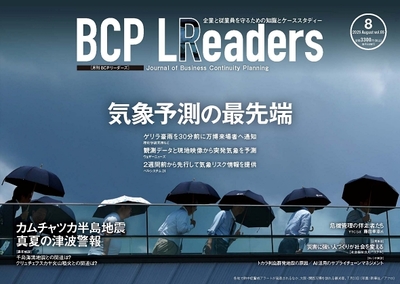
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/09/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方