連載・コラム
-

-
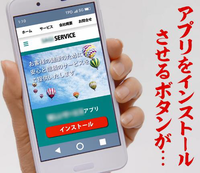
-
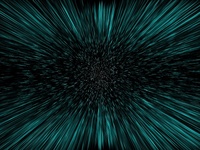
-

-

-

-

-

-

-

5日より先の台風予測が知りたい時に見る情報
日本の気象庁は、台風や台風に発達する見込みの熱帯低気圧について現在5日先までの予報を提供しています。2019年までは3日先までの予報しか発表されておらず、熱帯低気圧の情報に至っては2020年までは24時間先までしか提供されていませんでした。このため、5日先の情報が入手できるようになったことは大きな一歩であったのですが、「もっと先の予測があればぜひ参考にしたい」と思われている方も多いかもしれません。 そのようなニーズを満たすために、報道機関や民間気象会社などは海外の気象機関による台風予測の結果を紹介する形で5日先以降の傾向を示す例があります。2022年台風11号の際にもそうしたニュースや配信記事を見かけました(下図参照)。こうした場面で引用される図にはアンサンブル予報と呼ばれる手法で導き出された予測が反映されています。そこで今回の記事では、アンサンブル予報に関する基本的な知識をまとめていきます。また、海外の台風予測を自分で確認できるウエブサイトの例として、GPV WeatherやReal Time Tropical Cyclonesを紹介します。
2022/09/02
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
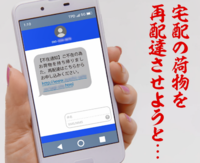
-


































![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



